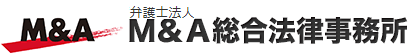後継者問題などで事業譲渡を検討しているため、メリット・デメリットと実際の流れなどを押さえておきたい方もいらっしゃるのではないでしょうか。
この記事では、売り手・買い手の各立場からみた事業譲渡のメリット及びデメリット、必要な手続きの流れ、最も大切な契約である「事業譲渡契約書」を結ぶうえでの注意点を解説します。
事業譲渡M&Aのメリット及びデメリット
事業譲渡は、事業の全部もしくは一部を、第三者である買い手会社に譲渡する手続きです。
事業譲渡には、売り手(譲渡会社)と買い手(譲受会社)、それぞれの立場からみたときに次のメリットとデメリットがあります。
売り手(譲渡会社)
メリット
- 不採算事業の譲渡により、事業の選択と集中ができる
- 残したい事業や資産が選べる
- 現金が手に入る
デメリット
- 手続きの負荷が大きい
- 譲渡後、同一事業の運営が制限される
- 債務が残る可能性がある
- 譲渡益に課税される
買い手(譲受会社)
メリット
- 望んだ事業だけ譲り受ければよい
- 簿外債務など想定外のリスクを承継する確率が低め
- 節税が可能
デメリット
- 手続きの負荷が大きい
- 契約や許認可を承継できない
- 有能な人材が流出する可能性がある
- 消費税が課税される
売り手からみた事業譲渡M&Aのメリット
売り手からみた事業譲渡のメリットは次の点です。
不採算事業の譲渡により、事業の選択と集中ができる
譲渡する事業を選べるため、採算がとれない事業の譲渡により得た資金や浮いたコスト・人材を、採算が見込める事業に注ぎ込んで事業の選択と集中が図れ、より効率的な経営ができます。
残したい事業や資産が選べる
株式譲渡では会社丸ごとの譲渡となるため、事業や資産、従業員などの一部を選んで手元に残すことはできませんが、事業譲渡では可能です。
現金が手に入る
事業譲渡では株式交換などとは異なり、譲渡の対価としてまとまった金額の現金が手に入ります。シンプルなメリットですが、現金があれば経営の立て直しから生活資金まで様々な用途に充てることができ、特に中小企業のオーナーにとっては魅力的なポイントです。
売り手からみた事業譲渡M&Aのデメリット
売り手からみた事業譲渡のデメリットは次の点です。
手続きの負荷が大きい
事業譲渡は株式譲渡と比べると、たとえば不動産などの各資産ごとの名義変更が必要など、手続きの負荷が大きくなる傾向があります。
ただし、家族経営の中小企業などでは、そもそも名義変更や再契約が求められる資産や契約などの数が少ないため、この点がそれほど問題にならないケースも多いです。
譲渡後に同一事業の運営が制限される
売り手は事業譲渡から20年間、同じ・隣接する市町村内において、譲渡した事業と同じ事業の運営を禁止されます。
ただし、この規制は買い手との取り決めがない場合に適用されるので、買い手と上手く交渉すれば、このような制限をゼロにするのも可能です。
債務が残る可能性がある
株式渡は会社丸ごとの譲渡なため、債務も丸ごと承継されます。しかし、事業譲渡では買い手が承継する内容を契約で取り決め可能なため、債務は残ってしまう可能性があります。
譲渡益に課税される
事業譲渡では、譲渡益に約30%の法人税が課税されます。株式譲渡の場合は、株主であるオーナーに課税されるのは20%の所得税なので、それと比べると高い傾向です。
ですが、役員退職慰労金などで所得を抑えたり、繰越欠損金を保持していたりするケースでは、株式譲渡と比べて税金を低めに抑えるのも可能です。
買い手からみた事業譲渡M&Aのメリット
一方、買い手からみた事業譲渡のメリットは次の点です。
望んだ事業だけ譲り受ければよい
株式譲渡では会社を丸ごと承継するため、不要な事業も承継せざるを得ません。一方、事業譲渡では必要な事業とそれに付随する資産・負債だけを譲り受けることができます。
たとえば、赤字会社の中でひとつだけ有望な事業があるケースで、有望な事業のみ事業譲渡して、赤字会社の負債は引受けないということも可能です。
簿外債務など想定外のリスクを承継する確率が低め
事業だけではなく、承継する資産や負債も選べるため、株式譲渡と比べて、簿外債務など当初は想定できなかったリスクを承継する確率を抑えられます。
節税が可能
買い手が事業の将来性や無形資産に魅力を感じ、純資産額よりも高い金額で事業を買収した場合、その差額がのれん代となります。この場合、のれん代を損金として5年間償却できるため、法人税を節税できます。
買い手からみた事業譲渡M&Aのデメリット
買い手からみた事業譲渡のデメリットは次の点です。
手続きの負荷が大きい
売り手と同じく、手続きの負荷が大きい点がデメリットです。
契約や許認可を承継できない
手続きの負荷として、特に買い手側では、従業員との雇用契約や取引先との各種契約、事業に必要な許認可などが自動的には承継されないため、再契約が必要という大きな手間が発生します。
有能な人材が流出する可能性がある
従業員との雇用契約が当然には引き継がれないため、有能な従業員を引き継ぎたいと思っても、当人の同意が得られず転職されてしまう可能性もあります。
消費税が課税される
株式譲渡では株式に消費税はかかりませんが、事業譲渡では固定資産や棚卸資産など事業における課税資産に対して消費税がかかります。
このように事業譲渡の主なメリットは、必要な事業や資産のみを譲渡できる点であり、主なデメリットは、資産などを個別に譲渡できるがゆえに手続きが煩雑な点です。
事業譲渡M&Aの手続の流れ
実際に、事業譲渡を行ううえで必要な手続きの流れは次のようになります。
- 取締役会での決議を得る
- 譲渡先の候補を探す
- 意向表明書
- 基本合意契約書
- デューデリジェンス(DD)
- 事業譲渡契約書
- 株主への通知や公告
- 株主総会での特別決議
- 引き継ぎや諸手続きなど
それぞれの手続きを具体的に見ていきましょう。
取締役会での決議を得る
まず、事業譲渡を行うことについて、取締役会での決議を得ることが必要です。譲渡する事業はどれになるのか、どのくらいの期間を交渉に充てるのかなど大筋の内容について申し合わせをします。
譲渡先の候補を探す
事業を譲渡する候補企業を探します。候補先のコネクションなどがない場合は、M&Aの仲介会社などに依頼する方法もあります。
事業譲渡やM&Aはお見合いに例えられることが多く、よい譲渡先を見つけられるかどうかは相手先候補とのマッチングも大きな要素です。
たとえば、ある地方での赤字事業について、再建の余力がない自社にとっては負担でしかないけれど、その地方でのコネクションが欲しい大企業にとっては魅力に映ることもあるなど、意外な事業が売れる可能性もあります。
それゆえ、譲渡先の候補を探す段階で大切な要素のひとつに挙げられるのは、いかに多くの候補先を挙げられるかという点です。
譲渡先候補(買い手候補)が見つかり、双方が話を進めたいと思ったら、両社の経営陣間で面談の場をもちます。売り手の事業理念や事業方針、譲渡するうえで譲れない条件や金額など、基本的な面での話し合いを行います。
意向表明書
面談を重ねて基本的な条件で合意し、買い手候補がさらに話を進めたいと希望する場合は、売り手に「意向表明書」を渡します。
意向表明書には、譲り受ける事業の内容や範囲、買収価額など、買い手が提示する基本的な条件が記載されています。
基本合意書
双方が意向表明書で提示された内容に合意できれば、取締役会の承認を得たのちに「基本合意書」の締結に至ります。
基本合意書には、事業譲渡についての基本的な条件や買収価額、譲渡全体の日程、デューデリジェンス(DD)、独占交渉権などについて記載されています。
なお、基本合意書の時点では法的拘束力がなく、その旨について記載があるケースもあります。
デューデリジェンス(DD)
買い手は基本合意書を締結した後、譲渡される事業について売り手から得た情報と事業の実情が一致しているかなどを調べるため、弁護士などの専門家に依頼してデューデリジェンス(DD)(買収調査)を実施します。
事業譲渡におけるデューデリジェンス(DD)は、譲渡される事業のみが対象です。買収価額の算出や、対象事業に係る資産や負債、従業員、契約や許認可などについての権利義務など、法務面・財務面・税務面など多岐にわたる調査となります。
デューデリジェンス(DD)を行うことで、買い手は譲渡される事業の実態や簿外債務など予想されるリスクを把握し、対策の立案や買収価額の調整・交渉などを行います。
事業譲渡契約書
デューデリジェンス(DD)の結果を踏まえて最終的な交渉などを行い、取締役会の承認を経たうえで「事業譲渡契約書」の締結に至ります。
事業譲渡契約書には、譲渡の対象となる事業や資産などの範囲や詳細、譲渡価額、譲渡や移転に関する日程、支払方法、従業員などの引き継ぎ、競争避止義務、契約の効力発生日などについて記載されています。
事業譲渡契約書では、売り手が契約書に記載された内容は正しいと表明する「表明保証」を行います。そのため、これ以降の段階で、事業譲渡契約書の内容と実際の事業とに乖離がある事実が判明した場合、売り手は損害賠償請求を受けるリスクがある点に注意しましょう。
届出書などの提出が必要なケース
事業譲渡契約を結んだ後に、場合によっては次の届出などが必要なケースがあります。
公正取引委員会に対する届出
買い手において、国内における総売上高が200億円を上回る場合、次の条件に該当するなら、公正取引委員会に対して届出をする義務が生じます。
- 売り手の全事業を譲り受ける場合に、売り手の国内売上高
- 譲り受ける一部の事業における国内売上高
- 譲り受ける事業に関連する固定資産における国内売上高
のいずれかが30億円を上回っているとき
臨時報告書の提出
有価証券報告書の提出が必要な会社においては、次の条件にあてはまるなら、内閣総理大臣に対して臨時報告書を提出する義務が生じます。
・事業の譲渡あるいは譲受のため、最近事業年度の末日時点における純資産額と比べて、資産額が3割以上増減するとき
・事業の譲渡あるいは譲受のため、最近事業年度の実績と比べて、売上高が1割以上増減するとき
株主への通知や公告
事業譲渡を行う会社は、事業譲渡契約の効力が発生する日の20日前までに、事業譲渡の実施について、株主へと通知する義務があります。
ただし、後述する株主総会にて特別決議を得た場合には、公告だけでよいと定められています。
株主総会での特別決議
事業譲渡を行う会社は、場合に応じて、事業譲渡契約の効力が発生する日の前日までに、事業譲渡について株主総会での特別決議を得る必要があります。
特別決議とは、議決権(株主総会の決議に投票できる権利)において過半数以上をもつ株主が株主総会に出席したうえで、そのうちの3分の2以上の賛成が必要な決議です。
次の場合に、株主総会での特別決議が必要となります。
- 売り手(譲渡会社):事業の全部あるいは一部(総資産の5分の1以上)を譲渡するとき
- 買い手(譲受会社):売り手から事業の全部を譲り受けるとき
一方、次の場合は株主総会での別決議は必要ありません。
- 簡易事業譲渡:売り手が譲渡する事業の帳簿価額が、総資産の5分の1を上回らないとき
- 略式事業譲渡:買い手が、売り手会社における90%以上の議決権をもっているとき
株式買取請求
事業譲渡に対して反対する株主が株式買取請求を行った場合、事業譲渡契約の効力が発生する日から数えて60日以内に、支払のための手続きを取る義務があります。
引き継ぎや諸手続きなど
株主総会での特別決議が得られたら、事業に関連する資産や負債、権利や契約などを譲受企業へと移転する手続きや、のれんやノウハウなどの無形資産の引き継ぎなどを行います。
事業譲渡では、事業に関連する土地や預金などの資産を個別に譲渡する必要があり、売り手の社名で登録された資産を、買い手の社名で登録・登記する手間が生じます。
また、事業に関連する従業員との雇用契約なども従業員と買い手とで結び直したり、事業に必要な許認可も買い手の名義で取り直したりすることが必要です。
事業譲渡契約書の注意点
事業譲渡は、事業に付随する個々の財産をひとつの商品とみなして取引する売買契約であると考えることが可能です。
それゆえ、事業譲渡契約書を作成するうえでのポイントは売買契約書と同じ考え方ができるので、次についての事項を記載する必要があります。
A.譲渡の対象となる事業や財産の特定
B.譲渡の対価
一方、事業譲渡は単なる売買契約とは異なり、株主総会の特別決議が必要など一定の法規制が定められていたり、売り手と従業員との雇用契約が買い手に引き継がれない等の特徴があったりするため、次についての事項も大切です。
C.法令上必要な手続きや規制
D.従業員の処遇
E.その他契約に必要な事項
まとめると、事業譲渡契約書には次の項目などが記載されることが多いです。
A-1.譲渡の対象となる事業の特定・譲渡日
A-2.譲渡の対象となる財産の特定・移転手続き
B-1.譲渡の対価・支払方法
B-2.公租公課の負担
C-1.譲渡に必要な手続き
C-2.競業避止義務
C-3.商号を続用する際の免責登記
D.従業員の処遇
E-1.表明保証
E-2.売り手における善管注意義務
E-3.契約解除 など
上記の項目において、どのような点に注意が必要かを順番に解説していきます。
譲渡の対象となる事業の特定・譲渡日
どの事業が譲渡の対象となるのかを、第三者にも分かるように一つひとつ明記する必要があります。
譲渡日に対しては、クロージング日を記載するケースが多いです。また、譲渡日は必要があれば協議した上で変更できるといった旨の一文を追加しておけば、譲渡日の変更も可能になります。
譲渡の対象となる財産の特定・移転手続き
事業に帰属する財産に対しても、どの財産が譲渡の対象となるのかをはっきり明示することが非常に重要です。
財産は主に、資産・債務・債権に分かれるため、それぞれを特定して別々の目録にまとめて契約書に添付する必要があります。
また、財産を移転する時期、移転に要する承認や引き渡し、登記といった手続き、費用負担に対しても明記が必要です。財産の移転時期に関しては、譲渡日あるいは譲渡日から30日以内などと設定するケースがあります。
資産
事業に帰属する資産として挙げられるのは、たとえば、預金額、在庫や仕掛り品、建物に付属する設備・器具備品・車両運搬具・機械装置・不動産、知的財産権や営業権、その他無形資産などです。
それぞれを列挙して評価価格を算定し目録にまとめます。すべてを網羅するのが困難な場合は、事業に帰属する一切の資産という旨の包括的な一文を記載し、但し書きで対象に含めない資産を除外していく方法もあります。
譲渡する資産に瑕疵があった場合どうするかに対しては、立場に応じて自社に有利な文言を明記しておきましょう。
- 売り手:責任を負わない旨を明記
- 買い手:売り手が責任を負う旨を明記
著作権
事業に帰属するホームページや商標などの著作権に対しても、立場に応じて自社に有利な文言を明記しておく必要があります。
- 売り手:事業に帰属する著作物を譲渡後も使いたい場合は、譲渡の対象に含まない旨を明記
- 買い手:事業に帰属する著作権その他知的財産権は譲渡の対象となる旨を明記
譲受会社が特に注意したいのは、譲渡対象にホームページやアプリケーション、プログラムなどが含まれるケースです。
著作物には、著作権のほかに「著作者人格権」と呼ばれる権利が存在し、この権利は譲渡できません。
著作者人格権には、同一性保持権(断りなく著作権を修正されないための権利)があるため、事業譲渡後であっても、売り手が著作権人格権を主張した場合、買い手はホームページなどの変更ができなくなります。
それゆえ、買い手は売り手に、著作権人格権の行使をしないよう契約書に明記させる必要があります。
債務
事業に帰属する債務には、仕入債務・未払給料・リース債務などの流動負債、社債や長期借入金などの固定負債を目録にまとめます。債務の承継に際ては、個別の契約において債務の承継を禁止していないかの確認や、債権者への通知・承認が必要です。
売り手が中小企業の場合、オーナーが債務の連帯保証人となっているケースが大半ですので、譲渡後は連帯保証人から外れることができるような手続きを明記するとよいでしょう。
また、債務承継後においても、債権者が売り手に支払を求めた場合は応じる必要があるため、そうした場合には売り手から買い手に請求ができる旨の条項を記載しておく必要があります。
一方、買い手が特に注意したいのは、事業譲渡後に想定外の未払債務が発生するリスクです。目録に明記されていない債務は引き継がないといった旨の一文を必ず入れておきましょう。
債権
事業に帰属する債権についても目録にまとめます。債権譲渡に対しても、債務の承継と同じく、個別の契約において債権譲渡を禁止していないかの確認や、債務者への通知・承認が必要です。
契約
事業譲渡では、事業に帰属する契約は引き継がれません。買い手が個別に契約を結び直す必要があります。
事業を左右するような重要な契約に対しては、買い手が契約を承継することを契約相手が承認してくれるかに関する事前の打診が重要です。
譲渡の対価・支払方法
譲渡の対価は適切な価格を算定する必要があるため、弁護士などの専門家による助言が必要です。
対価となる金額は、事業譲渡契約日時点での財産評価額に基づいて算定が行われます。しかし、契約日から事業譲渡における効力発生日までに、評価額が変動することも予想されます。
価格の変動に対応できるよう、たとえば契約日時点では仮の金額を設定して、第三者に評価額を再評価してもらう日程を確保しておくなどの条項を設定しておく方法もあります。
財産評価額は、売り手から提出される決算書類などをもとに算定されます。それゆえ、買い手側には、売り手が提出する資料や情報が正しいものであると、財産評価額の保証をさせる条項の追加が重要です。
また、対価が確実に支払われるように、支払日や一括・分割、口座振込や手形振出しなどの支払方法、振込手数料の負担先なども明記します。
公租公課の負担
公租公課とは、国に対して支払う税金や社会保険料などです。譲渡日を境とし、売り手が譲渡日の前まで、買い手が譲渡日の後から負担するのが一般的です。各々の支払金額と、間違って支払った分は相手に精算を要求できる旨などを明記しておきましょう。
譲渡に必要な手続き
先述したように、事業譲渡には取締役会や株主総会での決議といった手続きが求められます。法令上の手続きを踏まないと事業譲渡の効力が発生しないため、契約書に必要な手続きの実施を保証する条項を記載しましょう。
競業避止義務
会社法では、売り手は事業譲渡から20年間は、同じ・隣接する市町村内にて譲渡した事業と同一の事業の運営を禁止されています(競業避止義務)。
しかし、これは当事者間で取り決めがない場合の規制であるため、事業譲渡契約書では競業避止義務に対して条項を定めるのが一般的です。自社がどちらの立場かで、次のように注意点が異なります。
- 売り手:競業避止義務を負う範囲を、可能な限り小さくするよう設定
- 買い手:売り手が競業避止義務を負う範囲を、可能な限り大きくするよう設定
売り手にとっては、競業避止義務を全く負わない、または期間などをできるだけ短く設定したいです。一方、買い手にとっては、期間を上限30年への設定、競合事業を含む禁止、場所を限定しない競業禁止などと、売り手が負う禁止範囲をできるだけ大きくしておきたいでしょう。
商号を続用する際の免責登記
買い手が売り手から商号を承継し続けて使うケースでは、事業を運営する主体が変更した事実が第三者に伝わりづらいです。
こうした事情から会社法では、事業譲渡後もこれまでの商号を買い手が使い続ける場合は、事業譲渡の以前に生じた債務に対しても、買い手には弁済が義務づけられています。
しかし、免責登記を行えば弁済の義務はなくなるため、免責登記を行う際には契約書へと、売り手に必要書類の交付など協力を義務づける条項を加えておくことが大切です。
従業員の処遇
事業譲渡では、従業員の雇用契約は本人の同意がなければ、売り手から買い手に引き継がれません。それゆえ、従業員との雇用契約における「使用者」の地位をどうするかを、事前に決めておくことが必要です。
買い手が使用者の地位を承継する場合
買い手が使用者の地位を承継する場合には、契約書に従業員の雇用条件などの処遇を明記し、従業員の同意を効力発生日までに得るなどの条項を記載します。
また、従業員には売り手会社を一旦退職してもらって、買い手が再雇用するという手法がとられるケースも多いです。その場合は契約書に、退職と再雇用という形式を譲渡日にとる旨と、譲渡日までに従業員から承諾をもらえるよう売り手が協力する旨を明記します。
未払給料や退職金などの債務、勤続年数、未消化の有給数などの承継や、雇用条件は売り手会社を引き継ぐのか、買い手会社を適用するのかなども、事前に契約書で設定しておきましょう。
買い手が使用者の地位を承継しない場合
従業員の籍は売り手会社に残すという選択もあります。買い手はこの場合、雇用関係は承継しない旨を契約書に定めておきましょう。
ただし、従業員が転籍しない場合は事業のノウハウも得られない不安があるなら、買い手会社から売り手会社に一定期間従業員を出向させる旨を契約書に明記しておく方法もあります。この場合には、出向命令権の濫用にあたらないよう配慮が必要です。
表明保証
売り手・買い手ともに、契約の締結日時点で、契約内容・財産や従業員などの移転内容・手続きなど契約で取り上げられた内容に関して虚偽事項がないことを保証するのが表明保証です。
表明した内容と事実とに乖離があった場合には損害賠償請求が可能なため、特に買い手は設定しておきましょう。売り手は表明内容に虚偽がないよう注意が必要です。
売り手における善管注意義務
事業譲渡契約書を交わした後に、突然売り手が財産処分を行うなどのリスクも可能性は低いですが存在はします。それゆえ契約書にて、買い手は売り手に善管注意義務を義務づける条項を設定しておいたほうがよいでしょう。
契約解除
倒産や違反事実、想定外の事実の顕在化など、事業譲渡の手続きが続行できない事態が生じる可能性もあるため、どういった事実が起こった場合に契約を解除できるか、解除条件に対しても定めておきましょう。
まとめ
事業譲渡には、株式譲渡とは異なり、必要な事業とそれに付随する資産などを自由に譲渡できるという大きなメリットがあります。
反面、資産などを個別に譲渡する手続きが必要になるため、手続きは煩雑です。
最も大事な事業譲渡契約書についても、先述しように多種多様な注意点があり、専門的な知識なしには締結は不可能です。
煩雑な手続きというデメリットに悩まされずに、事業譲渡で最大限の効果を上げるためには、事業譲渡のプロであるM&A專門の弁護士にご依頼されることをお薦めします。