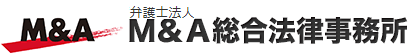- 1 株式譲渡契約書の逐条解説 一般条項
- 2 株式譲渡契約書の逐条解説 一般条項
- 2.1 ■■■第23条■■■■■■■■■■
- 2.2 費用の負担に関する規定について
- 2.3 遵守条項の履行費用について
- 2.4 変更登記費用などについて
- 2.5 金融機関から融資(LBOローン)や法律意見書に関連する費用について
- 2.6 ■■■第24条■■■■■■■■■■
- 2.7 東日本大震災と不可抗力条項について
- 2.8 リーマンショックと不可抗力条項について
- 2.9 ■■■第25条■■■■■■■■■■
- 2.10 譲渡禁止の規定について
- 2.11 株式譲渡契約書を譲渡すべき場合について
- 2.12 ■■■第26条■■■■■■■■■■
- 2.13 ■■■第27条■■■■■■■■■■
- 2.14 ■■■第28条■■■■■■■■■■
- 2.15 ■■■第29条■■■■■■■■■■
- 2.16 ■■■第30条■■■■■■■■■■
- 2.17 ■■■署名欄■■■■■■■■■■
- 2.18 代表者が署名押印しない場合について
株式譲渡契約書の逐条解説 一般条項
弁護士法人M&A総合法律事務所のM&A契約書類のフォーマットはメガバンクや大手M&A会社においても、頻繁に使用されています。
ここに弁護士法人M&A総合法律事務所の株式譲渡契約書のフォーマットを掲載しています。
M&Aを検討中の経営者の皆様でしたらご自由にご利用いただいて問題ございません。
ただし、M&A案件は個別具体的であり、このまま使用すると事故が起きるものと思われ、実際のM&A案件の際には、弁護士法人M&A総合法律事務所にご相談頂くことを強くお勧めします。
また、このフォーマットは弁護士法人M&A総合法律事務所のフォーマットのうちもっとも簡潔化させたフォーマットですので、実際のM&A取引において、これより内容の薄いDRAFTが出てきた場合は、なにか重要な欠落があると考えてよいと思われますので、やはり、実際のM&A案件の際には、弁護士法人M&A総合法律事務所にご相談頂くことを強くお勧めします。
なお、詳細な解説につきましては、以下の弊所書籍「事業承継M&Aの実務」をご覧ください。
株式譲渡契約書の逐条解説 一般条項
■■■第23条■■■■■■■■■■
第23条は、費用の負担に関する規定である。 費用の負担に関する規定について本条は、各自の費用は各自の負担とだけ規定する。 ただし、事業承継M&Aに関する費用には様々なものがあり、各自の負担とすれば、すべて公平性が担保されるほど単純ではない。 遵守条項の履行費用について株式譲渡契約書には、すでに述べた通り、多数の遵守条項が存在し、売主も買主もそれを履行するにはそれなりのコストが発生することがある。 例えば、売主に対して、遵守条項として、クロージングまでに、対象会社の就業規則を作成するという規定があった場合、対象会社において、就業規則を作成するために、弁護士又は社会保険労務士を指名し、報酬を支払うこととなる。その報酬は、だれが負担するのかと考えると、対象会社が負担することが一般的である。 しかし、対象会社において、就業規則が作成されていなかったというのは、売主である旧オーナー経営者の怠慢なのではないかとも考えられる。 対象会社が就業規則の作成の費用を負担するとなると、その対象会社を買収するのは買主なのだから、総合的にみると、買主が対象会社を通じてその費用を負担したということになるのではないかとも思われる。そうであるならば、買主としては、株式譲渡価格をその分減額する必要があるだろう。もし、株式譲渡価格をその分減額しないのであれば。対象会社が就業規則の作成の費用を負担してしまうと、対象会社の企業価値がその分減少してしまう。そう考えると、対象会社の就業規則の作成の費用は、売主である旧オーナー経営者が負担するべきではないかとも思えるが、売主である旧オーナー経営者が対象会社の就業規則の作成の費用を負担するための遵守条項は規定されていないことが多い。 就業規則の作成の費用であればそれほどの金額にはならないが、事業承継M&Aに伴い、対象事業を会社分割する会社分割方式の場合は、その会社分割手続きの費用や会社分割の登記費用は、誰が負担するかも大きな問題となる。 各自の費用は各自の負担とだけ規定する場合は、特段の規定がなければ、対象会社がその費用を負担し、事業承継M&Aのクロージングに伴い、実質的に買主の負担ということとなってしまうが、その個別の遵守条項において、費用負担を明記することにより、売主に費用負担をさせるべき場合が多く存在するのである。 変更登記費用などについてまた、クロージング前後における臨時株主総会の開催の費用や、クロージングに伴い、売主側の役員が辞任し、買主側の役員が就任する場合の登記費用なども、売主又は買主のどちらが負担するべきか問題になることが多い。 この点、事業承継M&Aのクロージングに伴い、臨時株主総会が開催されるのは、一般的にクロージングの直後であり、したがって、役員変更登記を行うのもクロージングの後であることから、その費用は対象会社が負担し、実質的に買主の負担となることが多いかと思われるが、買主としては、それを嫌って、クロージング前に臨時株主総会を開催し、役員を変更し、役員変更登記も済ましておくことを求めることも多い。その場合も、対象会社自身の費用であることから対象会社負担となり、結局、実質的に買主の費用負担となるものと思われるが、実務上は、売主の費用負担である旨明記することも多く、また、売主側役員の辞任に関する費用は売主負担、買主側役員の就任に関する費用は買主側負担とすることも多い。 また、対象会社が、取締役会非設置会社・監査役非設置会社となり一人代表取締役となっている場合も多く、買主としては、特に、中堅企業・大企業の場合、一般的な組織形態である取締役会設置会社・監査役設置会社に戻したい場合も多い。そのような場合、一般的ではない組織形態を採用していた売主である旧オーナー経営者が費用負担するべきではないかとも思われる。また、買主が、クロージングを契機に、対象会社を、管理が容易な取締役会非設置会社・監査役非設置会社の一人代表取締役にしたいと考えることもあり、そのような場合、その部分は、売主ではなく、買主が費用負担するべきとも思われる。すなわち、特殊な組織形態を採用した場合、それを採用した者が、費用負担をすることとされる場合が多い。 金融機関から融資(LBOローン)や法律意見書に関連する費用についてまた、買主が事業承継M&Aを行うに伴い金融機関から融資(LBOローン)を借りる場合には、金融機関に法律意見書の提出などが必要となり、その法律意見を形成する前提として、対象会社が数多くのクロージング書類を作成することとなるが(事業承継M&Aの対象会社は中小企業、零細企業のためそのような業務能力に欠けることもあり売主が対応することが多くなるが)、その作業には多大な費用が発生するところ、また、法律意見書作成の弁護士費用はとかく高額であるところ、その費用の全てを売主が負担するのか、買主が金融機関から融資(LBOローン)を借りるために必要な資料を、売主が労力と費用をかけて作成するのか、売主としても、買主や対象会社に費用負担して頂くのが自然なのではないかなどの問題が生ずる。 ■■■第24条■■■■■■■■■■
第24条は、不可抗力条項である。 事業承継M&Aにおいて、多くはないものの、予定していたM&Aを否応なく取り止める必要性に迫られることが存在する。 東日本大震災と不可抗力条項について特にこれが問題となったのは、まずは、東日本大震災の際である。東日本大震災の被害は甚大であり、その後、当面の間、対象会社が通常の事業運営の状態に戻ることができないことは明らかであった。対象会社が被災していなくとも、対象会社の取引先が被災したり、インフラが毀損したりして、対象会社はそれまで通りの事業運営や業績を上げることは著しく困難になったのである。すなわち、対象会社の企業価値は著しく毀損したのである。このような場合、買主は、対象会社の株式譲渡の実行を強行しなければならないとしたら、事業承継M&A直後から、直ちに大きな損害が発生することとなる。特に、東日本大震災は3月11日に発生したこともあり、非常に多くのM&A案件が、3月末のクロージングを目指して、株式譲渡締結を完了し、クロージングに向けて準備をしていた。 東日本大震災が発生した際、多くのM&A案件は、この不可抗力条項が入っていることを理由に、又は不可抗力条項が入っていない場合であっても当事者の合意により事実上、クロージングを停止し、ひとまずクロージングを延期し、最終的に、事業承継M&A自体が取り止めになったものが多く存在した。 他方、株式譲渡契約書にこの不可抗力条項が入っていなかったため、買主として、売主からクロージングの実行を迫られ、ここで買収したら直後から多額の損害が発生することを予測しつつも、紛争化することや損害賠償責任・補償責任を避けるため、泣く泣く、事業承継M&Aのクロージングを実行した事例も存在すると聞いている。 リーマンショックと不可抗力条項についてまた、特にこれが問題となったのは、リーマンショックの際である。 リーマンショックの前数年間は、未曾有のM&Aバブルであり、リーマンショックの際もM&Aバブルのピークは過ぎていたものの、余韻の冷めやらぬ中、多数のM&A案件が存在しており、クロージングを迎えていた。その際に、リーマンショックが発生した。買主としては、リーマンショックの後の、経済情勢の不透明感の強い中、M&Aを実行し、対象会社を買収したとしても、対象会社においてそれまでと同様の業績を上げることは著しく困難な状態である。すなわち、これも、対象会社の企業価値が著しく毀損してしまったのである。しかも、その帰責性は、売主にあるものでもなく、買主にあるものでもない。売主にも買主にも帰責性があるわけではなく、株式譲渡契約の解除事由も適用されない。株式譲渡契約書に不可抗力条項が規定されていなかった場合、買主は、泣く泣く、株式譲渡のクロージングを強行し、対象会社を買収しなければいけないこととなってしまう。 実際にこのような場合も想定されることから、事業承継M&Aの買主においては、対象会社の買収という小さからぬ買い物をするわけであることから、不可抗力状況を規定しつつ、やむを得ない場合には、不可抗力条項により、事業承継M&Aを取り止めることができるようにしておく必要があるものと思われる。 ■■■第25条■■■■■■■■■■
第25条は、譲渡禁止の規定である。 譲渡禁止の規定についてすなわち、この株式譲渡契約の当事者を、第三者に譲渡することを禁止する規定である。これは英米法上、契約書の一般条項として、一般的に規定されるものである。 これはいわば当然の規定である。売主としても、買主を信頼して対象会社を売却するのであり、買主としても、売主を信頼して対象会社を買収するのであるから、もし、株式譲渡契約の当事者を第三者に譲渡することができ、株式譲渡契約の当事者が他の第三者となるのであれば、事業承継M&Aは成立しないであろう。 英米法上、このような譲渡禁止規定が存在していないことを良いことに、契約当事者の地位を譲渡してしまう事例が生じたため、敢えて契約書にこの譲渡禁止を入れることとなった歴史がある。 株式譲渡契約書を譲渡すべき場合について日本においても、確かに、有望な会社を買収する株式譲渡契約を予め締結しておいて、クロージングまでに多めに日数を確保し、その間にマーケティングを行い、新しい買収希望会社を探し出し、より高い価格でその買収希望会社に売却するか、あるいは、この株式譲渡契約の買主の地位をその買収希望会社に譲渡してしまうことで利益を得る業者は存在してもおかしくはない。 実際、ファンドなどは、ファンド運営会社などがひとまず株式譲渡契約の当事者となり、クロージングまでに、ペーパー・カンパニー(SPC)を設立し、このペーパー・カンパニー(SPC)に対して、株式譲渡契約を譲渡することはまま行われる。また、ファンド運営会社がひとまず株式譲渡契約の当事者となり、クロージングまでに投資家の了解を得てその出資を確保し、買収主体となるファンドを設立し、そのファンドに対して、株式譲渡契約を譲渡し、そのファンドが対象会社を買収することもある。 このような場合には、株式譲渡契約の譲渡は許されることとなり、本条に基づき、売主の承諾を得て、株式譲渡契約の譲渡が行われるのである。 ■■■第26条■■■■■■■■■■
第26条は、通知に関する規定である。 事業承継M&Aのクロージング前はともかく、クロージング後において、売主と買主の間では何かとコミュニケーションが発生する。 クロージング前であれば、クロージングの準備などの実務的なコミュニケーションはもとより、第8条第2項に基づき、対象会社に、対象会社に重大な悪影響を及ぼすおそれのある事由が発生した場合において、売主は買主に対する通知義務が課されているが、このような通知は、本条に基づき行う必要がある。また、第22条に基づき、株式譲渡契約を解除する場合の通知も、本条に基づき行うこととなる。 また、株式譲渡契約書に明記されていない通知についても、株式譲渡に関する通知は、本条に基づき行う必要がある。すなわち、実務上発生するものは、買主から売主に対する表明保証違反や遵守条項違反行為に関する要請や警告の通知や、売主が株式譲渡契約の解消を求めている場合や、売主が他の買主候補者と交渉している場合に送付する警告書などは、本条に基づき送付することとなる。 また、株式譲渡のクロージング後についても、買主から売主に対する表明保証違反や遵守条項違反行為に関する要請や警告の通知や、損害賠償請求権・補償請求権の行使の通知などは、本条に基づき行うこととなる。 第26条では明確に記載していないが、日本の民法はいわゆる到達時説を採用し、通知は到達したときに有効になるのが原則であるものの、必ずしも到達しなくても発信しさえすれば通知が有効であると規定されることもあり(発信時説)、注意が必要である。また、当事者が、自らの故意又は過失によって、例えば、通知が届かないようなところに引っ越したり、FAX番号を変更したりして通知が届かなかった場合や、引っ越しをしたことによって通知が届かなくなった場合も、受信者の過失として、実際には通知が到達していなくても通知は有効であるとする規定がなされることもある。 そのような意味で、株式譲渡契約書には、当事者とも、明確に住所・氏名・FAX番号を記載し、株式譲渡のクロージング以降も当面はそれを維持すること、及び、通知先が変更になる場合は遅滞なく通知することを前提に、相手方当事者からの通知が相違なく届く状況にしておくことが必要となろう。 ■■■第27条■■■■■■■■■■
第27条は、完全合意条項である。 完全合意条項とは、当事者間の合意は、この株式譲渡契約書に記載されたもののみであり、それ以前になされた文章又は口頭の合意は全て無効とするものである。 たしかに、事業承継M&Aの手続の過程は長く、通常は、事業承継M&Aに本格的に取り組み始めてから半年程度、長いものでは2-3年越しの案件も多く、さらに事業承継M&Aの話になる前に、かなりの長期間にわたって、M&A専門家やM&A税理士が売主との間で相談に応じていることもあり、その過程で、売主と買主のみならず双方のアドバイザーや専門家も含めて、さまざまな口頭の合意をすることも多く、事業承継M&Aの後には、往々にして、「あのとき・・・という約束をしたはずだ」「・・・にするという話だった」という問題が生ずることが多い。 たしかに、日本法上、口頭での合意も有効であり、かつ書面がなくても、メールや録音、その他の周辺事情から、そのような口頭の合意があったことが証明できることも多い。 しかし、そのような合意が、株式譲渡契約書の内容と異なっていたり、矛盾していたりすると、後日混乱をきたすし、当事者の一方はそのような合意はすでに失効したと考えているのに対し、もう一方の当事者は有効と考えているなど、合意の状態が不明確な状態になっていたり、それが原因で後日トラブルになりそうな場合も多い。 したがって、そのような株式譲渡契約書外の合意を排除して無効化し、株式譲渡契約の内容を一元化するために、株式譲渡契約書においては、この完全合意条項が重要となるのである。 他方、事業承継M&Aの際には、株式譲渡契約書以外の契約書も締結されることも多い。 法的拘束力を有する可能性のある書類としては、秘密保持契約書、意向表明書、基本合意書があるし、事業承継M&Aのストラクチャーによっては、会社分割計画書・会社分割契約書、合弁契約書、商標譲渡契約書その他の知的財産権譲渡契約書、ライセンス契約書、業務委託契約書、顧問契約書などが締結される。株式譲渡契約書に完全合意条項を規定することで、そのような契約書の効力が失効させられてしまうことは避ける必要があり、契約書を特定したうえで、本条において除外文言を入れることもある。 なお、契約書の特定は、契約当事者名・契約締結日付・契約書名をもって行い、例えば、「売主及び買主の間の平成30年7月10日付け秘密保持契約書」などというように記載する。 その他、第27条は、売主と買主との間のその他の契約をすべて失効させるものではない。売主と買主との間には事業承継M&Aのみならず、通常の取引も存在する可能性があり(全く無い場合も多くあると思われるが)、そのような契約の効力を失効させるべきではない。そこで、第27条においては、「本契約の対象事項に関する」との文言が入っており、事業承継M&Aに関する事項についてのみの完全合意条項となっており、事業承継M&A以外の合意については失効させないような配慮がなされている。 ■■■第28条■■■■■■■■■■
第28条は、準拠法に関する規定である。 売主と買主の双方が日本人又は日本企業であれば、通常、準拠法は、日本法が選択される。このような準拠法の合意がなされれば、法の適用に関する通則法第7条に基づき、この株式譲渡契約書の準拠法は日本法になり、またこのような規定が存在していなくても、法の適用に関する通則法第8条に基づき、密接関連地法として、日本法が準拠法として選択されるものと思われるため、いずれにしろ事業承継M&Aの株式譲渡契約書の準拠法は日本法となるものと思われる。 第28条は、今日の、日本人・日本企業同士の一般的な事業承継M&Aにおいてはあまり問題になることはないものの、今後、外国人や外国法人の事業承継M&Aへの参入又は、多国籍企業の事業承継M&Aが生ずる場合などは、重要な論点として浮上してくる可能性は存在する。 この点、株式譲渡契約の準拠法を外国法としたとしても、いずれにしろ対象会社に適用されるのは日本法であり、業法も日本法が適用されるのであり、対象会社の所在や事業承継M&Aの取引は日本で行うのであるから、日本法を準拠法とすべきである。また、外国人に対して、事業承継M&Aを実行する場合も、米国などの自由主義国家の法律であれば、日本法同様、取引について特殊な制限は多く存在しないこともあり、また、国によっては、M&Aの準拠法は自国の法律が適用されるとする国もあることもあり、日本法を準拠法とすることに了解を頂く必要があるものと思われる。 ■■■第29条■■■■■■■■■■
第29条は 専属的合意管轄の規定である。 この規定がない場合は、民事訴訟法4条が適用になり、被告の所在地の裁判所が管轄になるため、売主又は買主のいずれが訴訟提起するかにより、管轄裁判所が異なってくる。 しかし、専属的合意管轄の規定を入れることにより、株式譲渡契約について紛争になった場合の管轄裁判所が一義的に明確になるのである。 この管轄裁判所をどこにするかは、多分に、交渉力によって決定することが多い。 また、専属的合意管轄は、売主の管轄裁判所又は買主の管轄裁判所になることが多いが、売主が原告になる場合は買主の管轄裁判所、買主が原告になる場合は売主の管轄裁判所と相互主義的に規定することもあるし、売主の管轄裁判所とも買主の管轄裁判所とも異なった第三の裁判所を指定することもある。 また、紛争解決は裁判所ではなく、仲裁機関で行うこととし、仲裁機関を指定することもある。特に、国際的な取引の場合、他の国の裁判所の判決については、他の国で承認・執行することができない可能性がある。例えば、日本の裁判所では、米国や韓国などの判決は承認・執行されることが可能であるものの、相互主義の観点から、中国の判決は承認・執行されないため、中国人又は中国法人が当事者になる場合、中国の裁判所を管轄指定することは意味をなさない。 他方、ニューヨーク条約に基づいて、中国の裁判所においても、日本の裁判所においても、仲裁機関の決定は承認・執行されるため、中国人又は中国法人が当事者になる場合、管轄裁判所の合意をするのではなく、仲裁合意をすることも多い。 なお、第28条とも関連するが、準拠法の合意をしたとしても、管轄裁判所が、準拠法の合意をした国と異なる場合、管轄裁判所において、その準拠法に基づいて審査することは、事実上困難である。そのような場合、管轄裁判所は、事実上、自国の法律に基づいて事案を検討し、審理を進めることとなる。したがって、外国人に対して、事業承継M&Aを実行するような場合は、準拠法もしかりではある者の、特に、管轄裁判所を日本の裁判所とする必要があるものと思われる。 ■■■第30条■■■■■■■■■■
第30条は、誠実協議義務の規定である。 日本人であれば、紛争について訴訟提起する前に誠実協議をすることは当然の前提のように思われるが、世界的にも必ずしもそうではない。また、日本における大企業においても、誠実協議の規定が存在することを根拠に、いきなり訴訟提起や交渉謝絶をするのではなく、社内検討の結果、まずは協議することとしようかと意思決定されることもある。また、誠実協議の規定が存在しない場合、同規定が存在しないことに不安を覚える当事者は存在するようであり、株式譲渡契約書においても、誠実協議義務の規定を入れることが一般的である。 ■■■署名欄■■■■■■■■■■
署名欄である。 なお、株式譲渡契約書を何通作成するかは、当事者の数により、各当事者が1通ずつ保管することが通常であるものの、売主が複数の場合、少数株主については、写しを作成して保管することもある。 代表者が署名押印しない場合についてまた、事業承継M&Aの買主が大企業の場合、代表取締役ではなく事業部長などが署名押印することもある。しかし、事業部長などは、必ずしも、会社の代表権は有しておらず、代表権がある者から代理権を与えられているかどうかは明らかではない。そこで、本来的には、売主としては、買主に対して、代表権のある者の署名押印を求めることが原則である。 この点、株式譲渡契約書に代理権を有しない事業部長などが署名押印し、後日、クロージング前に、対象会社の業績が悪化したような場合、買主の代表権を有していないものが署名押印していることをもって、買主が対象会社の買収を拒否することも十分考えられる。筆者らに実際に相談のあったケースでは、株式譲渡契約書ではないものの、通常の取引契約書の基本合意書などで、代表権がある者が署名押印していないことをもって、無責任な態度を取られたことも存在する。判例としても、代表権がある者が署名押印していない場合は、契約責任は発生しないとするものは多く存在するとの理解である。 ただ、買主がどうしても代表権を有する者の署名押印が困難だということであれば、その理由をしっかり確認し、その事業部長などの代理権の存在を委任状などで確認し、表明保証にその事業部長などが代理権を有する旨規定しつつ、その事業部長などの署名押印により株式譲渡契約書を締結することもある。 |