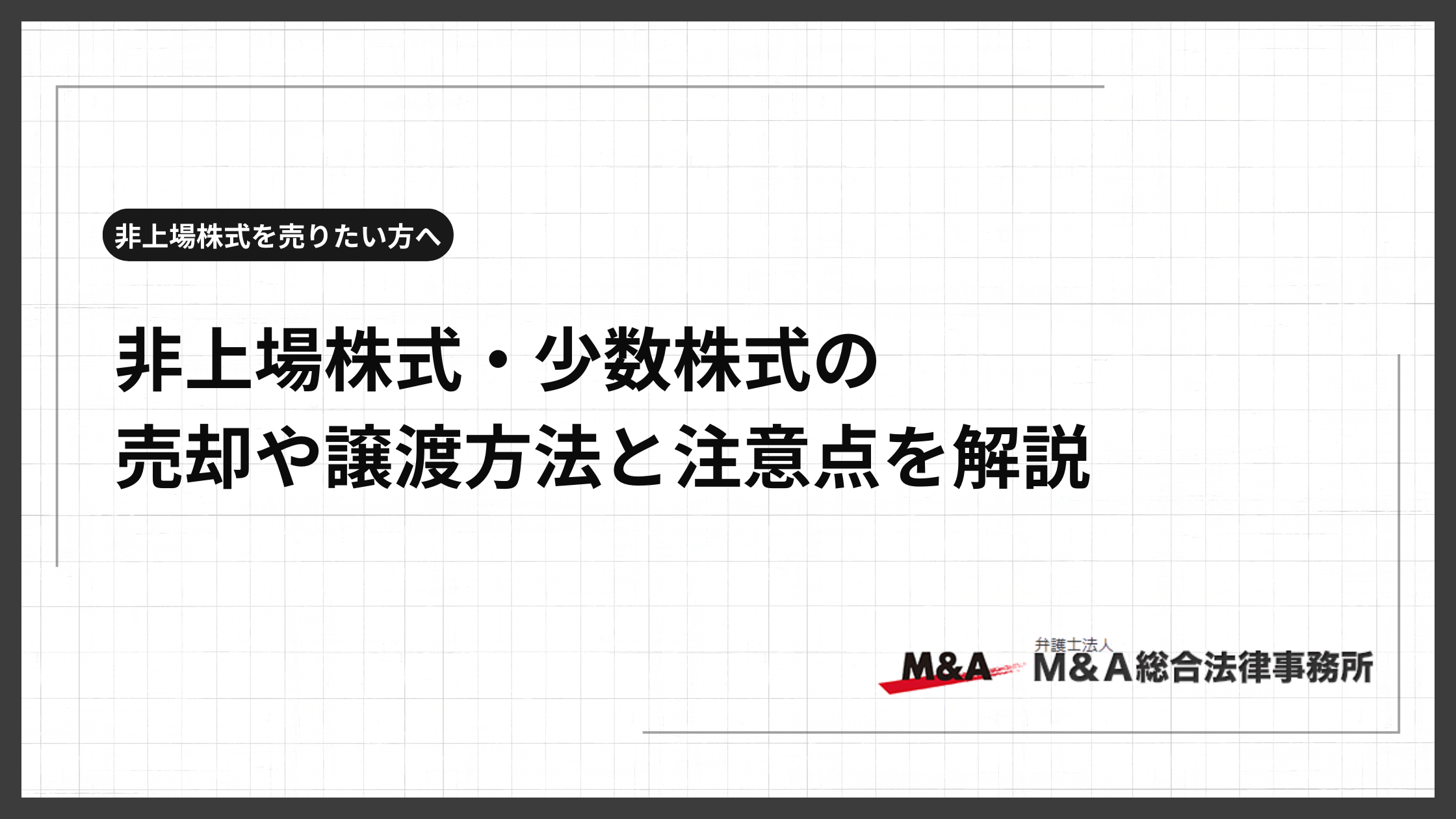
「相続で受け継いだ非上場株式や、少数株主として長年持ち続けてきた非上場株式を現金化したいのに方法がわからず困っている。」もしそのような状況に陥っているのであれば、このページの情報がお力になれます。
証券取引所で自由に売買できない非上場株式は、株式譲渡制限の存在も相まって「売れないもの」と誤解されがちです。しかし実際には、非上場株式の少数株主であっても正しい手順を踏めば第三者への売却や譲渡は十分に実現できます。
このページでは、株式譲渡制限の有無を確認する方法、非上場株式の譲渡のステップ、適正株価の設定手法、みなし配当や譲渡所得課税を抑えるポイントまで、非上場株式トラブルの経験が豊富な弁護士の視点からわかりやすく解説します。
非上場株式は売却・譲渡できるのか?少数株主でも現金化できる理由
非上場株式は市場での売買ができず流動性が低いものの、正しい手続きと買い手探しのコツさえ押さえれば、非上場株式の少数株主でも売却ができます。まずは「売れない」という思い込みが生まれる背景と、実際に売却を実施するための具体策を解説します。
非上場株式と上場株式の違いとは?
非上場株式とは、東京証券取引所などの証券取引所に上場していない企業の株式を指します。日本企業の約99.9%が非上場企業であり、国内約358万社のうち上場企業は約4,000社にすぎません。言い換えれば、株式の大半は非上場株式なのです。
上場株式は証券会社を通じてリアルタイムに売買できますが、非上場株式には市場価格が存在しません。そのため、株主と買い手が直接条件を交渉して取引を成立させる「相対取引」が基本となります。
非上場株式の主な特徴は次のとおりです。
・株価の変動幅が小さい
市場の需給ではなく企業価値の推移に合わせて緩やかに変動します。
・情報が限定的
上場企業のような開示義務がなく、価値判断に必要な情報が少ない傾向にあります。
・長期保有が前提
短期売買が難しく、保有期間が長期化しやすい点が特徴です。
| 項目 | 上場株式 | 非上場株式 |
| 取引の場 | 証券取引所 | 当事者間の相対取引 |
| 価格決定 | 市場の需給で決定 | 交渉により決定 |
| 流動性 | 高い(即日売買可能) | 低い(買い手探しが必要) |
| 株式譲渡制限 | 原則なし | 定款で制限されることが多い |
| 情報開示 | 義務あり | 義務は限定的 |
| 株主権行使 | 容易 | 発言力が弱い場合も |
| 価格の透明性 | リアルタイムで公開 | 評価方法で大きく変動 |
「非上場株式だから売れない」のではなく、「売り方が違うだけ」という視点を持つことが重要です。
譲渡制限株式を譲渡(売却)できるパターン
多くの非上場企業では、第三者の経営参加を防ぐために株式譲渡制限を設けています。制限があるとはいえ、以下の3つの方法で売却や譲渡は可能です。
1.株式発行会社の承認を得て売却
株主総会や取締役会で承認を受ければ、希望する相手に株式を譲渡できます。株式譲渡承認を得るには譲渡先の信用力を示し、経営方針を尊重する姿勢を示すこともポイントの一つです。
2.会社または指定買取人に売却
株式発行会社が第三者への株式譲渡を認めない場合でも、会社自身または 株式発行会社が指定した買取人が株式を買い取る制度があります。価格に合意できないときは裁判所へ株式売買価格決定を申し立てることも可能です。
3.相続による株式移転
相続は株式譲渡に該当しないため、株主が亡くなると株式譲渡承認なしで相続人に株式が移転します。相続が発生しても経営に関与しない相続人は、株式現金化を検討するケースが少なくありません。
なお、株式譲渡承認請求から2週間以内に会社が応答しない場合は、株式譲渡を承認したものとみなされ、自動的に手続きが進められます。
非上場株式・少数株式の譲渡(売却)で起こりやすいトラブル
非上場株式の譲渡では、以下のような予期せぬトラブルも発生します。
- 株式の譲渡や売却を会社に持ちかけても経営者が取り合わない
- 経営者が示す株式買取価格が相場より極端に低い
- 買い手が見つからず株式を手放せない
- 「譲渡制限があるから売却できない」と断られる
このような問題に直面した場合は、早めに専門家へ相談することがおすすめです。相談実績「300件以上」の弁護士法人M&A総合法律事務所にまずはご相談ください。
【少数株主向け】非上場株式の売却手続きと注意点
少数株主が非上場株式を売りたいと考えて、実際に売却するには、複雑そうに見える手続きを順番にこなすことが重要です。
ここでは実際に非上場株式の売却を実現する際の具体的な流れと、途中でつまずかないためのポイントを解説します。事前準備と専門家の伴走があれば、「非上場株式は売れない」と諦めていた非上場株式でも現金化の道が開けます。
| ステップ | 手続き内容 | ポイント・注意点 |
|---|---|---|
| 1 | 株式譲渡制限の有無を確認 | 定款・株主名簿を確認し、承認機関(取締役会/株主総会)を把握 |
| 2 | 株主総会または取締役会で承認を取得 | 承認請求後2週間以内に回答、無回答は承認みなし。不承認時は指定買取人・裁判所申立てへ |
| 3 | 売却先を探す | 発行会社・経営者・主要株主・外部投資家など候補を比較。売却先によって税負担が異なる |
| 4 | 株価評価と価格交渉 | 類似業種比準方式・純資産価額方式・DCF法などを併用し客観的な根拠を提示 |
| 5 | 株式譲渡契約書を締結 | 譲渡株数・価格・表明保証・紛争解決条項を明記。専門家チェック推奨 |
| 6 | 売買代金の決済と株主名簿の名義書換 | 入金確認後に名義変更。株券発行会社は裏書・交付、非発行会社は名義書換請求が対抗要件 |
| 7 | 税務申告と納税手続き | 譲渡所得として20.315%課税。発行会社への売却はみなし配当課税の可能性あり。 |
1.株式譲渡制限の有無を確認する
まずは、自分が持つ株式に譲渡制限が付いているかを必ずチェックしましょう。非上場企業の多くは、経営権を守るために株主総会または取締役会の承認を必要とする「譲渡制限株式」を発行しています。譲渡制限の有無は会社の定款に明記されているため、定款を入手して確認することが第一歩となります。
定款・株主名簿のチェックポイント
株式譲渡制限の有無の確認には、以下のような内容を確認をしましょう。
定款
- 株式譲渡制限の条文(「株式の譲渡制限」など)
- 承認を行う機関(株主総会か取締役会か)
- 特別な承認手続きの有無や種類株式の発行状
株主であれば会社法第31条に基づき、閲覧・謄写を請求できます。
株主名簿
- 自分の保有株式数と種類
- 発行済株式総数に対する持株比率
- 他の主要株主の構成や支配株主の存在
- 株券発行の有無
株主および債権者は会社法125条2項により、営業時間中いつでも閲覧・謄写を請求できます。
2.株主総会または取締役会で株式譲渡承認を取得する
譲渡制限株式を譲渡や売却するには、会社からの承認プロセスが必要です。承認機関は定款の定めによって異なり、取締役会設置会社では取締役会、そうでなければ株主総会が担当します。株式譲渡承認プロセスは次の流れで進めます。
1.事前対応
経営陣や主要株主に株式売却の意向を伝え、株式売却の理由や想定する買い手のメリットを説明しておくと、正式手続き後の株式譲渡承認が得やすくなります。
2.株式譲渡承認請求書の提出
書面で株式譲渡承認請求書を作成し、配達証明付き郵便など記録に残る方法で会社へ送付します。
3.会社による審査と回答
会社は株式譲渡承認請求の受領後2週間以内に承認か不承認かを決定し通知する義務があります。期限内に通知がない場合、自動的に株式譲渡は承認されたとみなされます(会社法145条)。
4.指定買取人が提示された場合の対応
株式譲渡が不承認となったときは、会社自身または会社が指名する第三者(指定買取人)が株式を買い取ります。提示された株式価格に納得できなければ、裁判所へ株式売買価格決定の申立てが可能です。
専門家の助言を受けながらこれらの手続きを進めることで、非上場株式の少数株主でも円滑に株式を売却できる可能性が高まります。
3.非上場株式の売却先を探す
株式譲渡の承認を得たら、次は譲渡対象の株式を購入してくれる相手を見つける段階です。取引市場が存在しない非上場株式では買い手探しがハードルになりやすいため、自社関係者から外部投資家まで幅広く候補をリストアップし、優先順位を付けてアプローチしていくことが重要です。代表的な買い手は次の4パターンに大別できます。
- 株式の発行会社(自己株式取得)
- 株式発行会社の経営者
- 株式の発行会社の主要株主
- 外部の法人・個人投資家
発行会社への売却と第三者への株式売却の違い
税負担や交渉期間に大きな差が生じるため、株式の売却先の選定は慎重に行いましょう。特に税務面では「みなし配当」の有無で納税額が大きく変わります。
| 比較項目 | 発行会社へ売却(自己株式取得) | 外部または主要株主へ売却 |
| 手続きのしやすさ | 会社が協力的なら比較的スムーズ | 新規株主の場合は手続きが増える |
| 価格交渉の幅 | 会社基準の提示額が中心 | 相手の投資目的によって柔軟 |
| 税金 | みなし配当課税で最大55% | 譲渡所得課税で約20.315% |
| 売却までの期間 | 会社の意思決定に左右される | 買い手探しで長期化することも |
| 成立の可能性 | 会社の資金余力と意向次第 | 買い手のニーズ次第 |
4.株価評価と価格交渉
非上場株式は市場価格がないため、適正株価をどう算出するかが交渉では重要になります。少数株主の場合でも複数の評価手法を併用し、客観的な根拠を示すことで買い手からの大幅な値引きを防げます。
代表的な評価方法は次のとおりです。
- 類似業種比準方式:同業種の上場企業指標を参照
- 純資産価額方式:貸借対照表の純資産を基礎に算出
- DCF法:将来キャッシュフローを割り引いて現在価値を算定
- 配当還元方式:過去の配当実績から利回り換算
算出結果を持って交渉にする際は、相手の投資目的やシナジーを汲み取り、「企業の成長性」「事業の独自性」などプラス要素も具体的に提示しましょう。評価計算は専門知識が必要なため、株価算出に詳しい専門家にバリュエーションを依頼すると交渉材料として説得力が上がります。
5.株式譲渡契約書を締結する
売却先と価格が確定したら、最終的に法的拘束力を持つ株式譲渡契約書を取り交わします。後日のトラブルを避けるため、条項の抜け漏れがないよう専門家のチェックを受けることを推奨します。契約書には少なくとも以下を盛り込みましょう。
- 譲渡株式の詳細(種類・株数)
- 譲渡価額と支払条件
- 株式の引渡日(効力発生日)
- 表明保証条項(株式の真実性、権利帰属、担保不設定など)
- 秘密保持条項
- 補償条項(表明保証違反時の損害賠償範囲)
- 紛争解決条項(専属管轄裁判所・仲裁など)
- 準拠法
これらを明文化しておくことで、株式の売却後に隠れ債務や未払い税金が発覚した場合の責任分担を明確にできます。弁護士と連携しながら契約書を作成・締結し、安全に契約の締結を進めましょう。
6.売買代金の決済と株主名簿の名義書換
株式譲渡契約を締結したら、実際に代金を受け取り、株主名簿の名義を書き換える手続きを完了させる必要があります。株主の名義書換が終わらなければ、買主は配当受取や議決権行使など株主としての権利を行使できません。株主の名義書換には通常、次の書類が求められます。
- 株主名簿書換請求書
- 株券(株券発行会社の場合)
株券を発行している会社では、裏書譲渡または株券の交付が対抗要件になります。一方、株券不発行会社では株主名簿の名義書換が対抗要件となるため、株主名簿書換請求が済めば権利移転が確定します。決済方法は銀行振込が一般的ですが、取引金額が大きい場合や双方の信頼関係が十分でない場合は、第三者が資金を一時的に預かるエスクロー口座の利用を検討すると安全です。
株主名義書換が完了した時点で株式譲渡手続きは実質的にクローズとなり、買主は正式に新株主として登録されます。書類提出の不備や入金遅延があると手続きが止まるため、早めに必要書類をそろえ、決済スケジュールを明確にしておきましょう。
7.税務申告と納税手続き
非上場株式を売却して得た利益は譲渡所得として扱われ、原則として20.315%(所得税・復興特別所得税15.315%+住民税5%)が課税されます。ただし、発行会社に売却した場合は「みなし配当」とみなされる部分が生じ、最高55%(所得税45%+住民税10%)の税率が適用される可能性がある点に注意してください。
非上場株式の株価評価と適正価格を決める方法
非上場株式には市場価格がないため、どの評価手法を採用するかで株式価値が大きく変わります。とくに株式の売買交渉では「会社法上の時価」と「税法上の評価額(国税庁方式・相続税評価額)」が混同されがちですが、実務で重視されるのはあくまでも取引当事者が合意できる“経済的価値”です。
ここでは代表的な3手法を取り上げ、それぞれの特徴と使い分けのポイントを解説します。
| 評価手法 | 算定の考え方 | 適している会社・ケース | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|---|
| 類似業種比準方式 | 上場している同業種の株価指標(配当・利益・純資産)を基準に算定。 税務評価でも利用される。 | 中堅~大企業/業績・配当が安定している会社 | 客観的なデータを使える/相続税評価でも使われる | 業績不振の企業だと割高に出やすい/業績好調でも割安に出やすい |
| 純資産価額方式 | 貸借対照表の純資産(資産-負債)を基に1株あたり価額を算出。 | 赤字企業/小規模企業/清算価値を重視したい場合 | 計算がシンプル/財務諸表から算出できる | 将来の利益・成長性を反映できない/含み損益で評価が歪むことがある |
| DCF法(ディスカウント・キャッシュフロー) | 将来のキャッシュフローを割引率で現在価値に換算して算定。 | 成長企業/スタートアップ/M&A投資案件 | 将来性を反映できる/投資判断に近い理論的評価 | 予測や割引率の設定次第で結果が大きく変わる/算定に専門知識が必要 |
類似業種比準方式
類似業種比準方式は、評価対象会社と事業内容や規模が近い上場企業の株価指標(配当・利益・純資産)をベースに算出する方法です。相続税の計算によく採用され、大企業や中堅企業の評価で活躍します。算定式の一例は次のとおりです。
類似業種比準価額 = 類似業種株価 × { (配当金額比 + 利益金額比 + 純資産価額比) ÷ 3 } × 0.7
配当や利益が安定している企業だと、純資産価額方式より評価が低く出る傾向があります。逆に業績が振るわない場合は割高になることもあるため、他の手法と併用してバランスを見るのが安全です。
純資産価額方式
純資産価額方式は貸借対照表の純資産(総資産−負債)をベースに1株当たり価額を計算する、いわば“解散価値”に近いアプローチです。赤字企業や小規模企業でも適用でき、計算がシンプルなのが強みですが、成長性や将来利益を加味しないため、含み損があると実態より高く、含み益が大きいと逆に高評価となりがちな方法です。
DCF法(インカム・アプローチ)
DCF(Discounted Cash Flow)法は、将来創出されるであろうキャッシュフローを割引率で現在価値に置き換え、企業価値を算定する手法です。M&Aやベンチャー投資で標準採用され、成長企業や事業ポテンシャルが高いスタートアップの評価に適しています。
基本手順
- 事業計画に基づく将来キャッシュフロー予測
- 資本コスト(割引率)の設定
- 終末価値(継続価値)の計算
- ①と③を現在価値に割り引き、企業価値を算出
メリット:将来の収益性・成長性を反映でき理論的裏付けが強い
デメリット:予測値や割引率の設定次第で結果が大きく変わる
赤字スタートアップでも将来キャッシュフローが見込める場合は高い評価額が提示されることがあり、実際の売買交渉ではDCF法が決定打となるケースも珍しくありません。
複数の手法を並行して試算し、最も合理的かつ当事者が納得できる価格帯を探るのが、非上場株式取引の基本姿勢です。株式の評価結果には前提条件や試算根拠を添え、買い手・売り手双方の理解を得ながら交渉を進めましょう。
非上場株式の売却時の税制とみなし配当
非上場株式を売却するときは、譲渡所得の計算だけでなく「みなし配当」の有無によって税負担が大きく変わります。とくに発行会社へ株式を譲渡するケースでは、想定以上の課税額になることが少なくありません。ここでは個人株主が押さえておくべき基本ルールと、課税額を左右するポイントを詳しく解説します。
個人が売却した場合の譲渡所得税
個人が非上場株式を第三者へ売却すると、その利益は一律 20.315%(所得税・復興特別所得税 15.315%+住民税 5%)で課税される「譲渡所得」に区分されます。
譲渡所得 = 譲渡価額 -(取得費 + 譲渡費用)
- 取得費は購入代金や出資額など株式取得に要した実費を指し、相続・贈与で取得した場合は被相続人または贈与者の取得価額を引き継ぎます。
- 取得費が不明なときは、譲渡価額の5%を「概算取得費」として差し引くことも可能です(所得税法施行令113条)。
- 譲渡費用には仲介手数料・契約書の印紙税・専門家報酬・株主名簿書換手数料などが含まれます。
確定申告と損益通算
非上場株式は特定口座で管理できないため、毎年の確定申告(2月16日〜3月15日)が必須です。
- 非上場株式の損益は「一般株式等に係る譲渡所得等」としてまとめられ、上場株式の損益とは原則通算できません。
- 同じ区分(一般株式等)の中であれば、他の非上場株式の譲渡益・損失と相殺することが可能です。
- 控除しきれなかった損失は、確定申告を行えば翌年以降3年間繰り越せます。
イメージ
非上場A社株式:譲渡益 500万円
非上場B社株式:譲渡損失 300万円
上場C社株式 :譲渡益 400万円
A社とB社の損益を相殺すると「一般株式等の譲渡所得」は200万円、上場C社の益400万円は別区分となり通算できません。結果、税額は約121.9万円(200万円×20.315%+400万円×20.315%)。
法人と個人の組み合わせ別・課税区分
非上場株式の売却では、売り手と買い手が「個人か法人か」によって課税の仕組みが大きく変わります。代表的な4パターンを把握しておくと、想定外の税負担を避けやすくなります。
個人 から 個人 への株式譲渡
売り手:譲渡所得(申告分離課税 20.315%)
買い手:課税関係なし
時価とかけ離れた低額で売却すると、差額が贈与とみなされ贈与税がかかる恐れがあります。
個人 から 法人(発行会社以外)への株式譲渡
売り手:譲渡所得(20.315%)
買い手:原則課税なし
法人が時価より大幅に高い価格で取得すると、その差額は「寄附金」として扱われ、損金算入に制限がかかる場合があります。
法人 から 個人 への株式譲渡
売り手:法人税の課税対象(譲渡益は益金算入)
買い手:課税関係なし
時価を大きく下回る価格で譲渡した場合、個人側でみなし贈与となり贈与税が発生する可能性があります。
個人 から 発行会社 への株式譲渡(自己株式取得)
売り手:譲渡所得(20.315%)+みなし配当(最大55%)
買い手:課税関係なし
譲渡対価は「みなし配当」と「譲渡収入」に区分され、みなし配当部分は配当所得として総合課税の対象になります。結果として最高税率が適用される場合があるため、特に注意が必要です。
適正時価を外れた取引のリスク
低額譲渡
個人間・個人→法人:差額が贈与税の対象
法人→個人:個人側で贈与税、法人側で寄附金課税の可能性
高額譲渡
個人→法人:差額が役員賞与等として課税される場合あり
法人→個人:差額が配当や給与と見なされ課税される場合あり
株式の取引価格が時価と著しく乖離すると、思わぬ形で課税される危険性があります。売買前に客観的な株価評価を行い、適正な株価で契約を結ぶことがトラブル防止の観点で必要となります。
みなし配当課税の基礎知識
発行会社が自社株を買い戻す「自己株式取得」では、受け取る代金の一部がみなし配当として扱われ、通常の株式譲渡所得より高い税率で課税されることがあります。仕組みを理解しないまま取引すると、税負担が想定より大きく膨らむ恐れがあるため、事前に計算ロジックと回避策を押さえておきましょう。
非上場株式売却時のみなし配当の計算方法
税法上のみなし配当額は次の式で求められます。
みなし配当額 = 受取金額 - その株式に対応する資本金等の額
ここで「その株式に対応する資本金等の額」は、以下のように算定します。
資本金等の額 ×(売却株式数 ÷ 発行済株式総数)
計算例
- 株式売却価額:1億円
- 発行済株式総数:1,000株
- 売却株式数:100株(10%)
- 資本金等の額:2,000万円
対応資本金等 = 2,000万円 × (100 ÷ 1,000) = 200万円
みなし配当額 = 1億円 - 200万円 = 9,800万円
この9,800万円が配当所得として総合課税(最高55%)の対象となり、残り200万円が譲渡所得として20.315%課税されます。
みなし配当課税を抑える3つのアプローチ
1.第三者への株式売却を検討する
発行会社ではなく外部の法人・個人に譲渡すれば、課税は20.315%の譲渡所得のみで済み、みなし配当は発生しません。
2.相続の特例の活用
相続または遺贈で取得した株式を、相続開始から3年以内に発行会社へ売却する場合は「みなし配当課税の特例」を適用できる可能性があります。条件を満たせば譲渡所得課税へ置き換えられ、負担が軽減されます。
3.段階的な株式売却で累進税率を回避
大口株式を一度に現金化すると総合課税部分が大きくなりがちです。数年に分けて売却すれば各年の課税所得が抑えられ、累進税率の影響を緩和できます。
みなし配当は計算方法を誤ると数千万円単位の追加納税につながることもあります。株式の売却先やタイミング、適用特例の有無によって税額が大きく変動するため、自己株式取得を検討する際は税理士など専門家に試算を依頼し、最適なスキームを選択しましょう。
税務申告時の注意点
非上場株式を売却したあとは、確定申告まで気を抜けません。取得費や譲渡費用を適切に計上し、期限内に正しい書類を提出することで、余計な追徴課税やトラブルを防げます。
取得費の立証は必須
譲渡所得の計算では取得費の裏付けが重要です。購入代金の領収書、出資払込証明書、契約書の原本などは原則として捨てずに保管しましょう。相続・贈与で取得した場合は、被相続人や贈与者側での取得時資料も必要になります。どうしても取得費が分からないときは、譲渡価額の5%を「概算取得費」として差し引けますが、実額より少なくなる可能性が高いため、できる限り実費を証明できる書類を探すことが得策です。
譲渡費用は漏れなく控除
譲渡所得からは取得費だけでなく、株式売却に直接要したコストも控除できます。たとえば仲介手数料、契約書の印紙税、必要に応じた登記費用、株価算定の鑑定料、弁護士や税理士への報酬などが対象です。領収書や請求書を用意して金額を証明できるようにしておきましょう。
確定申告の手続き
非上場株式の譲渡は特定口座の源泉徴収制度が使えないため、原則として翌年2月16日から3月15日までに確定申告を行います。確定申告書Bのほか、第三表(分離課税用)と「一般株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」を添付するのが基本です。みなし配当が生じた場合は配当所得としても計上し、総合課税で他の所得と合算して税額を計算します。
源泉徴収された税額の取り扱い
発行会社に売却してみなし配当が発生すると、支払時に20.42%の源泉所得税が差し引かれるのが一般的です。この金額は確定申告で精算し、最終的な税額から控除できます。総合課税の結果として税率が20.42%を超えれば、差額を追加で納付する必要があります。
相続税との二重課税調整
相続で取得した株式を売却した場合、相続税と所得税の二重課税を調整する制度があります。相続開始から3年10か月以内に株式を売却し譲渡益が出たときは、一定の計算式により譲渡所得税から控除を受けられる可能性があるので、該当する場合は忘れずに適用しましょう。
適切な税務申告を行うためには、専門的な知識が必要です。特に複雑なケースでは、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。
※本ページに掲載している情報は一般的な内容を示すものであり、税務に関する専門的なアドバイスを提供するものではありません。税金に関する詳細なご相談や正確な判断が必要な場合は、必ず税理士などの専門家にご相談ください。
非上場株式の譲渡(売却)事例
非上場株式・少数株式の売却では、価格や手続、会社との関係性をめぐる紛争が生じやすく、適切な法的対応が不可欠です。
事例1|外部招聘の社長が創業者の私情で解任されたケース
後継者不在により外部から招聘された社長(依頼者)が、経営方針に関する意見表明を理由に突然解任。退職慰労金は支払われず、依頼者の適正価格での株式買取要請も拒否され、著しく低廉な価格のみ提示されました。法的措置の結果、裁判所の和解勧告により、退職慰労金の全額支払いと株式譲渡代金の支払いを獲得しました。
事例2|長男が次男を経営から排除し利益を独占しようとしたケース
創業家の次男である依頼者は、長男と共同で経営に携わっていましたが、長男が過半数の株式を背景に専横を強化。依頼者は役員の地位・収入を失い、自宅からの退去も迫られる事態に。さらに、保有株式の不当な低額買い取りを迫られました。依頼者は弁護士に依頼し、適正価格での買い取りを主張。長男の公私混同行為も指摘しつつ交渉を重ね、適正価格での買い取りを実現しました。
事例3|会社支配をめぐり本家が分家を排除したケース
依頼者は創業家「分家」出身の元取締役で、20%を保有。退社後、会社から株式の買い取りと配当の双方を拒否されました。会社を掌握した「本家」出身の社長は身内を優遇し、分家系の人材は排除。依頼者も会社から締め出されました。依頼者は適切な買い取りと、社長の公私混同による不正を追及。訴訟と交渉を並行し、おおむね時価相当額での株式買い取りに至りました。
※個人の特定を避けるため、当事者や経緯は一部デフォルメしています。実際の結果は事案の事情により異なります。
FAQ
非上場株式・少数株式は売れないのですか?
証券取引所で自由に売買できないだけで、非上場株式や少数株式でも売却自体は十分に可能です。譲渡制限の有無を確認し、買い手候補を探し、会社の承認を得る。このような正しい手順を踏むことで現金化への道が開けます。流動性が低いぶん時間や労力は掛かりますが、適切なアプローチと専門家の支援があれば取引は成立します。
非上場株式・少数株式を売却(譲渡)するときの注意点は?
最大の注意点は、市場がないため株主自身が買い手を見つける必要があることです。さらに定款で株式譲渡制限が設けられている場合は、取締役会や株主総会の承認を得なければ売却できません。持株比率が小さい少数株主は交渉力が弱くなりがちなので、複数の株価評価を用意して価格交渉の根拠を示すとともに、想定される税務リスクを把握しておくことが大切です。
相続した非上場株式・少数株式を売却するには?
まずは遺産分割協議や名義変更、相続税申告など相続そのものの手続きを完了させる必要があります。相続自体は譲渡制限の対象外ですが、相続後に第三者へ売却する場合は通常どおり会社の承認が求められます。また、相続開始から3年以内に発行会社へ売却する場合に適用できる「みなし配当課税の特例」を利用すれば、高率課税を避けられる可能性があります。相続時点の株価は将来の譲渡所得計算に影響するため、評価方法と金額を必ず記録しておきましょう。
非上場株式を相続する際の注意点はありますか?
非上場株式を相続する際にはメリットがある一方で以下のような注意点もあります。
- 相続税の評価が複雑で納税資金が不足しやすい
- 譲渡制限があり非上場株式の売却ハードルが高い
- 少数株主になると情報が乏しく影響力も小さい
- 株主名簿の名義書換をしないと権利行使や売却が滞る
- 会社や定款のルールで相続後の選択肢が左右される
非上場株式・少数株式の譲渡は専門家への相談が必要ですか?
価格評価、契約書作成、会社との交渉、税務申告まで一連の手続きが複雑なうえ、譲渡制限やみなし配当など専門知識を要する論点も多いため、早い段階で弁護士や税理士に相談することを強くおすすめします。経営者が交渉に応じない、提示価格が相場とかけ離れている、買い手が見つからない。こうした事態に直面してからでは対応が後手に回りがちです。専門家にサポートを依頼することで、適正価格の提示やスムーズな手続きを実現し、トラブルを未然に防ぐことができます。
非上場株式・少数株式が売れないとお悩みならご相談ください
非上場株式・少数株式の売却は、適切な手続きを踏むことで実現可能です。専門家のアドバイスを受けながら、適切な手続きを踏んで非上場株式・少数株式の売却を進めてください。複雑に見える手続きも、一つずつクリアしていくことで、非上場株式を売却できるはずです。
お困りのことがあれば、相談実績300件以上の弁護士法人M&A総合法律事務所にまずはご相談ください。
※本ページは一般的な情報提供を目的としており、個別具体的なケースについては、必ず専門家にご相談ください。
※税金に関する詳細なご相談や正確な判断が必要な場合は、必ず税理士などの専門家にご相談ください。



