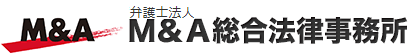M&Aの相場は、どうなっているのでしょうか。
M&Aを行う場合に、M&Aの対象となるのは事業や株式です。
上場株式には時価が付きますが、そうではない普通の事業や株式には時価が存在していません。
また、M&A価格は、さまざまな企業価値評価の結果を踏まえて、協議・交渉の結果、決定されますので、M&Aの相場を把握するためには企業価値評価を行うべきということとなります。
そのため、企業価値評価(事業価値評価・株式価値評価)をしてM&A価格について交渉・決定してゆくこととなります。
ですので、M&A価格の相場を把握するためには企業価値評価を行うべきなのです。
この点、企業価値評価に基づくM&A価格はあくまでも想定であり、実際の交渉では理屈通りに決定されるものではなく、実際の交渉の結果、大きく異なることも多くあります。
ただ、実際の交渉の結果、個別の案件では、M&A価格が企業価値評価から大きく異なることがあっても、当事者は企業価値評価を意識してM&A価格を交渉し決定していることに相違ありませんので、総体としてのM&Aの相場は、やはり企業価値評価を反映したものとなっているものと思われます。ここからもやはりM&A価格の相場を把握するためには企業価値評価を行うべきなのです。
では、M&Aではどのように企業価値評価を行うべきでしょうか。
また、その結果、M&Aの相場は、どうなっているのでしょうか。また、M&Aの相場より高い価格でM&Aを実現するためにはどうすればよいのでしょうか。
M&Aの相場はあるのか?
M&Aにおいて売り手会社と買い手会社は相反する状況下にあります。売り手会社は譲渡価格を少しでも高くすることを目的にしており、また買い手会社は買収価格を抑えたいと考えています。双方の思惑が異なることから、M&Aの相場を把握しておくことが重要となります。
売り手会社の考えるM&Aの相場
売り手会社としては、M&Aの相場を高めに見る傾向があります。その理由としては以下のようなことが考えられます。
- 自社の技術をもってすれば、本来ならば売り上げ、利益も向上するはず
- 今までの苦労があって今の会社があるのだから、企業価値は高い
- M&Aで受け取りたい金額は○円ほどという希望
- 同業他社が〇円でM&Aをしたのであれば、自社はより高額になるという考え
このような考え方から、売り手会社はM&A価格の相場を高く見る場合が多くなっています。
買い手会社の考えるM&Aの相場
売り手会社とは反対に、買い手会社はM&Aの相場を安く見る傾向にあります。投資に対するリターンやリスクを考えると、少しでも安い価格でM&Aをしたいという気持ちの表れといえます。
- M&Aで支払う価格を抑えたいという意向
- M&Aが採算に合っているかという考慮
- M&Aする場合と自社で同事業を立ち上げる場合とどちらが有利なのかとの比較対象
- M&Aをしても売り手会社にシナジー効果が生じないかもしれないという心配
- M&Aによるオーナー交代で業績不振が起こるかもしれないという懸念
買い手会社としてはさまざまなリスクを回避したい考えから、M&Aの相場を安く見る傾向にあります。
これらのことから、M&Aの相場を知っておくことが重要となります。M&Aの相場をベースに話し合うことができれば、売り手会社は安い価格でM&Aをするリスクを減らすことができ、反対に、買い手会社はM&Aの相場よりも高い価格でM&Aをするリスクを減らすことが可能となります。
M&Aの相場の決まり方について
M&Aの相場を知るためには、M&A価格がどのように決定されるかを知る必要があります。
M&A価値を決めるためには、いくつかの要素を考慮する必要があります。M&A相場を知るために、まずはM&A価値を決定するうえで考慮されるこれらの要素についてご紹介します。
企業価値
企業価値評価は、企業そのものの価値を算定することです。
中小企業の場合には、後述するいくつかの企業価値評価算定方法のいずれかで企業価値の評価をすることになります。
純資産
純資産とは、貸借対照表の資産から負債を引いた金額のことをいいます。企業は有形無形の資産を保有していますが、同時に買掛金や借入金などの負債も保有しています。
通常、貸借対照表に記載されている資産には含み損益などがあり正確な価値を反映していない場合が多くなっています。
そのため企業価値評価では、簿価純資産よりも時価純資産を採用することが多くなっています。
将来の収益
企業価値評価において重要なのは、対象会社が将来どれくらいの収益を得ることができるかです。そのため、企業価値評価においては、将来の収益がどのように発生するかに基づいて企業価値を評価することとなります。
将来の収益は、対象会社の現在の価値と将来性を表すことができるため、企業価値評価方法としては優れています。しかしあくまでも将来の収益は予測であるため、企業価値評価の結果は評価した人によって異なります。
また将来の収益は、過去の実績を用いて将来の収益を予測するものであり、客観性に乏しいという側面もあります。
⇒将来の収益価値が売却額に影響を与えるアパレル会社のM&Aはこちら
市場価格
市場価格とは株式市場での株価のことをいいます。株式市場での価格は、長期的に見ると企業価値を適正に評価できていると考えられていますが、短期的にみると企業価値とは関係なく変動を繰り返すものといえるでしょう。
そのため、M&Aでは株価の騰落を排除して考える場合が多く、毎日の終値の平均を取り、企業価値評価を行うことが一般的です。
企業価値評価においては、対象会社と同様の業種で上場している企業の市場価格を参考にして、対象会社の企業価値評価を行います。
無形資産
将来収益に基づく企業価値と、純資産に基づく企業価値とは一致しません。将来収益に基づく企業価値の中には純資産に含まれない決算書に記載されない無形資産というものがあります。例えば、長年かけて構築した技術やノウハウは、特許の有無にかかわらず価値があります。
また売上や顧客の情報などのデータベース、ソフトウェア、コンテンツなどは収益を生み出す源泉ですが、決算書に記載されることはありません。その他、従業員の能力も同様です。
このような無形資産は、しばしば「のれん」「営業権」とも言われたりします。のれん(営業権)とは、純資産の価格を上回る価値のことを言います。決算書では「連結調整勘定」や「営業権」という勘定科目で記載されます。
基本的に、企業価値に含まれるが決算書に記載されていない無形資産の場合や、企業価値を上回る価格でM&Aをした際に発生する部分の場合があります。企業価値というのは将来生み出す収益を含んでいるため、現段階の純資産と一致するわけではありません。また企業価値には決算書上は評価されない無形資産も含まれています。
また、のれん(営業権)として、M&Aにおいて、対象会社に希少価値があるなどの理由で企業価値を上回る価格でM&Aをしてしまった場合などが挙げられるでしょう。つまり、M&Aの買収価格が高騰すれば、その分、のれん(営業権)も増えるということになります。
企業価値と同じ価格でM&Aできるということは少なく、実際にはズレが生じるものです。どのような企業価値評価の方法を選択するかによって、のれん(営業権)が発生する場合やのれん(営業権)が発生しない場合があります。
企業価値評価方法
M&A価格を決定する際に、企業価値評価を基準とすることが多いため、企業価値評価の方法を知っておく必要があります。
企業価値評価の方法としては、以下のような方法があります。
コストアプローチ(静態的評価方式)
会社が持っている資産や負債から企業価値評価する方法がコストアプローチです。貸借対照表(バランスシート)の純資産額を基準に算出する評価方法で、「純資産方式」と呼ばれてます。純資産は資産から負債を差し引いた価格のことです。
純資産方式の中でも「時価純資産法」「修正簿価純資産法」「簿価純資産法」が重要です。
簿価純資産法
まず簿価とは「帳簿価額」の略称で帳簿に記帳された資産・負債・資本の価格のことです。つまり、簿価純資産法は、決算書の貸借対照表の資産から負債を引いたもののことです。決算書を入手することができれば、M&Aの企業価値評価をシンプルな形で行うことができるでしょう。
簿価純資産法では、会社価値評価は行わず、貸借対照表の値をそのまま利用します。場合によっては、簿価と時価の差が大きいこともあるため、簿価純資産法では企業価値評価できないということも考えられます。
時価純資産法
時価純資産法では、貸借対照表の値を時価換算して企業価値評価を行うため、企業価値評価の正確性は高くなります。時価純資産法は、専門的な知識やさまざまなデータを必要とせず企業価値評価ができるため、中小企業のM&Aでは多く採用されている手法です。
デメリットとしては売り手会社の将来性が評価されておらず、過去の利益を基に企業価値評価します。また貸借対照表に含まれない資産も含まれません。
修正簿価純資産法
時価純資産法の値の中で簿価と時価の違いが大きい可能性が高いものには、有価証券、土地、建物などがあります。これらは含み損益が存在する可能性が高いのです。
修正簿価純資産法とは、このよう簿価と時価の違いが大きい可能性の高いものだけを時価修正を行う企業価値評価の方法をいいます。簿価と時価の違いが大きい可能性の高いものについて、時価評価を行うため、簿価純資産法よりも正確な企業価値評価を行うことができるのです。
年買法(時価純資産+営業権)
年買法とは、時価純資産に営業権(のれん)を加算して企業価値評価を行う方法です。営業権(のれん)は、純資産の価格を上回る価値であり、帳簿に記載のない企業の潜在価値のことです。企業は、帳簿に記載のない資産を有していることが多いものです。帳簿に記載がなくても将来的に収益を生み出す可能性が高いものを、現在の価値に換算して営業権(のれん)として評価するのです。
営業権(のれん)は、継続的に収益が見込まれる3年~5年について評価するもので、将来性が高ければ年数も長く評価されるものです。逆に将来性が低ければ年数も短く評価されるべきものです。
インカムアプローチ(動態的評価方法)
企業の将来性に着目して企業価値評価を行うのがインカムアプローチです。将来的な事業計画における収益に基づく企業価値評価を行うため、正確な企業価値評価となりやすいという特徴があります。
今後の成長性が見込まれる大手企業、ベンチャー企業などに使用されます。インカムアプローチには、「収益還元法」と「DCF(Discount Cash Flow)法」という方式があります。
それぞれの方法を詳しく説明していきましょう。
収益還元法とDCF(Discount Cash Flow)法
収益還元法とDCF(Discount Cash Flow)法は、企業の事業計画書の将来の収益に基づき企業価値評価を行う方法です。割引率を使用して、将来の収益を現在の収益に還元して企業価値評価を行う方法です。
収益還元法
収益還元法においては対象会社の過去の収益の水準が将来も継続するとみなして企業価値評価を行う点、DCF(Discount Cash Flow)法においては対象会社の将来の事業計画書を作成しその事業計画に基づく将来の収益を使用して企業価値評価を行う点、に違いがあります。
ただし、対象会社の過去の収益の水準が将来も継続するとみなすことについては、そのような保証はなく合理的ではありませんが、過去の収益の水準が将来も継続する可能性が低いわけではなく、特に、事業の安定した会社については、合理的な企業価値評価方法ということができます。
そこで、対象会社の過去の収益の水準が将来も継続するとみなすことが合理的ではないような場合に適用すべき企業価値評価方法が、DCF(Discount Cash Flow)法です。
DCF(Discount Cash Flow)法
DCFとは、Discounted Cash Flow(ディスカウンテッド・キャッシュ・フロー)の略称です。売り手会社にとって、M&Aは、対象会社からの将来の収益を放棄することになるため、売り手会社にとっては、DCF法を採用することに合理性があります。
買い手会社もまた将来の収益を得る権利を獲得する対価としてM&A価格を支払うことになるので、買い手会社にとっても、DCF法を採用することに合理性があるのです。
DCF法について、手順を追って説明していきましょう。
事業計画書の作成
将来の収益を基にして企業価値評価を行うため、まずは将来の収益を予想する事業計画書が必要となります。DCF法による企業価値評価のために、一般的には、5年分程度の将来の収益を予想した事業計画書を作成することが多くなっており、事業計画書の信憑性や精度の高さが企業価値評価に大きな影響を与えることとなります。
事業計画書としては市場動向や設備投資などさまざまな要素を盛り込んだ事業計画書を作成する必要があります。
そして、事業計画書を基に各年度のFCF(フリー・キャッシュフロー)を計算していきます。
FCFを算出する方法は
FCF=営業利益×(1-税率)+減価償却費-設備投資-運転資本
から求めることができます。
割引率の決定
その次は、FCFを割引いて、現在価値に変換するための割引率を算定しなければなりません。
DCF方式で採用される割引率は、「加重平均資本コスト」(WACC(Weighted Average Cost of Capital))を用います。
計算式
| WACC=資本コスト×((株主資本÷(株主資本+負債))+負債コスト×(1-実効税率)×((負債÷株主資本+負債)) |
DCF方式において割引率は非常に重要です。割引率が1%変わっただけでも企業価値に大きく影響し、最終的な結果が大きく変わってしまうこともあります。ただ、売り手会社が未上場の場合、正確な割引率を算出することは非常に困難です。
DCF法が採用できないケース
- 将来の収益がマイナスになっている場合には企業価値評価がマイナスになるため採用できない
- 事業を停止している場合、将来の収益が発生しないため採用できない
- 会社を清算することが決まっている場合、将来の収益が発生しないため採用できない
DCF法では、事業計画書においては、将来の収益を予測しており、事業計画作成者の主観が加味されることも多く、企業価値評価として客観性に乏しいというデメリットがあります。
DCF方式では、事業計画の実現可能性や割引率によって企業価値評価の結果が大きく異なります。事業計画や割引率の前提条件を検証しながら慎重に進めなければなりません。
- 配当還元方式
配当還元方式は、株主が将来受け取ることが期待される配当の価格に基づいて企業価値評価を行うものです。
少数株主や非同族株主などが保有する株式の価値評価のために使用する方法です。
株式の配当の価格を、割引率で還元し、株式価値評価を行う方法です。
配当還元方式は、「基本式」「国税庁方式」「ゴードンモデル方式」といったいくつかの配当還元方式が挙げられます。
- 基本式
将来に配当されると予想される配当金を、株主資本コストを割引率として使用し、現在価値に割引くことで企業価値評価を行うものです。
- 国税庁方式
国税庁方式とは、相続税や贈与税を算定するための財産評価基本通達に基づく株価算定方法であり、国税庁が使用する株価算定方法です。直前期2年間における年平均配当金の1株当たりの配当金について、10倍した金額を株価として算定するものです。
- ゴードンモデル法
基本式を発展させた方式で、投資利益率に基づき予想される利益と、社内に蓄積された内部留保を再投資することで得られると予想される利益に基づき、株価を算定する方法です。
株価=1株当たりの配当金÷(資本還元率-投資利益率×内部留保率)
配当還元方式では、配当が継続的に支払われることを前提として算定されるため、配当を出していない会社には適用することができません。
マーケットアプローチ(批准方式)
コストアプローチやインカムアプローチは事業自体の価値に着目し、企業価値評価を行うものです。それに対してマーケットアプローチは、対象会社と同業種の上場企業などの平均株価を基に企業価値評価を行う方法です。
マーケットアプローチには「類似企業比較法」「類似取引比較法」「類似業種比準法」「市場株価法」があり、比較対象が異なっています。
類似企業比較法(マルチプル法)
類似企業比較法(マルチプル法)とは、対象会社と事業が類似する上場企業の財務指標を基準にして、企業価値評価を行う方法です。対象会社と上場企業の特定の財務指標を比較した倍率を用いるためマルチプル(倍率)法とも呼ばれています。
基準とする指標は、売上高、営業利益、EBITDA(イービットディーエー)や純資産です。
対象会社と類似企業を比較してマルチプル(倍率)を計算し、対象会社の財務指標にマルチプル(倍率)を掛け算することにより企業価値評価を行うことが可能です。上場企業であれば財務情報を集め易いため、対象会社がどのような会社であっても、企業価値評価を簡単に行うことができます。類似企業を複数選択することにより、より正確に企業価値評価を行うことができます。
類似企業比較法にもいくつか企業価値評価手法が分かれていますので、以下詳述します。
- PBR法(株価純資産倍率法)
PBRとはPrice Book-value Ratioの略称で、株価純資産倍率のことです。
株価純資産倍率=株価時価総額÷簿価純資産額
株価純資産倍率は、上記の通り、株式時価総額を簿価純資産額で除した率で算出することができます。例えば、PBRが1.0を下回っていると、株式時価総額が簿価純資産額を下回っている状態といえ、株価が割安になっていと言えるでしょう。この状態は、企業を継続するよりも、解散する方が価値が高くなることを示しており、その会社は敵対的買収の対象になりやすいということができます。反対に、PBR が1.0より大きい場合は、純資産以外の価値であるのれんを市場が評価しているということとなります。
- PER法(株価収益率法)
PERとはPrice Earnings Ratioの略称で、「株価収益率」のことです。企業の収益力に対して株価がどれくらい割安又は割高なのかを測ることができます。
PER(株価収益率)=株価時価総額÷純利益
PER(株価収益率)=株価÷1株当たりの利益
PERは、上記のいずれかの計算式で計算されます。株価時価総額は株価×発行済み株式数で求めることとなり、1株当たりの利益は純利益÷発行済み株式数で求めることとなります。
PERで分かるのは、M&Aで買収した対象会社の収益から見て、M&A価格の元を取るためにはどのくらいの時間がかかるかという会社の収益力が分かります。日本の上場企業のPERの全業種平均は約15倍となっています。
PERが小さければ株価が割安、反対に大きければ株価が割高ということとなります。ただし、中小企業の未上場会社の場合は、株式に流動性がないため、PERがその分低くなることに注意が必要です。
PERは企業価値評価の方法として広く活用されていますが、将来の成長に対する期待であり、PERのみで企業価値評価するべきではありません。
- EBITDA法
EBITDA(イービットディーエー)は、税引前利益に、特別利益、支払利息、減価償却費を足して求める値のことをいい、対象会社のFCF(フリーキャッシュフロー)を生み出す力を評価する指標です。
EBITDA=税引前当期純利益+特別利益+支払利息+減価償却費
EBITDA法が広く採用されている理由は、FCF(フリーキャッシュフロー)という企業の収益を生み出す力を指標としており、会社ごとの会計的評価が影響を与えない指標を基準としているため、正確な企業価値評価が可能であるからです。
EBITDAを基準とすることで国や企業ごとの会計基準や税制の差に影響されずに企業価値評価を行うことができるのです。ただ、注意しなければならないのは、設備投資や運転資本など企業ごとの投資の差についても考慮していない点です。
類似取引比較法
類似取引比較法とは、対象会社に類似する会社のM&A事例を基準にしてマルチプル(倍率)を算出し。企業価値評価を行う方法です。業界によっては多数のM&A実績があるため、その事例の取引価格に基づき企業価値評価を行うのです。
類似取引として、通常、3社から10社ほどを参考にして企業価値評価を行います。
類似業種比準法
類似業種比準法とは、財産評価基本通達に基づき相続税や贈与税を算出するために国税庁が使用する株価算定方法であり、取引相場のない株式の株価を算定する場合に使用されます。相続や贈与などによって株式を取得する際に株価の操作が行われ租税負担に不公平が発生しないように評価を行うものであり、企業価値評価というよりは、租税負担の公平性や客観性に重点が置かれています。国税庁が指定する各種データを基に株価算定をする方法であり、正確な企業価値評価を目指したものではありませんので、M&Aで使用されることは少なくなっています。
国税庁:令和3年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目的別株価等について(法令解釈通達)参照
市場株価法
市場株価法とは、対象会社の株式市場における市場価格を基準に企業価値評価を行う方法です。上場企業の企業価値評価にしか使用できません。一定の期間における平均株価を算出し、企業価値評価を行います。株式市場における市場価格を基準としているため、客観性が高い企業価値評価方法です。
実際のM&A価格の決定方法
実際のM&A価格は、企業価値評価の価格を基準として、その他の要素や売り手、買い手の状況によって決定します。
M&A価格は次のような要素が影響して実際の価格が決定されることになります。
年買法(中小企業のM&Aの企業価値評価で使用される年買法)
中小企業のM&Aで広く使用されている「年買法」という企業価値評価方法があります。
年買法は中小企業の実務で多く使用されている方法であり、対象会社の時価純資産に、営業権として通常1~5年分の収益を加算して企業価値評価をします。
この営業権は、M&A後に予想される営業利益のことであり、対象会社の収益が将来継続すると見込まれる年数分の収益を基に算出します。
年買法の計算に使用される計算式は、
株式価値=時価純資産+修正営業利益×3年分(営業利益)
が一般的でした。しかし、営業利益が将来継続すると見込まれる年数は、一般的に3年といわれているだけで正確な裏付けに基づいているものではありません。そのため、4年分や5年分を加算した場合もあります。
なお、この時価純資産とは、貸借対照表の純資産を時価に直し必要な引当金を考慮した実態純資産額のことです。
また、修正営業利益とは、損益計算書から役員報酬や節税のための費用を適正額に修正した営業利益のことです。
年買法で使用されている営業利益は、過去の数字であり、将来の利益ではないため、適正な企業価値を評価できていません。また、この営業利益は、将来的に継続する保証はどこにもありません。また営業権を計算するための営業利益が継続する年数についても理論的な裏付けがありません。
現在では、年買法は、営業権を加味できる点や簡便な方法であることから、企業価値評価の方法というよりは、M&A価格の参考基準として採用されることが多いようです。
当事者の主観
M&Aの相場は決まっているものではなく、当事者の対象会社の純資産や将来の収益に対する主観が大きく影響しますので、売り手会社と買い手会社の主観がどの程度重なっていて両社の妥協の範囲がどの程度あるかによって決定します。
例えば、企業価値が5億円だった場合に、売り手会社は6億円以上のM&A価格を希望していたとします。
買い手会社は7億円までであれば、M&Aを実行するという意思であった場合、M&A価格は6億円~7億円の間で交渉が行われることになるでしょう。
すなわち、企業価値が5億円であっても、売り手会社と買い手会社が合意・妥協できる範囲内でM&A価格が決定するのです。
その他、買い手会社は、M&A価格の上限として、企業価値以外にも、M&Aにかかった費用の回収期間なども考えますので、これらもM&A価格の決定の要因となっています。
希少価値の存在
対象会社が特殊な技術や特許、立地、ブランドなどを持っている場合には、企業価値評価に影響を与えます。
そこでさらに重要なのは、買い手会社がその特殊な技術や特許をどれくらい手に入れたいと思っているかによってM&A価格はかなり影響が出ます。
つまりM&Aが買い手会社の収益にどれくらい貢献するかということに言い換えられます。特殊な技術や特許、立地、ブランドなどを持っている場合には、買い手会社は、対象会社が赤字であっても高いM&A価値を提示することがあります。
すなわち、売り手会社としては、特殊な技術や特許、立地、ブランドなどについては、高い評価を期待することとなりますが、買い手会社がどのように評価するかは不明であり、買い手会社の収益にどの程度貢献するかに依るということとなります。
繰越余剰金の評価
また決算書の繰越余剰金が評価されることもあります。繰越余剰金は過去の利益であり、会社の純資産でもありますが、収益を見ることもできます。決算書において、繰越余剰金によって会社の継続性が評価されることもあります。
取引先や顧客リスト
企業には多くの取引先や顧客があり、M&A後に買い手会社が対象会社の取引先や顧客をそのまま引き継ぐことができるかは重要です。買い手会社がM&A後に取引先や顧客を引き継ぐことができれば、事業の安定に加えて新たに新規取引先や顧客を開拓することができます。
また、買い手会社は、取引先や顧客を引き継ぐことで、新しいビジネスチャンスを得るきっかけになります。買い手会社が取引先や顧客を引き継ぐことができるかどうかは、M&A価格の相場に影響を与える要素となります。
⇒顧客リストがM&Aで重要となるエステ・ネイル・ヘアサロンのM&Aはこちら
優秀な人材を引き継げるかどうか
企業を動かしているのは人材です。優秀な人材が揃っていれば、経験や専門知識、ノウハウを一から構築することなく即戦力として活用することができます。
市場シェア
対象会社がすでに大きな市場シェアを獲得しているのであれば、買い手会社はM&Aによって更なる事業の拡大を図ることが可能になります。
⇒市場でのシェアがM&Aで重要となる日本語学校のM&Aについてはこちら
技術力
技術力は他社との差別化を図るための大きな要因であり、買い手会社はその技術を承継して事業の拡大を図ることが可能になります。
M&Aの相場よりも高い価格でM&Aを行うには
M&Aの売り手企業は少しでも高い価格でのM&Aを望みます。
上述のとおり、M&A価格は企業価値評価やその他の要因に基づき決定されますので、少しでも高い価格でM&Aを行うためには、対象会社の企業価値を高めることやその他の要因を備えることが重要です。
では、どのように企業価値を高めたりその他の要因を獲得すればよいのでしょうか。
収益力を高める
会社の収益力を高めることができれば、企業価値も高くなり、M&Aにおいても高く売却できるようになります。
時価純資産法に営業権を加味して企業価値評価を行う手法を使用する場合、収益力の向上は営業権の評価に反映され、企業価値評価が高くなります。
インカムアプローチは収益性を基準として企業価値評価をする方法ですので、収益力が向上すれば企業価値評価も高くなりますし、マーケットアプローチにおいても比較対象とする会社の収益力が向上するわけですので企業価値評価も高くなります。また、コスト削減による収益力の向上であっても同様に、企業価値評価が高くなります。社内業務の見直しや、コストのかかり過ぎの見直しも、企業価値にはプラスなのです。
資産の含み益
資産の含み益は、現実には利益になっていなくても、売却することで利益が出ます。簿価よりも時価が上回っている時に含み益が生じます。資産の含み益としては、上場有価証券や保険積立金、土地などに存在する場合が多くなっています。
例えば、土地を取得してから数十年経っている場合、高額の含み益が見込まれる可能性があります。その場合、時価純資産が高くなるため、企業価値も向上することとなります。
M&Aにおいて複数の買い手会社と交渉をする
特定の買い手会社候補のみとM&A価格の交渉をすることを相対方式といいますが、これとは別に、入札方式というものがあります。入札方式のメリットの一つには、複数の買い手会社候補が存在していますので会社間で競争原理が働き、M&A価格が高くなることが期待されます。
また、入札方式でなくても、複数の買い手会社候補と交渉をすることによって、競争原理が働き、営業権がより高く評価され、M&A価格が高くなる傾向があります。
その他、特殊な技術や特許、立地、ブランド、繰越余剰金、取引先や顧客リスト、優秀な人材、市場シェア。技術力などについては、一朝一夕には獲得できるものではありませんが、継続的に経営を行う過程で獲得してゆくべきものであり、その結果、M&A価格に影響を与えるような存在となり、M&Aの相場よりも高い価格でM&Aを行うことができるようになるのです。
M&A仲介手数料の相場
M&A仲介手数料には相場があります。
しかし、M&A案件によっても大きく異なります。またM&A仲介会社によってもM&A仲介手数料には違いがあります。なお、M&A仲介を依頼する際には、必ずM&A仲介手数料体系について確認することが必要です。
相談料
M&A仲介の依頼をする前に、まずはM&Aの相談をすることが可能です。ほとんどのM&A仲介会社では相談料を無料としていますが、相談に行く前に、相談料の有無を確認しておく方が良いでしょう。
着手金
着手金とは、M&A仲介依頼時・着手前に支払う費用のことをいいます。M&Aの成否に関わらず支払うものです。着手金の相場としては、無料~数百万円まで幅が広くなっているのであらかじめ確認しておく必要があります。
月額報酬
月額報酬とは、毎月支払いが生じる費用のことをいいます。M&Aのプロセスには数ヶ月~数年に及ぶことも考えられるため、かかる年月が長くなるほど月額報酬の負担が続くことになりますのであらかじめ確認しておく必要があります。
中間報酬
中間報酬とは、基本合意書が締結された日に支払う報酬のことです。中間報酬としては、無料~100万円ほどの固定報酬又は成功報酬の10%~20%であることが多くなっています。また、着手金と同様、M&Aの成否に関わらず返金されることはありませんのであらかじめ確認しておく必要があります。
成功報酬
成功報酬とは、M&Aが成就した際に支払うM&A仲介手数料のことです。最終契約書の締結後又はクロージング後に支払うものとされていることが多くなっています。
成功報酬の相場は、レーマン方式によって算出されることが一般的です。
レーマン方式とはM&A価格に応じて下記の表に基づく計算式により算出されるM&A仲介手数料体系です。この取引総額として、M&A価格を使用するM&A仲介会社と、対象会社の総資産額(M&A価格と負債額の合計額)を使用するM&A仲介会社がおり、後者は、上場M&A仲介会社一社のみとの認識ですが、その場合、M&A仲介手数料が非常に高額になってしまうという問題が存在しています。
記
| 取引総額 | 料 率 |
| 取引総額の5億円以下の部分 | 5.0% |
| 取引総額の5億円超10億円以下の部分 | 4.0% |
| 取引総額の10億円超50億円以下の部分 | 3.0% |
| 取引総額の50億円超100億円以下の部分 | 2.0% |
| 取引総額の100億円超の部分 | 1.0% |
また、成功報酬において最低報酬が決められていることが一般的です。最低報酬の額としては、500万円~3,000万円といったイメージですが、銀行や上場M&A仲介会社などは3000万円のところが多いという認識です。
リテイナーフィー
リテイナーフィーとは、M&A仲介会社をリテイン(契約維持)するための費用であり、毎月支払う月額報酬(定額顧問料)のことです。
M&A仲介会社によっては必要がない場合もありますが、月額50万円ほどの場合もあります。M&A仲介会社をリテイン(契約維持)する間発生しますのであらかじめ確認しておく必要があります。
まとめ
M&A価格は企業価値評価やその他の要因に基づき決定され、企業価値評価は「インカムアプローチ」「マーケットアプローチ」「コストアプローチ」などにて評価され、それらに基づいてM&A価格を交渉・決定してゆくこととなりますので、M&Aの相場も、必然的にこれらの要因に影響されます。
ですので、M&Aを検討されている経営陣の皆様は、企業価値評価などのM&Aの相場に影響を及ぼす要因をよく理解し、満足のゆくM&A価格でのM&Aを実現できるようにかんばって頂きたいと思います。