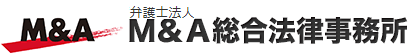前提条件■■■第5条■■■■■■■■■■第5条 (クロージングの前提条件)1. 売主は、クロージング日において、以下の各号の事由が全て充足されていることを条件として、第3条に定める買主に対する義務(本件株式の譲渡義務)を履行するものとする。 (1) 第7条に規定する買主の表明保証の全てが、クロージング日に、真実かつ正確であること (2) 買主が本契約上の義務について違反をしていないこと 2. 買主は、クロージング日において以下の各号の事由が全て充足されていることを条件として、第4条第2項に定める買主の義務(譲渡代金の支払義務)を履行するものとする。 (1) 第6条に規定する売主の表明保証の全てが、クロージング日に、真実かつ正確であること (2) 売主が本契約上の義務について違反をしていないこと |
第5条 解説第5条は、「前提条件」に関する規定である。 英語では、Condition Precedentと言い「前提条件」と直訳される。 前提条件について本条1項では、売主の義務(対象会社の株式の譲渡義務)に関する「前提条件」が規定されている。したがって、売主は、本条1項に規定されている「前提条件」が満たされた場合のみ、株式譲渡の実行義務を負うのである。 本条2項では、同様に、買主の義務(株式譲渡の譲渡代金の支払義務)に関する「前提条件」が規定されている。また、同様に、買主は、本条2項で規定されている「前提条件」が満たされた場合のみ、株式譲渡の譲渡代金の支払義務を負うのである。 本条に規定された「前提条件」は、(1)と(2)の2つであるが、多数の前提条件を規定することも多く、本条は、最も少ない数の「前提条件」であり、①表明保証がすべて真実かつ正確であること、及び、②当事者が本契約上の義務について違反していないことのみが規定されている。 「前提条件」が充足されない以上、株式譲渡契約の相手方は、自らの義務を履行してくれないのであり(売主は株式を譲渡してくれないのであり、買主は譲渡代金を支払ってくれないのであるから)、当事者としては、何とかして相手方の要請する「前提条件」を充足させることが必要となる。 前提条件の放棄についてなお、「前提条件」は、いずれも当事者の義務の「前提条件」であるから、その相手方が「前提条件」の全部又は一部が充足されていない場合、その「前提条件」を放棄して、相手方が「前提条件」を充足していないにも拘らず、自ら自分の義務を履行することは禁止されない。 この点、この趣旨を明らかにするために、本条に「なお、クロージング日において以下の各号の事由の全部又は一部が充足されていない場合には、買主は、その任意の裁量により、かかる事由のいずれも放棄して第4条第2項に定める義務を履行することができるものとする。」と規定する場合もある。 なお、通常は、当事者が「前提条件」を放棄した場合、相手方としては、その「前提条件」を永久に充足せずに放置してよいかという問題が生じるものの、当事者としては、本来であれば、「前提条件」を放棄する際に、相手方と協議し、その「前提条件」に関して、永久に充足する必要がないのか、今後速やかに充足する必要があるのか、取り決めをするべきである。すなわち、そのような取り決めを行わずに一方的に「前提条件」を放棄してしまった場合、相手方は、もうその「前提条件」は永久に充足しなくても良いものと考える可能性が高い。 しかし、たいていの場合は、当事者が「前提条件」を放棄したとしても、それはその当事者の好意で「前提条件」を充足していないにも拘らず株式譲渡を実行してくれたのであり、「前提条件」を充足する義務を永久に無しにするものではなく、最終的に、相手方が「前提条件」を充足できず、それが株式譲渡契約書場の表明保証違反や義務違反を構成する場合は、相手方が損害賠償責任を負うものと解釈することが当事者の合理的意思である解釈できるため、そのように放棄された「前提条件」は、基本的に、クロージング後、可及的速やかに充足されることが求められると考えるべきである。 ただ、放棄された「前提条件」は、永久に充足する必要がないのか、可及的速やかに充足する必要があるのか、いずれなのかということで紛争化することを避けるためにも、の趣旨を明らかにするために、本条に、「なお、クロージング日において以下の各号の事由の全部又は一部が充足されていない場合には、買主は、その任意の裁量により、かかる事由のいずれも放棄して第4条第2項に定める義務を履行することができるものとする。」に続けて、買主による前提条件の放棄は、損害賠償又は補償請求権を放棄する趣旨ではない旨を規定することもある。 前提条件と遵守条項についてその他、前提条件としては、対象会社の取締役会又は株主総会において、本件株式譲渡に関する譲渡承認決議が行われることを規定することもある。ただし、対象会社の株式譲渡承認を取得することは、株式譲渡契約書上の義務として、通常、別途、遵守条項として規定され、かつ、(2)の「売主が本契約上の義務について違反をしていないこと」は、通常、株式譲渡の「前提条件」として規定されるので、本件株式譲渡に関する譲渡承認決議が行われることについては、「前提条件」として殊更に規定しなくても、いずれにしろ株式譲渡の実行の「前提条件」となるため、敢えて、「前提条件」として規定する必要性はあまりない。 ただ、相手方に対して、その「前提条件」の充足を特に念を押す必要があるような場合や、その「前提条件」を充足することを重視していることを印象付ける必要がある場合には、屋上屋を重ねることとなるものの、表明保証や遵守条項して規定されているものを、重ねて「前提条件」にも盛り込むことがある。 その他、「前提条件」としては、株式譲渡を実行することにより、許認可が失効するような場合、許認可の再取得を「前提条件」として規定することや、いわゆるチェンジ・オブ・コントロール条項(COC条項)(事業承継M&Aが実行され、対象会社の支配権が変更になったような場合に解除事由などが発生する取引先等との取引契約における条項)との関連で、取引先等の事前承諾を取得することなど、敢えて、「前提条件」に明記することがあるものの、通常このような内容は、株式譲渡契約書に遵守条項としても規定されるため、やはり屋上屋を重ねて強調することにより、重ねて「前提条件」にも盛り込んでいるものといえる。 その他、取締役会又は株主総会の株式譲渡の譲渡承認決議の取得や、許認可の再取得、いわゆるチェンジ・オブ・コントロール条項(COC条項)に関する取引先等の事前承諾お取得などについて、遵守条項には規定しないものの、前提条件には規定する場合がある。このような場合は、買主としては、それらの条件を充足しなかった場合、売主に対して、損害賠償責任・補償責任は追及しないものの、前提条件に抵触するとして、株式譲渡を実行しないという強い意志の表れとも考えられるし、買主としては、クロージングに際しては、前提条件の充足については、柔軟に対応しようとする意図であるとも考えられる。 独占禁止法上の企業結合の届出についてその他、M&Aの株式譲渡契約書の株式譲渡や事業譲渡契約書の事業譲渡の「前提条件」としては、独占禁止法上の企業結合の届出を行い、かつ待機期間(原則として30日)を経過していることを規定することも多くあるものの、事業承継M&Aにおいては独占禁止法上の届け出が求められるような取引(原則として、買主の売上が200億円超かつ対象会社の売上が50億円超(事業譲渡の場合は売上が30億円超)の場合)、は多くは存在しないため、ここでは説明を割愛する。 表明保証の機能と効果■■■第6条及び第7条■■■■■■■■■■第6条 (売主の表明保証)1. 売主は、買主に対して、本契約締結日及びクロージング日において、別紙1記載の各事項が真実かつ正確であることを表明し、保証する。 2. 本条において売主が表明保証した事項に関する買主の認識又は認識可能性は、これらの表明保証の効力又はこれらに関する補償又は救済手段の行使又は効力に影響を及ぼさないものとする。 第7条 (買主の表明保証)1. 買主は、売主に対して、本契約締結日及びクロージング日において、別紙2記載の各事項が真実かつ正確であることを表明し、保証する。 2. 本条において買主が表明保証した事項に関する売主の認識又は認識可能性は、これらの表明保証の効力又はこれらに関する補償又は救済手段の行使又は効力に影響を及ぼさないものとする。 第6条及び第7条 解説第6条及び第7条は、「表明保証」の規定である。 表明保証とは表明保証は、売主又は買主候補会社が相手方に対して、一定の事項が真実であり正確であることを表明し、表明したことを保証する条項である。 「表明保証」の具体的中身については、項目も分量も多岐にわたるため、別紙に記載して添付することが多く、本契約書においてもそのようになっている。 「表明保証」条項としては、例えば、別紙に規定されているように、対象会社には「従業員に関して、支払期限が到来した未払賃金・退職金その他の報酬、又は社会保険料は存在しない。」といった「表明保証」が存在するが、すなわち、対象会社に瑕疵がある旨の規定が種々存在する。 事業承継M&Aに関するトラブルのほとんどは、この表明保証条項を巡って発生しており、特に留意が必要ある。 表明保証違反の効果について表明保証に違反した場合、前提条件を充足しないため株式譲渡が実行されないこととなるし、損害賠償条項・補償条項に基づき、表明保証違反に基づく損害について、損害賠償義務・補償義務を負うこととなるし、表明保証違反が解除原因ともなり得る。 すなわち、「表明保証」に違反し、「表明保証」の規定されている事実が真実と異なる場合、前提条件が充足されずに株式譲渡実行義務が発生しないという効果や、損害賠償条項・補償条項に基づき、表明保証違反に基づく損害について、損害賠償義務・補償義務を負うという効果が発生し、「表明保証」の規定されている事実が真実と異なる場合、それが解除事由となり、相手方に株式譲渡契約の解除権が発生してしまうという効果が発生するのである。 このように、「表明保証」は、株式譲渡の多方面において影響を及ぼす重要な規定なのである。 表明保証の損害賠償責任・補償責任の無過失責任性表明保証違反は、債務不履行ではなく、当事者の帰責事由(当事者の故意過失)があるわけではなく、単なる事実の表明に誤りがあったということではあるが、その事実の表明を信頼して取引に入る相手方当事者の保護のための規定であり、それに違反する結果として、前提条件を充足せず株式譲渡が実行されない、損害賠償義務・補償義務を負う解除原因になるなどの効果を持たせて、相手方当事者を保護することで、当事者間の情報の格差により相手方当事者が取引に入れないこととなることを防ぎ、取引を促進するための条項である。 そうであるからこそ、この「表明保証」違反に基づく損害賠償責任・補償責任というのは、民商法の過失責任の原則に基づく責任ではなく、真実であると「表明保証」したにもかかわらず真実でなかった場合の売主と買主の間の損失分担のための規定であるから、無過失の補償責任ともいうべきものである。 表明保証と瑕疵担保責任について買主が、このような瑕疵のある対象会社を買収してしまった場合、不動産取引と同様に、瑕疵担保責任(民法570条及び566条[1]など)を追及することにより損害を回復することができるのではないかと思われるかもしれない。しかし、不動産取引の譲渡対象物は不動産であるのに対して、株式譲渡契約書における譲渡対象物は株式会社ではあるものの具体的には株式であり、株式自体にはおそらく瑕疵は存在しない。仮に、対象会社が株券発行会社であり、株券に損傷があり欠損していたような場合、それは、譲渡対象物の瑕疵であり、瑕疵担保責任が追及できるかもしれない。 しかし、事業承継M&Aにおいて、買主が、このような瑕疵のある対象会社を買収してしまった場合に追求したいのは、そのような瑕疵担保責任を追及したいのではなく、対象会社において、その会社の性質上当然有するべき性質を有していなかった場合に、それを瑕疵として瑕疵担保請求権を追及したいのである。 しかし、瑕疵担保責任の「瑕疵」とは、通常備わっているべきあるべき機能・品質・性能・状態が備わっていないこと、と表現され、不動産においては、通常備わっているべきあるべき機能・品質・性能・状態というものについては、一応社会的コンセンサスがあると思われる反面、会社については、通常備わっているべきあるべき機能・品質・性能・状態というものは、会社ごとに様々であり、特定の問題が、必ずしも瑕疵とは言えない。したがって、買主が売主に対して瑕疵担保請求権を行使したとしても、買主の主張するその株式会社の瑕疵が、果たして瑕疵なのか瑕疵でないのかということ自体が明確ではないものと思われる。したがって、事業承継M&Aにおいては、株式譲渡契約書に、瑕疵担保責任が規定されていて、対象会社に特段の問題が存在していても、買主は、必ずしも、売主に対して、責任追及をすることはできないということとなる。 したがって、株式譲渡において、買主が売主に対して瑕疵担保責任(民法570条及び566条など)を追及することは容易ではなく、どのような状態の場合、買主が売主に対して損害賠償責任・補償責任を追及することが可能かを明らかにするべく、多くの株式譲渡契約書においては、多数項目にわたる「表明保証」が規定され、売主に各項目が真実であることを「表明保証」してもらうことによって、それが真実でなかった場合、買主が売主に対いて損害賠償責任・補償責任を追及することができるという契約書の構造になっているのである。 表明保証に関する認識又は認識可能性の影響買主が、売主の表明保証違反の損害賠償責任・補償責任などを追及する場合に問題となるのが、表明保証をした事項に関する認識又は認識可能性の問題である。 すなわち、買主としては、事業承継M&Aにより損失を被った場合、売主が、対象会社に関して、何らかの表明保証をしており、その違反があった場合は、表明保証違反を根拠に、売主に対して、損害賠償責任・補償責任を行いたい。 買主としては、売主の行ったその表明保証を信用して、この事業承継M&Aに取り組んだのであるから当然である。 ただ、買主が表明保証を信用してこの事業承継M&Aに取り組んだというのであれば、買主がその表明保証違反について、認識又は認識可能性があった場合まで、買主の表明保証違反に基づく損害賠償責任・補償責任を認めるべきなのか否かということが問題となる。 この点、平成18年1月17日の東京地方裁判所判決平成16年(ワ)第8241号では、表明保証違反につき、売主がデューデリジェンス(DD)に資料を開示していたことに関連して、買主が悪意又は重過失がある場合、表明保証違反に基づく損害賠償責任・補償責任が認められない可能性があることを判示しつつ、売主が表明保証違反の事実を故意に秘匿したとして、売主の表明保証違反の責任を認めている。 すなわち、売主が表明保証をしたとしても、買主が表明保証違反の事実を認識していたり、認識可能性があったのに重大な過失により認識していなかった場合には、買主は、売主に対して、表明保証違反の損害賠償責任・補償責任を行うことができないのである。他方、売主は、デューデリジェンス(DD)に資料を開示していたとしても、表明保証違反の事実を故意に秘匿した場合は、表明保証違反の責任を免れないのである。 サンドバッキング条項について上記のとおり、裁判例にて、買主が表明保証違反の事実を認識していた場合には、買主は、売主に対して、表明保証違反に関する認識の有無に係らず表明保証違反の損害賠償責任・補償責任を問うことができる旨を規定すれば、買主が表明保証違反の事実を認識していた場合でも、表明保証違反の損害賠償責任・補償責任を行うことができるのではないかとも思われる。 第6条と第7条それぞれの2項は、これであり、いわゆるサンドバッギング条項である。 なお、株式譲渡契約書において、このいわゆるサンドバッキング条項を規定する場合もあれば、いわゆるアンチ・サンドバッキング条項(表明保証違反に関する認識があった場合には表明保証違反の損害賠償責任・補償責任を認めない規定)を規定することもあれば、いずれも規定しない場合もある。いずれも規定しない場合は、上記の裁判例の立場がそのまま適用されることに相違ない。 事業承継M&Aにおいては、結果として、いずれも規定しない場合が多いように見受けられるものの、いわゆるサンドバッギング条項を規定する場合も多くみられる。 買主は、対象会社に対してデューデリジェンス(DD)を実施するため、実際は、特定の事項について、表明保証違反の状態にあることを認識するに至ることは多い。例えば、売主は対象会社における未払残業代の存在について否定し、表明保証を行うものの、買主は、対象会社をデューデリジェンス(DD)した結果、実際は、対象会社に未払残業代が存在することを発見するような場合である。 このような場合、買主は、そのような表明保証違反の状況があることを認識しつつ対象会社を買収するのであるから、そのような表明保証違反のリスクが顕在化して、例えば、従業員から対象会社に対して未払残業代の請求が行われたとしても、そのような場合は表明保証違反の責任追及を行うべきではないという考え方もある。上記の裁判例は、このようなスタンスであるものと思われる。 ただ、買主が労力とコストをかけてデューデリジェンス(DD)を実施し、売主の表明保証違反の事実を発見した時、売主に対する表明保証違反の責任追及を禁止することは経済合理的ではないと思われる。また、買主が売主の表明保証違反の事実を発見したとしても、その問題の詳細や影響の大きさなどまでは容易に判明するものではなく、表明保証違反の事実を認識していただけですべての売主に対する表明保証違反の責任追及を禁止することも経済的不合理とも思われる。 このような検討から、事業承継M&Aにおいては、現在においては、多くの場合で、いわゆるサンドバッキング条項を規定することが多くなっている。 ただ、他方、事業承継M&Aの交渉中に、表明保証違反を知っていたのなら、売主に対して損害賠償責任・補償責任をするのはおかしいのではないかという見解が売主から出されることもあり、最終的に、株式譲渡契約書にいわゆるサンドバッキング条項を盛り込まないこととなることも多い。 ただ、株式譲渡契約書にいわゆるサンドバッキング条項を盛り込む場合においても、このいわゆるサンドバッキング条項が裁判所で有効と判断されるか否か分からない(サンドバッキング条項を規定したとしても、裁判になった場合、上記の裁判例の立場が貫かれ、表明保証違反に関する認識があった場合には、表明保証違反の損害賠償責任・補償責任が認められない可能性もある)ということもある。 したがって、近時においては、買主が、デューデリジェンス(DD)において、表明保証違反の状態を発見した場合には、表明保証条項のみならず(表明保証条項ではなく)、特別補償条項を別途規定することにより、例えば、未払残業代などが発見され、そのリスクが顕在化した場合に、売主に対して、特別補償条項を発動することにより、その損失について補償請求を行えるように規定することが一般的となっている。 [1] 民法570条(売主の瑕疵担保責任)売買の目的物に隠れた瑕疵があったときは、第566条の規定を準用する。ただし、強制競売の場合は、この限りでない。 民法566条(地上権等がある場合等における売主の担保責任)1 売買の目的物が地上権、永小作権、地役権、留置権又は質権の目的である場合において、買主がこれを知らず、かつ、そのために契約をした目的を達することができないときは、買主は、契約の解除をすることができる。この場合において、契約の解除をすることができないときは、損害賠償の請求のみをすることができる。 2 前項の規定は、売買の目的である不動産のために存すると称した地役権が存しなかった場合及びその不動産について登記をした賃貸借があった場合について準用する。 3 前二項の場合において、契約の解除又は損害賠償の請求は、買主が事実を知った時から一年以内にしなければならない。 遵守条項■■■第8条■■■■■■■■■■第8条 (クロージングまでの誓約事項)1. 売主は、本契約締結日以降、クロージングまでの間、対象会社をして、善良なる管理者の注意をもって、本契約締結日以前と実質的に同一かつ通常の業務の方法により、業務の執行及び財産の管理・運営を行わせしめるものとし、買主の事前の書面による承諾のある場合を除き、通常の業務以外の重要な業務執行を一切行わせしめてはならないものとする。 2. 売主は、本契約締結日以降、クロージングまでの間、対象会社に関して、訴訟、法令違反、その他事業、資産、負債、財務状態、経営成績、キャッシュフロー又は将来の収益計画に重大な悪影響を及ぼすおそれのある事由又は事象が生じた可能性を認識した場合には、直ちに買主に対してその報告を行うものとする。 |
第8条 解説第8条以下は、いわゆる遵守条項である。 英語ではCovenants(コベナンツ)と言われ、株式譲渡契約書を構成する主要な項目の一つである。 遵守条項とは、売主又は買主候補会社が、事業承継M&Aに際して、相手方に対して約束し遵守する事項である。 善管注意義務の遵守条項について本条1項は、株式譲渡契約書締結日からクロージング日までの間、売主に、対象会社の経営に関して、善管注意義務違反を負わせる遵守条項である。 すなわち、買主は、株式譲渡契約書の締結日の直前まで、対象会社についてデューデリジェンス(DD)を行い、その結果を踏まえて企業価値を算定し、それに基づいて株式譲渡価格を決定し、株式譲渡契約を締結するのであるから、株式譲渡契約の締結日以降、売主が、対象会社の企業価値を変動させるようなことをするようでは、株式譲渡価格の前提が崩れてしまうのである。であるから、買主としては、株式譲渡契約の締結日以降、対象会社の企業価値を変動させるようなことを禁止する必要があり、売主に対して、その間、対象会社の経営に関して、善管注意義務を規定しているのである。 勿論、買主が事前に承諾したことであれば、企業価値を変動させるような業務運営を行っても問題はない。買主もそれを前提として企業価値を計算し、株式譲渡代金を決定しているのであり、また、そうでなくても、承諾をする前提条件として、売主と別途合意し、買主が想定外の損失を被らないよう、何らかの施策を要求したり、株式譲渡価格の変更を要求したり、買主の株式譲渡価格の前提が崩れない対策が可能である。 追加デューデリジェンス(DD)の必要性についてこのような善管注意義務の遵守条項を規定していても、売主や対象会社のこの善管注意義務違反が行われることはあり、買主は、株式譲渡のクロージングの直前まで、対象会社について、デューデリジェンス(DD)情報をアップデートする必要がある。 すなわち、買主は、デューデリジェンス(DD)完了から、株式譲渡契約締結日までに、一定の期間が空いてしまったような場合、株式譲渡契約締結の直前に、追加デューデリジェンス(DD)を行うことで、対象会社の企業価値を変動させる事項が発生していないかを最終的に確認する必要がある。 また、デューデリジェンス(DD)完了(又は株式譲渡契約書の締結)からクロージングまでの間に、一定の期間が空いてしまったような場合、クロージング直前に、対象会社の企業価値を変動させる事項が発生していないかを、最終的に確認する追加デューデリジェンス(DD)を行うこともある。 通常、株式譲渡契約書の表明保証には、売主は買主に対して対象会社に関する重要な事項はすべて開示した旨の表明保証(完全開示条項)が規定されることから、対象会社の企業価値を変動させる事項が発生していたにも拘らず、売主が買主に対してその事実を開示しなかった場合には、売主は買主に生じた損害について、損害賠償責任・補償責任を負担することとなるが、事後的に表明保証違反の事実を発見して、売主に対して、損害賠償責任・補償責任するのでは、救済が十分ではなくなる可能性もあり、追加デューデリジェンス(DD)によって、クロージング前に表明保証違反などの事実を確認し、未然に対応をすることが好ましい。 後発事象の通知義務について本条2項には、同様の趣旨から、売主が、対象会社の企業価値を変動させる事項(後発事象)を認識した場合の、買主への通知義務が規定されている。 この規定は、対象会社の企業価値を変動させる事項(後発事象)が発生している場合は、買主としては、その事実を踏まえて、売主に対して、対象会社の企業価値の毀損させる事項(後発事象)の発生により、買主が想定外の損失を被らないよう、何らかの施策を要求したり、株式譲渡価格の変更を要求したり、あるいはそもそもこの株式譲渡を取りやめるか否かを検討することができる機会を与えるための規定である。 しかし、このように対象会社の企業価値を変動させる事由が発生したとしても、それに応じて、株式譲渡価格を変更することは、その旨の当事者の合意がなければ不可能である。そこで、株式譲渡契約書に、そのような対象会社の企業価値を変動させる事由が発生した場合、株式譲渡価格について再交渉することができる規定を盛り込むこともある。 また、そうでなくても、株式譲渡価格の変更を要するような重要な事項が発生したのであれば、表明保証条項やその他の遵守条項に違反することとなることが多いと思われ、また、特に、通常、株式譲渡契約書の表明保証条項には、売主は買主に対して対象会社に関する重要な事項はすべて開示した旨の表明保証(完全開示条項)が含まれることからも、買主は、売主に対して、いずれかの方法により、損害賠償責任・補償責任を追及することができ、それにより、実質的に、株式譲渡価格を減額することができ、また、株式譲渡契約書の前提条件や解除条項に基づき、事業承継M&Aの取り止めをすることもできる。また、そうであるからこそ、このような場合、売主は、通常、株式譲渡価格の再交渉などに応じざるを得ないということとなる。 |
⇒M&Aトラブルを解決する方法を見る! 株式譲渡承認■■■第9条■■■■■■■■■■第9条 (譲渡承認の取得)売主は、クロージング日までに、対象会社をして、取締役会を開催させ、本件株式の譲渡を承認する決議を行わせるものとする。 |
第9条 解説第9条は、株式譲渡承認に関する遵守条項である。 すなわち、遵守条項として、売主に対して、対象会社の株式譲渡に関する承認を取得する義務を負わせる規定である。 株式譲渡承認に関する遵守条項について事業承継M&Aにおいては、対象会社は、通常、株式譲渡制限会社(株式の譲渡を対象会社に対抗するためには対象会社の承諾が必要な会社)であることから、売主が買主に対して株式の譲渡を実行するためには、クロージングまでに、対象会社の承諾を取得する必要がある。 なお、株式譲渡制限会社であっても、対象会社の組織構成に応じて、株式譲渡の承認機関が異なり、多くの場合は、取締役会であるが、取締役会を設置していない取締役会非設置会社においては、株主総会であることが一般的である。 株式譲渡承認取得の手続について会社の株式譲渡の承認を得るためには、会社法上、対象会社に対する株式譲渡承認請求や対象会社からの株式譲渡承認通知などの手続き(会社法136条から139条[1])が必要とされるものの、事業承継M&Aの株式譲渡においては、多くの場合、そのような手続きまでは行われず、単に、対象会社が取締役会(又は株主総会)で株式譲渡に関する承認決議を行い、その旨の取締役会(又は株主総会)議事録を作成し、クロージングまでに、売主から、買主に対して、その取締役会(又は株主総会)議事録の写しを提出することが一般的である。会社法の株式譲渡承認に関する手続規定(会社法136条から139条)は、対象会社の利益のための規定であることから、対象会社が敢えてその利益を放棄し、株式譲渡承認決議を行うことは有効であるからである。 対象会社の経営陣が株式譲渡を承認しない場合について売主が対象会社の経営権を握っている場合、売主が対象会社の株式を譲渡すると言えば、対象会社も株式譲渡を承認するであろうから、これらの手続を省略したとしても、実務上の問題は発生しない。 しかし、対象会社において、取締役会設置会社で、所有と経営が分離しており、売主が対象会社の取締役会の過半数の議決権を握っていない場合など、売主が対象会社の株式を譲渡すると言っても、対象会社の取締役会がそれを承認しない可能性がある場合は、考慮が必要である。 また、売主が対象会社の取締役会の経営権を支配できていない場合など、オーナー株主が事業承継M&Aをしようとしても、対象会社の経営陣の協力が得られない結果、買主が、対象会社のデューデリジェンス(DD)を実施することができなかったり、買主が対象会社を買収したとしても、対象会社の経営陣の妨害にあり、買主が対象会社の経営権を掌握できそうにないような場合、結局、事業承継M&Aは困難となってしまうことも多い。 その場合、対象会社の経営陣に株式譲渡について理解して頂くプロセスが必要になるとともに、最終的に対象会社の経営陣が株式譲渡を承認しないのであれば、売主としては、対象会社の経営陣を解任して、改めて経営陣を指名したり、売主の意向に沿った経営陣を指名して、取締役会の過半数を掌握してから、対象会社の取締役会に株式譲渡を承認させるなどの手続きが必要となる。 [1]会社法136条(株主からの承認の請求)譲渡制限株式の株主は、その有する譲渡制限株式を他人(当該譲渡制限株式を発行した株式会社を除く。)に譲り渡そうとするときは、当該株式会社に対し、当該他人が当該譲渡制限株式を取得することについて承認をするか否かの決定をすることを請求することができる。 会社法137条(株式取得者からの承認の請求)1 譲渡制限株式を取得した株式取得者は、株式会社に対し、当該譲渡制限株式を取得したことについて承認をするか否かの決定をすることを請求することができる。 2 前項の規定による請求は、利害関係人の利益を害するおそれがないものとして法務省令で定める場合を除き、その取得した株式の株主として株主名簿に記載され、若しくは記録された者又はその相続人その他の一般承継人と共同してしなければならない。 会社法138条(譲渡等承認請求の方法)1 次の各号に掲げる請求(以下この款において「譲渡等承認請求」という。)は、当該各号に定める事項を明らかにしてしなければならない。 一 第136条の規定による請求 次に掲げる事項 イ 当該請求をする株主が譲り渡そうとする譲渡制限株式の数(種類株式発行会社にあっては、譲渡制限株式の種類及び種類ごとの数) ロ イの譲渡制限株式を譲り受ける者の氏名又は名称 ハ 株式会社が第136条の承認をしない旨の決定をする場合において、当該株式会社又は第140条第四項に規定する指定買取人がイの譲渡制限株式を買い取ることを請求するときは、その旨 二 前条第一項の規定による請求 次に掲げる事項 イ 当該請求をする株式取得者の取得した譲渡制限株式の数(種類株式発行会社にあっては、譲渡制限株式の種類及び種類ごとの数) ロ イの株式取得者の氏名又は名称 ハ 株式会社が前条第1項の承認をしない旨の決定をする場合において、当該株式会社又は第140条第四項に規定する指定買取人がイの譲渡制限株式を買い取ることを請求するときは、その旨 会社法139条(譲渡等の承認の決定等)1 株式会社が第136条又は第137条第1項の承認をするか否かの決定をするには、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によらなければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。 2 株式会社は、前項の決定をしたときは、譲渡等承認請求をした者(以下この款において「譲渡等承認請求者」という。)に対し、当該決定の内容を通知しなければならない。 |
⇒M&Aトラブルを解決する方法を見る! COC条項(チェンジ・オブ・コントロール条項)■■■第10条■■■■■■■■■■第10条 (取引先等の承諾の取得)売主は、クロージング日までに、対象会社をして、対象会社が締結している取引先等との契約に関して、本件株式の譲渡について、当該取引先等の事前承諾が必要な場合には、取引条件を維持しつつ、当該取引先等の承諾を取得させるものとする。 |
第10条 解説第10条は、いわゆるチェンジ・オブ・コントロール条項(COC条項)に関する遵守条項である。 すなわち、遵守条項として、いわゆるチェンジ・オブ・コントロール条項(COC条項)の処理(この事業承継M&Aが実行され、対象会社の支配権が変更になったような場合に解除事由などが発生する取引先等との取引契約について、その取引先等の承諾等を取得すること)を定めた規定である。 (1) チェンジ・オブ・コントロール条項(COC条項)に関する遵守条項について株式譲渡契約書において、取引先との取引契約や賃貸人との賃貸借契約など、株主や会社の実質的支配者(大株主)や代表取締役などが変更になった場合に、その取引契約や賃貸借契約などが解除になる旨を定めた規定や、そのような場合に対象会社からその取引先や賃貸人などに対する事前通知や届出を求めたり、事後通知や届出を求めたりする規定(いわゆるチェンジ・オブ・コントロール条項(COC条項))が規定されていることは多い。 その取引先や賃貸人などとしては、契約の相手方が対象会社であり、その支配権を有するのが売主であることから、売主を信頼してその契約関係に入ったものの、買主とは特段の信頼関係もなく、そのような場合は、契約を解除することができるように契約書に規定していることが多いのである。 (2) チェンジ・オブ・コントロール条項(COC条項)違反の効果と対策について買主が、事業承継M&Aにより、対象会社を買収した暁には、買主は、対象会社の事業を、従前どおり運営できることを想定していることが一般的である。 にもかかわらず、対象会社と取引先や賃貸人などとの取引契約書や賃貸借契約書などに、このようないわゆるチェンジ・オブ・コントロール条項(COC条項)が規定されており、同規定に基づき、取引先や賃貸人などとの契約が解除されてしまった場合、買主は、対象会社の事業を従前どおり運営することができなくなってしまい、対象会社の企業価値が毀損されてしまい、買主が想定する株式譲渡価格の前提を崩すこととなるのである。 実際、事業承継M&Aを行った結果、主要取引先から取引契約を解除されてしまい、企業価値が大きく毀損してしまい、買主が売主に対して損害賠償請求をしている事例に遭遇することもままある。また、事業承継M&Aを行った結果、賃貸人から複数の賃貸借契約を解除され、多くの店舗を閉店せざるを得ず、売主と買主がトラブルになっていることに遭遇することも多い。 いずれにしろ、買主としては、株式譲渡契約書締結後、クロージングまでに、取引先や賃貸人などに通知し、とくに重要な取引先や賃貸人などには、自ら売主とともに訪問し、挨拶をするとともに、契約継続の意向を確認しておく必要がある。 また、融資を受けている金融機関に関して、通常、銀行取引約定書に、このいわゆるチェンジ・オブ・コントロール条項(COC条項)が規定されている。また、特に創業支援融資などの特別なテーマ性を有する融資の場合、対象会社の株主が変更になった場合など、いわゆるチェンジ・オブ・コントロール条項(COC条項)その他の規定に基づいて、契約は終了とされ、突如、融資の返済が求められることになるため注意が必要である。 ライセンス契約などについても、ライセンサーは、売主とは競業関係に無く、良好な関係であったものの、買主とは協業関係にあるなどの場合は、このいわゆるチェンジ・オブ・コントロール条項(COC条項)に基づいて、いとも簡単に、契約が解除されてしまう可能性があることにも注意が必要である。 なお、事業承継M&Aにおいて、売主が個人であり、買主が中堅企業又は大企業であるような場合は、取引先や賃貸人などとしても、買主に対する信頼としては心配はなく、いわゆるチェンジ・オブ・コントロール条項(COC条項)があったとしても、これを発動することはなく、従前どおり契約を継続して頂けることが一般的であることも事実である。 ただ、従前どおり契約を継続して頂ける場合であっても、取引先から取引条件の変更を要求されることもあり、一定の保証金の提供を求められるとか、取引単価の条件の変更(悪化)を要求される場合、契約の更新料を求められる場合、保証人の追加・変更を求められるとか、保証会社の更新が必要になり追加保証料が必要とされる場合もある。また、買主の信用調査が必要とされ、信用調査費用を請求されることもある。 このような場合、買主としては、対象会社の企業価値を毀損し、買主の想定する株式譲渡価格の前提が崩れるわけであるから、買主は、そのような事態が生じないよう、売主に対して、取引先などと粘り強く交渉するよう求めたり、また、自ら取引先や賃貸人などと交渉を行ったりする必要があろう。また、そのような事態が生じた結果、買主が想定した企業価値の前提が大きく崩れ、事業承継M&Aの前提が崩れるような場合は、第10条の遵守条項違反として、この事業承継M&Aを取りやめることも検討する必要がある場合もあろう。 |
貸借関係清算■■■第11条■■■■■■■■■■第11条 (金銭消費貸借関係の清算)売主は、売主と対象会社との間の金銭の貸借関係(もしあれば)について、クロージング日に、清算するものとする。 |
第11条 解説第11条は、借入金の清算に関する遵守条項である。 (1) 借入金の清算に関する遵守条項について事業承継M&Aの対象となる中小企業、零細企業においては、オーナー(売主)が、対象会社に対して、運転資金等の金銭を貸し付けていることが多い。また、金銭を貸し付けている場合以外に、オーナー(売主)は、実際には対象会社に対して金銭を貸し付けていないものの、対象会社が経営不振の時代や資金繰りに窮した場合などに、役員報酬を受領せずに、対象会社に対して、その役員報酬相当額の貸付を行ったこととして経理処理している場合(準消費貸借)も多い。 また、反対に、オーナー(売主)が対象会社から金銭の借り入れを行って言う場合もある。すなわち、オーナー(売主)が、対象会社を自己の財布代わりに使用していることが多いことも、事業承継M&Aの対象会社である中小企業、零細企業の特徴である。 事業承継M&Aにより、対象会社は、他人(買主)の会社になるわけだから、売主としては、対象会社に対する金銭の貸し借りの関係を清算して頂く必要がある。 売主にとっても、この事業承継M&Aの機会に、対象会社から貸付金を返済してもらわないと、その後、対象会社は他人(買主)の会社になるわけだから、容易に貸付金の返済を受けることができなくなってしまいこともあり、また、借入金については激しく債権回収をされることとなる可能性も高く、事業承継M&Aの機会に対象会社に対する貸付金や対象会社からの借入金を清算しておくことは重要であろう。 (2) 返済原資がない場合の対策についてこの点、売主が、対象会社に対して、貸付金を有している場合、対象会社に返済原資があれば、対象会社から売主に対して、そのまま返済をすればよいのであるが、そうではなく、対象会社に返済原資がない場合は問題である。そのような場合は、事業承継M&Aのクロージング日に、買主が対象会社に対して金銭の貸し付けを実行し、クロージング日のうちに、対象会社が売主に対して金銭の返済を行うというメカニズムを、株式譲渡契約書に盛り込む必要がある。 また、対象会社が売主に対して金銭を貸し付けている場合、売主に返済原資があればよいが、売主に返済原資がないような場合もある。また、売主が自らの個人財産から返済資金を出捐することに、抵抗感を覚えることも多い。そのような場合は、売主から対象会社に対する金銭の返済について、その相当額について、株式譲渡代金と相殺する又は株式譲渡代金から控除するメカニズムを、株式譲渡契約書に盛り込む必要がある。 (3) 借入金の清算を行わない場合もある勿論、このように、オーナー(売主)の貸借関係については、清算する場合だけではなく、オーナー(売主)にその貸付金債権を放棄してもらう場合や、オーナー(売主)から対象会社に対する貸付金についても、株式譲渡と同時に、買主に対して譲渡する債権譲渡スキームを採用することもあり、また、オーナー(売主)から対象会社に対する貸付金債権を、デット・エクイティ・スワップ(DES)の方法により、対象会社に対する株式(出資金)に転換し、買主に対して、その新株式も一緒に株式譲渡するスキームを採用する場合もある、その際に、その分、株式譲渡代金を調整することも多い。 また、売主が対象会社から借入金を有する場合、対象会社から売主に対して、特別報酬を支給したり、役員退職慰労金を支給したりして、それにより対象会社への借入金を返済することとし、実質的に借金を棚上げし、その分、株式譲渡代金を調整することも多い。 |
⇒M&Aトラブル・表明保証違反・コベナンツ違反・M&Aの損害でお困りの方はこちら! 役員の処遇■■■第12条■■■■■■■■■■第12条 (役員の処遇及び役員の選任)1. 売主は、クロージング日をもって、_____氏をして、対象会社の代表取締役及び取締役を辞任させるものとし、_____氏及び_____氏をして、対象会社の取締役を辞任させるものとし、_____氏をして、対象会社の監査役を辞任させるものとする。 2. 買主は、対象会社をして、_____氏に対して、退職に伴い、役員退職慰労金として、金____万円を支給させるものとする。 2. 対象会社は、_____氏をして、辞任後も、買主が本件事業を円滑に遂行することができるよう、買主が要請する事項につき、合理的な協力をさせるものとする。 3. _____氏以外の対象会社役員は、クロージング日以降も、当面は、同日以前と同様の役職及び処遇(報酬水準及び役員退職慰労金の水準を含む)にて、引き続き役員に在任するものとする。 |
第12条 解説第12条は、役員の処遇に関する遵守条項である。 (1) 事業承継M&A後の役員の在任及び退任事業承継M&Aが行われた場合、多くの場合は、対象会社の役員は全員辞任し、買主が対象会社に新役員を指名して派遣することとなる。 ただ、事業承継M&Aの対象会社である中小企業、零細企業においては、役員も業務運営のための重要なスタッフであることが多く、また、中小企業、零細企業においては、事業運営に関する「暗黙知」が多く、形式知になっていないものが多く、買主が対象会社に対して新役員を派遣したとしても、新役員は対象会社の事業を円滑に運営することはできないことが多い。 事業承継M&Aでは、オーナーである売主個人がそのまま代表取締役になっているケースが多く、また、その奥様やご子息が役員になっているケースも多く存在する。また、古参の経営幹部が役員になっているケースも多く存在する。事業承継M&Aでは、オーナーである売主は、対象会社の株式を売却し、引退をしたい意向であることが多いが、引き続き業務に携わりたいという売主も少なからずいる。また、オーナーである売主が役員を退任するのであれば、その奥様やご子息も役員を退任することは自然であるが、ご子息は引き続き役員として残りたいという言う項を示すこともある。 事業承継M&Aが行われる理由にはいろいろあり、後継者不在だけが理由ではない。事業の将来の展望が描けないとか厳しい業界環境に鑑み経営力のある買主に売却したいという理由であることも多く、そのような場合、ご子息は引き続き業務には関与したいという意向の場合もあるのである。 本条は、オーナーである売主は代表取締役を退任するものの、古参の経営幹部は引き続き対象会社の役員に残るというケースを想定している。勿論、その古参の経営幹部の意向次第なのであるが、買主としては、経営幹部が対象会社の役員として残るということは、業務の引継ぎを懸念する必要もなく、事業承継M&Aに伴う、対象会社の企業価値の毀損も大きくないと思われることから、好ましいことともいえる。 (2) 事業承継M&Aと事業の引継ぎと顧問契約また、オーナーである売主は代表取締役を退任するとしても、対象会社の業務の引継ぎに協力する義務が規定されることが一般的である。事業承継M&Aにおいては、対象会社はまさにオーナーである売主個人とイコールであることも多く、売主であるオーナーでなければ業務遂行することができないことも多く存在する。また、事業承継M&Aに伴い、突然、オーナーである売主が対象会社から居なくなってしまい、業務遂行にも関与しないということになれば、対象会社の事業運営の混乱は必至である。 また、対象会社の従業員の見地からも、オーナーである売主が対象会社からいなくなってしまうことは非常に大きなストレスとなる。中小企業、零細企業においては、従業員は、オーナーである売主が採用した従業員ばかりであると思われ、事業承継M&Aに伴い、対象会社からオーナーである売主が居なくなったら、これを契機に、退職する従業員が続出する可能性もあり、新オーナーである買主に忠誠心の低い従業員が、未払残業代の請求や不正行為を行うこともある。オーナーである売主が対象会社から居なくなってしまうと突然、従業員のモラールが低下し、効率的な業務運営が困難になる可能性もある。そのような場合、対象会社の企業価値は著ししく低下し、買主の想定する株式譲渡価格の前提が崩れてしまうのである。 そうであるからこそ、株式譲渡契約書では、通常、売主に対して、当面の間の、業務の引継ぎに協力する義務を規定することが多く、また、単に業務の引継ぎに協力する義務を規定するだけではなく、実際に、対象会社がオーナーである売主と顧問契約を締結し、当面の間、顧問として、対象会社から顧問料を支払いつつ、業務の引継ぎに協力をしてもらうこととするケースも多く存在する。 すなわち、オーナーである売主が、事業承継M&Aに伴い、対象会社の役員を退任した後、無償で業務の引継ぎに協力して頂けるとはなかなか思えない。オーナーである売主は、事業承継M&Aを行って引退したかったのである。買主としては、オーナーである売主と顧問契約を締結して、顧問料を払ってでも、なんとか売主から買主への業務の引継ぎを円滑に行いたいと考えることが多い。すなわち、買主としては、業務の引継ぎが円滑に行えず、対象会社の企業価値を毀損してしまっては、買主の想定する株式譲渡価格の前提が崩れてしまうため、このような方法により対象会社の企業価値の維持を図るのである。 (3) 事業承継M&Aと一般役員の処遇また、第3項は、その他の一般の役員の処遇について規定している。 事業承継M&Aにおいて、その他の役員が在任を希望している場合、売主からその役員の在任の継続の申し入れがある場合があるし、買主としても、明らかに不要な役員であればともかく、そうでないのであれば、事業の円滑な引継ぎのために、在任を継続して頂いたほうが、対象会社の企業価値を毀損する可能性は低くなる。 売主としても、事業承継M&Aの後、対象会社に残される役職員のその後については、非常に気になる事項である。売主としても、事業承継M&Aという自分の勝手で、その後、対象会社に残される役職員が幸せになったのか不幸になってしまったのかは心残りなのであることが多い。売主としては、対象会社に残された役職員には幸せになって欲しいものである。そのため、売主からは、買主に対して、対象会社に残された役員の役員報酬や役員退職慰労金の水準についても、当面は、少なくとも現状維持して欲しいという希望が強く出されることが多い。対象会社の業績により役員報酬や役員退職慰労金は変動してしかるべきものであることから、対象会社に残された役員の役員報酬や役員退職慰労金の水準について、永久に保証してほしいとは考えないまでも、当面は、維持してほしいと考えるのである。 買主としてもそこまで言われたら受けざるを得ない。ただ、その役員が不祥事を起こした場合などはそうはいかないため、役員報酬や役員退職慰労金の保証は全面的には受け入れられない。また、その役員の待遇を未来永劫維持することは自然ではありませんし不合理であり、また、経営環境が変わったのなら役員の待遇も変わらざるを得ない状況ともいえる。そのため、役員が在任を継続する期間については、当面とすることが多く、また、待遇の維持についても当面としつつ、不祥事や懲戒事由が発生しない限りとか、善管注意義務違反のない限りとか、経営環境に変動のない限りとか、例外事由を規定することもある。 ただ、役員というものは、オーナーから経営責任を問われるべき立場なので、従業員と比較してこのような身分保障が規定されることは多くはないように思われる。対象会社の旧役員としても、新オーナーの下で、引き続き、役員を継続したいかどうかは明らかではない。 (4) 一般役員の在任と退任ただ、対象会社の旧役員としては、事業承継M&Aの後も、役員として在任を継続するのであれば、役員報酬や役員退職慰労金などの水準その他の条件を維持してもらうことは前提であることが多く、そのためにも、株式譲渡契約書には、本条のような、対象会社に残された役員の役員報酬や役員退職慰労金の水準の維持に関する規定が規定されることが多い。 また、株式譲渡契約書の当事者には役員は含まれないことが一般的であり、株式譲渡契約書に第3項のような規定を規定したとしても、役員個人には、在任を継続する義務もなく、事業承継M&Aが行われた後に直ちに退任してしまうことも可能である。さらに、株式譲渡契約書の当事者に役員が含まれていたとしても、役員にも、憲法で保障された職業選択の自由があるため、役員個人に対する在任を継続する義務は限定的に解釈されることとなり、事業承継M&Aが行われたのち直ちに役員退任してしまっても、その役員個人の責任追及をすることは困難なことも多い。 ところで、筆者らに相談が多い事例としては、事業承継M&Aに伴い、オーナーが変更になるが、新オーナーの下、自分の役員としての身分や待遇は継続されるのか、悪化してしまわないか、というものがある。 株式譲渡契約書には、通常、この第12条のような規定が盛り込まれることが多いことから、オーナー(売主)に対して、そのような規定が盛り込まれているか、買主から役員に対して直接そのような身分や待遇を保証する誓約書のようなものを差し入れてもらえないかと、申し入れてみてはどうかアドバイスすることや、事業承継M&Aに伴って、クロージング後の役員としての在任の継続を条件に、売主と交渉し、売主に対して、買主から、対象会社の役員に対して、身分や待遇を保証する誓約書のようなものを差し入れることを申し入れるなどすることもある。 (5) キーマン(重要な役員)についてなお、買主が売主に対して、特定の役員について、在任させる義務を課すことは可能であるが、第3項は、売主の義務として規定されているものに過ぎず、役員に対して、直接、義務を負わせるものではないため、役員が第3項に違反して退任してしまっても、売主の責任追及をすることはできない。 他方、事業承継M&Aが行われたのち直ちに役員が退任してしまう結果、対象会社の企業価値が毀損されることはあると思われるが、対象会社の企業価値が毀損されることが可及的に防ぐため、株式譲渡契約書に、いわゆるキーマン条項(特定の重要な役職員が当面対象会社を退任・退職しないことや退任・退職させないことを規定する条項)を規定することにより、事業承継M&Aが行われたのち直ちに役員が退任してしまった場合、売主に対して、表明保証違反に基づく損害賠償責任・補償責任ができるようにすることが可能である。 従業員の処遇■■■第13条■■■■■■■■■■第13条 (従業員の処遇)買主は、クロージング日における対象会社の全従業員(嘱託を含むものとする。以下「対象会社従業員」と総称する)の雇用を、当面、維持するものとする。また、買主は、対象会社従業員の処遇(給与水準及び退職金の水準を含む)について、懲戒事由が無い限り、当面は、不利益に変更しないものとする。 |
第13条 解説第13条は、従業員の処遇に関する遵守条項である。 (1) 事業承継M&Aと従業員の処遇について売主としては、事業承継M&A後の従業員については、非常に気懸りである。すなわち、売主の勝手により、事業承継M&Aによって、従業員を含む対象会社が他人に売却されてしまうのである。売主としては、そのような従業員から恨まれないか心配をする者が多い。また、事業承継M&Aにおいて、売主にとって、従業員は、それまで一緒に会社の経営で苦楽を共にしてきた仲間である。売主としては、そのような従業員の今後を見届けたいという思いと、事業承継M&Aにより買主の従業員となった後も従業員には幸せになってもらいたいと願う思いが強いのである。 そこで、売主としては、M&Aの後、買主に対して、株式譲渡契約書に、対象会社の従業員の処遇を保証する旨の規定を、盛り込むことを要求することが多い。 ただ、買主としては、対象会社の従業員に対して、不当な仕打ちをする意図はなく、かつ、従業員の処遇についても、特段後退させようとする意図はないものの、もし対象会社の業績が悪化した場合などにおいてまで、対象会社の従業員の処遇を保証しなければいけないというのは困ると考えることが一般的である。また、買主としては、対象会社の従業員の処遇を保証するとしても、未来永劫、現状の処遇を保証するというわけにはゆかない。 そこで、株式譲渡契約書において、従業員の処遇を保証する規定がなされることが多いものの、その従業員の処遇の保証については、多くの場合は、期間制限がなされる。1年とされることもあれば、2年とされることもあれば、「当面」とされることもあり、おそらく、「当面」とされることが最も多いものと思われる。では、「当面」とは、何年程度のことを言うのかということが問題となるが、これは人により解釈は様々である。1年という人もいれば、2年という人もいれば、半年程度という人もいれば、3ヶ月程度という人もいる。 ただ、ここで重要なのは、従業員の処遇の保証について、明確に期限を設定しないことである。すなわち、従業員の処遇の保証について、2年との期間制限を設定した場合、買主は2年経過の翌日に従業員の処遇を大幅に悪化させることが可能となるのであるため、売主としては、明確に期限を設定することも心配でならない。勿論、「当面」という玉虫色の文言を使用されるのも心配でならないと思われるが、買主が、設定された期間の経過を根拠に、従業員の処遇を大幅に悪化させることを正当化することを避けることができるのではないかと思われる。 なお、従業員の処遇の保証の期間について、「当面」と設定された場合は、当事者の合理的意思としては、従業員の処遇の大幅な変更のためにはそれなりの期間が必要であり、小規模な変更であればそれほど期間は必要がないなど、経済合理的に解釈すべきであると思われる。 (2) 事業承継M&Aと従業員の処遇の変更についてその他、そもそも、日本の労働法制下において、従業員を解雇したり処遇を大幅に変更したりすることは非常に難しい。日本の労働法制下において、従業員を解雇したり処遇を大幅に変更したりできる場合は、それなりの理由がある場合であり、そのような場合は、買主としては、従業員の処遇の保証を継続できない事由が存在する場合であり、そのような事由が存在するのであれば、従業員の解雇や処遇の大幅な変更が認められてしかるべきである。 したがって、第13条では、従業員に就業規則規定の懲戒事由に該当するような行為が認められる場合は、従業員の解雇や処遇の変更を認める例外を規定している。 ところで、筆者らに実際に相談の多いケースでは、事業承継M&Aに伴い、オーナーが変更になるが、新オーナーの下、自分の雇用や待遇は継続されるのか、悪化してしまわないか、というものがある。筆者らとしては、株式譲渡契約書には、通用、この第13条のような規定が盛り込まれることが多いことから、オーナー(売主)に対して、そのような規定が盛り込まれているか、従業員に対して直接そのような待遇を保証する誓約書のようなものを差し入れてもらえないかと、申し入れてみてはどうかアドバイスすることや、事業承継M&Aに伴って、未払残業代の存否を確認することや、労働時間管理の不正確性などを根拠に、売主と交渉し、売主に対して、買主から、対象会社の従業員に対して、待遇を保証する誓約書のようなものを差し入れることを申し入れるなどすることもある。 |
⇒M&A契約書の作成・チェックの弁護士費用はこちら! 役員の選解任と退職慰労金■■■第14条■■■■■■■■■■第14条 (臨時株主総会開催)売主は、クロージング日に対象会社をして、以下の決議事項を株主総会の目的事項とする臨時株主総会を開催せしめ、当該事項について決議せしめるものとする。 (1) 買主が指名する対象会社の新取締役及び新監査役の選任 (2) ____氏に対する役員退職慰労金の支給 第14条 解説第14条は、新役員の選任等に関する遵守条項である。 新役員の選任等に関する遵守条項について事業承継M&Aにおいて、対象会社は、クロージング日におけるクロージングをもって、売主の所有から買主の所有に移るわけであるから、買主としては、クロージング日に、対象会社に対して、新役員を派遣することとなることが多い。 そこで、買主としては、クロージング日のクロージング終了後、対象会社に臨時株主総会を開催させて、新役員を選任させる必要がある。また、買主は、クロージング日に、対象会社に臨時株主総会を開催させて、新役員を選任した後、対象会社に取締役会を開催させて、新代表取締役を選任することとなる。 新役員の選任等の必要性理論的には、株式譲渡のクロージング日におけるクロージングが終了したばかりの段階では、対象会社の役員には、旧役員がそのまま在任していることとなる。また、株式譲渡契約書において、対象会社の旧役員は、クロージング後退任するものとされていたとしても、クロージング後に開催される株主総会の終了をもって退任とされることが一般的であるため、旧役員は、株式譲渡のクロージング後においても、しばらく役員として在任していることとなるのである。 また、会社法346条[1]上、役員は、定款上の定足数を欠くこととなる場合は、退任したとしても、新役員等が就任するまで、権利義務取締役として、役員としての権利及び義務を負うものとされているため、株式譲渡において、旧役員が辞任したとしても、引き続き役員としての責任を負ってしまうこととなることが多く、株式譲渡においては、クロージング後、速やかに、新役員を選任する必要があるのである。 また、会社法296条[2]3項上、株主総会の招集や開催は、取締役の権限とされており、株式譲渡のクロージング後、旧役員が辞任して対象会社に協力しないような場合、理論的には、対象会社の株主総会を招集・開催することができなくなり、新役員の選任もできなくなるという関係にある。この点、売主としては、株式譲渡のクロージングが完了し、買主が対象会社のオーナーになったのだから、買主が株主総会を招集・開催してほしいと考えることも多いが、そうはいかないのである。 このような理由もあり、株式譲渡のクロージング後の円滑な株主総会の招集・開催及び新役員の選任のため、株式譲渡契約書において、売主の義務として、対象会社に臨時株主総会を開催させる義務を規定することが必要なのである。 クロージング前の新役員の選任等また、売主としては、対象会社の株主総会を招集・開催して、新役員を選任する必要があるのであれば、株式譲渡のクロージング前に行えばよいと考えることもある。 ただ、その場合、株式譲渡のクロージング時における役員は新役員ということとなり、売主が所有する対象会社の株式譲渡のクロージングを、買主が派遣する新役員が行うこととなり、売主のガバナンスの問題が生ずることや、新役員としても他人の会社である売主から、対象会社のクロージングの実務を任されたとしても、責任は持てないであろう。また、新役員は、役員就任からクロージングまでの間、売主が所有する対象会社において、何らかの経営問題が発生した場合、経営責任を負うこととなるが、他人の会社の経営責任を新役員が負うことには抵抗があることが多いと思われる。 また、新役員とともに、クロージングまでは旧役員も在任し、クロージングとともに旧役員が辞任するということも考えられなくはないものの、この場合も、上記の他人(売主)の所有する会社の経営責任を、買主が派遣した新役員が負うことになってしまう。 株式譲渡方式における退職慰労金の支給と税効果また、本条では、第2号において、旧役員に対して、退職慰労金の支給を決議することが規定されている。 この退職慰労金の支給の対象となる旧役員は、オーナーである売主個人の場合も多い。 事業承継M&Aにおいて、株式譲渡代金を、実質的に、株式譲渡代金と役員退職慰労金の2つに分けて支給することはよく行われる。 売主と買主としては、対象会社の株式価値について、特定の額(例えば5億円)と決めたとしても、売主がその5億円をどのように受け取るかによって、売主の株式譲渡代金の手取額が大きく異なるのである。 買主としては、株式譲渡代金が5億円と決まったからには、いずれにしろいずれかの形で5億円を支払わけなればいけないのであり、比較的関心は薄いものの、売主としては、適用される税制により税金が大きく異なり、その結果、手取り額が大きく異なるため、非常に関心の濃い分野である。 株式譲渡代金については、ご存知の通り、適用される税制としては、譲渡所得として株式譲渡益課税であり、税率は株式譲渡益の20%(プラス復興特別税)であり、課税としてはそれ自体低い部類に入るが、退職慰労金については、退職所得となるため、退職金控除が存在し、一定以下の役員退職慰労金には所得税が発生しない。 また、退職所得では、退職金というものはその者がその後その資金で生活してゆかなければならないということで税制が優遇されており、控除後の金額の2分の1の額のみが課税所得とされるため、税金が少なくなることが多い。ただ、総合課税であることから、課税所得の合計額の多い人に対しては、累進課税により高い税率が適用されるため、課税所得の合計額が多い場合は、最終的には、譲渡所得よりも課税負担が重くなることがある。 売主としては、この2つの税制のはざまで、対象会社の株式価値を、株式譲渡代金と役員退職慰労金の2つにどの程度ずつ配分して、事業承継M&Aに伴って湯量することが、最も課税負担が少なくなるのかを考えるのであるが、これについては、よくよく検討する必要があるのである。 また、買主としても、買主から売主に対して株式譲渡代金を支払うのであれば、対象会社の株式価値分の出費がそのまま生ずるものの、対象会社の株式価値の一部を、対象会社から売主に対して退職慰労金として支払うのであれば、対象会社の手持ち資金で賄うことができるのであり、買主の資金を使用することなく事業承継M&Aを実行することができるのであり、半面、売主についても、対象会社において損金処理をすることができ、クロージング後の対象会社の税務負担の軽減につながるため、無関心ではいられない。 株式譲渡方式におけるその他の支払いの税効果その他にも、事業承継M&Aに伴い、売主に対して、対象会社の株式価値を、株式譲渡代金と配当金の2つに分けて支払う場合もある。特に、売主が法人の場合、対象会社からの配当金の支払いが、受取配当金の益金不算入になることから、対象会社から法人である売主に対して配当金が支払われたとしても、売主においては、益金とはされず、課税対象にもならない。 また、対象会社が売主から自己株式取得を行うことにより、法人である売主に対して、自己株式取得代金を支払う場合、売主の株式の譲渡益は、配当とみなされ、配当金と同様、益金不算入になることから、対象会社の株式価値を、株式譲渡代金と、自己株式取得代金の2つに分けて支払うスキームもしばしば採用される。 なお、配当金の支払いも自己株式取得も、会社法上の資本規制があるため、また対象会社の資金繰りの問題にも直結するため、無制約に行うことはできない点に留意が必要である。 その他にも、対象会社の株式価値を、株式譲渡代金と商標買取代金の2つに分けて支払う場合や、株式譲渡代金と不動産譲渡代金の2つに分けて払う場合など、いろいろなスキームが存在する。いずれも、実質的に、買主から売主に対する株式譲渡代金の支払いを、異なる支払いに変更することによって、適用される税制を変更し、税負担の最小化を狙っているのである。 事業譲渡M&Aと一般役員に対する役員退職慰労金の支給また、本条では、第2号において、旧役員に対して、役員退職慰労金の支給を決議することが規定されている。この場合の旧役員は、オーナーである売主個人であることもあれば、一般役員であることもあろう。 このような場合、通常は、旧役員に対して役員退職慰労金を支給することにより、対象会社の企業価値が減少するため、株式譲渡代金をその分減額調整することがあり得る。 [1] 会社法346条(役員等に欠員を生じた場合の措置)1 役員(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役若しくはそれ以外の取締役又は会計参与。以下この条において同じ。)が欠けた場合又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員(次項の一時役員の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。 2 以下略 [2] 会社法296条(株主総会の招集)定時株主総会は、毎事業年度の終了後一定の時期に招集しなければならない。 2 株主総会は、必要がある場合には、いつでも、招集することができる。 3 株主総会は、次条第四項の規定により招集する場合を除き、取締役が招集する。 |
⇒M&A契約書の作成・チェックの弁護士費用はこちら! 役員の免責■■■第15条■■■■■■■■■■第15条 (役員の免責)買主は、株主としての権利行使その他方法の如何を問わず、対象会社の役員による対象会社の役員としての一切の作為又は不作為に関し、当該役員に対して何らの責任も追及してはならず、損害賠償請求権その他の権利を放棄するものとし、かつ、対象会社その他の第三者をしてかかる責任の追及をなさしめてはならなず、損害賠償請求権その他の権利を放棄させるものとする。 |
第15条 解説第15条は、対象会社の役員の免責に関する遵守条項である。 役員の免責に関する遵守条項について事業承継M&Aにおいては、通常、対象会社のオーナー経営者は売主であり対象会社の社長である。 戦後まもなく創業し、そのまま会社を経営している場合もあれば、高度成長時代に会社を相続し、長期間、対象会社を経営してきたオーナー経営者が多く存在する。 昭和というのは平成に比べればかなりおおらかな時代であったようで、会社のガバナンスもしっかりしていないし、おおざっぱな事業運営をしていても何とかなった時代のようである。もちろん、オーナー経営者は、当然のように、社長として、会社資産を流用などをしていた。対象会社のオーナー経営者なのであるから、会社資産を流用などをしても問題ないのであるが、少数株主などが存在していた場合、問題が残るのである。 すなわち、会社の役員が善管注意義務違反を行った場合、会社に対して損害賠償責任を負う(会社法423条[1])が、株主全員の同意があれば免責されるものとされており(会社法424条[2])、オーナー経営者は対象会社株主であることから免責されてしかるべきあるが、少数株主が存在した場合などは、制度上、免責されないこととなる。会社法425条から427条まで株主総会による免責、定款の責任免除条項による免責、責任限定契約による免責などの規定が存在するが、これらは、特に、会社との利益相反取引には適用がない(会社法428条[3])。 旧オーナー経営者である売主としては、事業承継M&Aを迫られ、事業承継M&Aの結果、対象会社を買主に売却し、買主が対象会社のオーナーとなり、対象会社から、旧オーナー経営者である売主に対いて、善管注意義務違反などの経営責任を追及される可能性があるのでは、安心して事業承継M&Aを実行できない。また、旧オーナー経営者としては、買主の希望に応じて対象会社を売却したにも拘わらず、また、その買主が何ら損失を被っていないにも拘らず、責任追及されるということになっては、何のために対象会社を売却したのか分からない事態を招くこととなる。旧オーナー経営者としては、過去の会社資産の流用などを理由に、対象会社から責任追及される可能性があるのであれば、対象会社の売却を取り止めようとするのはごく自然である。 したがって、売主としては、買主に対して、対象会社の役員の免責に関する遵守条項を遵守して頂く必要があるのである。 事業承継M&Aの失敗と旧役員の責任の追及買主としては、対象会社に対して、デューデリジェンス(DD)を実施して、事業承継M&Aを実行しているはずである。いまどきデューデリジェンス(DD)を実施せずに事業承継M&Aを実行したため、対象会社の問題点に気づかなかったなどという言い訳は通らない。買主は、対象会社のデューデリジェンス(DD)を実施して対象会社を買収したのであり、旧オーナー経営者の会社資産の流用などは前提としたうえで、対象会社を買収しているのであり、また、対象会社の現在の決算書をベースに対象会社を買収しているのであるから、粉飾決算などがない限りは、買主の想定した対象会社の企業価値(旧オーナー経営者の会社資産の流用を前提)が毀損されることはなく、買主の株式譲渡価格の前提を崩すような事態は生じない。 筆者らに実際に相談のあったケースでは、旧オーナー経営者が対象会社と取引を行っていることも多く、そのような取引は、会社法356条[4]上の利益相反取引に該当し、会社法424条上、株主の全員の同意がなければ免責されない。 買主としては、これを根拠に、株主の同意書がないため免責されていないとして、旧オーナー経営者の責任追及をしてくることもあり、また、ごく一部の少数株主の同意がないため免責されていないとして、旧オーナー経営者の役員の責任追及をしてくることもある。 特に、買主としては、事業承継M&Aを実行した結果、対象会社の業績が想定外であったとか、対象会社とのシナジーが想定外であったとか、事業承継M&Aが失敗であると感じた場合、とにかく、何につけても、理由をつけて、旧オーナー経営者である売主の責任を追及し、事業承継M&Aの失敗の損失を補填させようとして、これが使用されること多い。 特に、買主としても、対象会社に対して、デューデリジェンス(DD)を実施して、事業承継M&Aを実行しているはずである。いまどきデューデリジェンス(DD)を十分に実施せずに事業承継M&Aを実行したため、事業承継M&Aが失敗したため、旧オーナー経営者に対して損害賠償責任・補償責任をするなどということは困難なのであり、対象会社の現在の決算書をベースに対象会社を買収しているのであるから、株式譲渡価格の前提を崩すような事態は生じないため、経済的も、旧オーナー経営者に対して損害賠償責任・補償責任する理由もない。そこで、買主としては、事業承継M&Aに失敗した場合、自己責任であることを顧みることなく、旧オーナー経営者の役員の責任追及をしてくることが多いことから、売主としては、買主に対して、対象会社の役員の免責に関する遵守条項を遵守して頂く必要があるのである。 [1]会社法423条(役員等の株式会社に対する損害賠償責任)1 取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人(以下この節において「役員等」という。)は、その任務を怠ったときは、株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 2 取締役又は執行役が第三百五十六条第一項(第四百十九条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定に違反して第三百五十六条第一項第一号の取引をしたときは、当該取引によって取締役、執行役又は第三者が得た利益の額は、前項の損害の額と推定する。 3 第三百五十六条第一項第二号又は第三号(これらの規定を第四百十九条第二項において準用する場合を含む。)の取引によって株式会社に損害が生じたときは、次に掲げる取締役又は執行役は、その任務を怠ったものと推定する。 一 第三百五十六条第一項(第四百十九条第二項において準用する場合を含む。)の取締役又は執行役 二 株式会社が当該取引をすることを決定した取締役又は執行役 三 当該取引に関する取締役会の承認の決議に賛成した取締役(指名委員会等設置会社においては、当該取引が指名委員会等設置会社と取締役との間の取引又は指名委員会等設置会社と取締役との利益が相反する取引である場合に限る。) 4 前項の規定は、第三百五十六条第一項第二号又は第三号に掲げる場合において、同項の取締役(監査等委員であるものを除く。)が当該取引につき監査等委員会の承認を受けたときは、適用しない。 [2]会社法424条 (株式会社に対する損害賠償責任の免除)前条第一項の責任は、総株主の同意がなければ、免除することができない。 [3]会社法428条(取締役が自己のためにした取引に関する特則)1 第356条第1項第2号(第419条第2項において準用する場合を含む。)の取引(自己のためにした取引に限る。)をした取締役又は執行役の第423条第1項の責任は、任務を怠ったことが当該取締役又は執行役の責めに帰することができない事由によるものであることをもって免れることができない。 2 前3条の規定は、前項の責任については、適用しない。 [4]会社法356条(競業及び利益相反取引の制限)1 取締役は、次に掲げる場合には、株主総会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。 一 取締役が自己又は第三者のために株式会社の事業の部類に属する取引をしようとするとき。 二 取締役が自己又は第三者のために株式会社と取引をしようとするとき。 三 株式会社が取締役の債務を保証することその他取締役以外の者との間において株式会社と当該取締役との利益が相反する取引をしようとするとき。 2 民法第108条の規定は、前項の承認を受けた同項第二号の取引については、適用しない。 |
⇒M&Aトラブル・表明保証違反・コベナンツ違反・M&Aの損害でお困りの方はこちら! 商号の続用■■■第16条■■■■■■■■■■第16条 (商号の使用継続)買主は、クロージング日以降、当面の間、対象会社の商号を変更しないものとする。 |
第16条 解説第16条は、対象会社の商号の取り扱いに関する遵守条項である。 商号の取り扱いに関する遵守条項について事業承継M&Aでは、オーナー経営者である売主の会社の商号に対する拘りは強いことが多い。オーナー経営者自身で創業し、何十年も経営してきた会社であるからこそ、その通りだと思われる。 また、オーナー経営者は、事業承継M&Aで会社を売却することに対する「負い目」を持っていることも多い。会社を売却して自分だけ儲けて引退し、従業員や取引先を見捨てたと思われるのではないかと、周りの目を気にするのである。であるからこそ、実際は事業承継M&Aにより対象会社を売却したのであるが、これはM&Aではなく、業務提携であるとか、、大企業の傘下に入ったのだとか、スポンサーから外部資本を入れたのだとか、有力企業と経営統合したのだとか、M&Aや会社を売却したという表現は極力使いたくないということが多い。 そうであるからこそ、オーナー経営者としては、事業承継M&Aの後も、当面、対象会社の顧問として、会社に関与している形態を取りたいという希望も多く、また、対象会社において、事業承継M&A後も、当面、従前の商号を使用継続して欲しいとの希望が出てくることも多い。 他方、オーナー経営者が複数の会社を経営しており、グループで商号を使用している場合など、事業承継M&Aにより対象会社がそのグループを離脱した以上は、ごループの商号を使用して欲しくないということで、事業承継M&Aの後、対象会社に対して、速やかな商号変更を求めることも多い。 事業承継M&Aと商号続用責任また、事業承継M&Aを株式譲渡方式により行う場合は、特段問題は生じないものの、事業譲渡方式や会社分割方式により事業を売却する事業承継M&Aの場合、会社法上、商号続用責任(会社法22条[1]1項)が生ずることがあるため、特に注意が必要である。 すなわち、事業譲渡方式や会社分割方式に基づき事業の譲渡を受けた買主が、もともとの事業会社の商号を承継して使用する場合、新会社はもともとの事業会社の債務を負担する責任を負ってしまうのである。これは、買主が事業譲渡や会社分割とともに事業会社の商号を承継したことにより、買主を債務者であると認識した債権者を保護するための規定である。 すなわち、事業譲渡方式や会社分割方式での事業を売却する事業承継M&Aにおいては、事業会社から、買主に対して、経営の実態が移るのであるから、買主としては、事業の承継とともに、もともとの事業会社の商号の承継を希望することが多く、そのような場合、もともとの事業会社は商号変更し、資産管理会社のような全く別の商号に変更しつつ、買主がもともとの事業会社の商号を承継することも多い。 商号続用責任の適用範囲の拡大この商号続用責任であるが、全く同じ商号でなくとも類似商号であっても、商号ではなく名称であっても、商号続用責任(会社法22条1項)が類推適用され、商号続用責任類似の責任が発生してしまうことがあるため、事業承継M&Aに伴う、商号や名称の続用には、特に注意が必要となる。 会社法上は、事業譲渡方式の場合に、この商号続用責任が生ずるものとされているが、会社分割方式の場合にも、これが類推適用されると考えるのが一般的である。 商号続用責任と商号続用責任免責登記なお、商号続用責任(会社法22条1項)の免責登記(会社法22条2項)という制度も存在する。 商号続用責任(会社法22条1項)が生ずるような場合でああっても、商号続用責任の免責登記(会社法22条2項)を行うことにより、商号続用責任(会社法22条1項)が免責されるのである。 買主としては、会社分割又は事業譲渡後、速やかに、この商号続用責任の免責登記をしさえすれば、商号続用責任の免責が得られるわけであるから、事業譲渡方式や会社分割方式の事業承継M&Aの場合は、この商号続用責任の免責登記を行っておくべきものである。 この商号続用責任の免責登記も、会社法上は、事業譲渡の場合にのみ規定されているものの、会社分割の場合に行うことも可能であるし、必ずしも商号続用していない場合であっても、類似商号を使用しており懸念がある場合や名称を続用している場合、登記することが可能であることから、幅広く行っておくことが好ましい。 [1] 会社法22条(譲渡会社の商号を使用した譲受会社の責任等)1 事業を譲り受けた会社(以下この章において「譲受会社」という。)が譲渡会社の商号を引き続き使用する場合には、その譲受会社も、譲渡会社の事業によって生じた債務を弁済する責任を負う。 2 前項の規定は、事業を譲り受けた後、遅滞なく、譲受会社がその本店の所在地において譲渡会社の債務を弁済する責任を負わない旨を登記した場合には、適用しない。事業を譲り受けた後、遅滞なく、譲受会社及び譲渡会社から第三者に対しその旨の通知をした場合において、その通知を受けた第三者についても、同様とする。 3 譲受会社が第一項の規定により譲渡会社の債務を弁済する責任を負う場合には、譲渡会社の責任は、事業を譲渡した日後二年以内に請求又は請求の予告をしない債権者に対しては、その期間を経過した時に消滅する。 4 第一項に規定する場合において、譲渡会社の事業によって生じた債権について、譲受会社にした弁済は、弁済者が善意でかつ重大な過失がないときは、その効力を有する。 |
⇒M&Aトラブル・表明保証違反・コベナンツ違反・M&Aの損害を解決する方法を見る! 経営者保証の解消と抵当権の解除■■■第17条■■■■■■■■■■第17条 (保証債務の解消及び抵当権の解除)買主は、売主が対象会社の債務及び契約を担保するために負っている保証債務及び担保のため設定している抵当権について、買主の費用と責任において、当該保証債務の解消及び当該抵当権の解除のために必要な手続きを行うものとし、同手続きが完了するまでの間に、債権者から売主に対して保証責任の追及又は抵当権の実行がなされた場合には、売主に対して補償するものとする。 |
第17条 解説第17条は、保証債務の解消や抵当権の解除に関する遵守条項である。 事業承継M&Aと保証債務や抵当権の取り扱い事業承継M&Aにおいて、オーナー経営者は、対象会社の借入金などの債務を担保するために、自ら連帯保証を行っていることや、不動産に抵当権を設定するなど担保提供を行っていることが多い。 売主としては、売主から、買主に対して、事業承継M&Aにより、株式譲渡が実行され、買主が対象会社のオーナーとなった場合も、売主である旧オーナー経営者の連帯保証責任や抵当権が継続することは納得がゆかないであろう。 売主としては、事業承継M&Aを契機に、対象会社のオーナーではなくなることから、保証債務の解消や抵当権の解除をしてもらうことは当然である。 保証債務の解消や抵当権の解除には、多くの場合は金融機関である債権者の承諾が必要であることから、相手方のある話であり、売主が希望したとしても、必ずしも保証債務の解消や抵当権の解除が行われるわけではないが、通常、金融機関は、オーナーが変更になった場合、旧オーナー経営者の保証債務の解消や抵当権の解除について承諾するため、株式譲渡契約書においては、売主の義務として、保証債務の解消や抵当権の解除を規定することが一般的である。 保証債務の履行請求や抵当権実行があった場合の取り扱い事業承継M&Aでオーナー経営者が変更になった場合、多くのケースでは、金融機関の保証債務の解消や抵当権の解除に対する承諾は、クロージング後、1-2か月程度で取得できているようである。 稀に、クロージング後、金融機関に対して、保証債務の解消や抵当権の解除を申し入れたとしても、金融機関がこれについてなかなか承諾しなかったり、この承諾の取得に時間がかかったりすることがある。 ただ、その間においても、売主は対象会社を売却済みであり、買主が対象会社のオーナーになっているのであり、対象会社の債務については、最終的には、売主ではなく買主が責任を持つことが経済合理的である。したがって、クロージング後、金融機関から保証債務の解消や抵当権の解除が得られるまでの間に、売主に対して、保証債務の実行がなされたり、売主の資産に対して、抵当権の実行が行われたりして、売主が損害を被った場合、買主がこの損失補償をするという約定がなされることが一般的である。 |
⇒M&A契約書の作成・チェックの弁護士費用はこちら! 競業避止義務■■■第18条■■■■■■■■■■第18条 (競業避止義務)1. 売主は、買主が事前に承諾した場合及び対象会社にて職務を遂行する場合を除き、対象会社が現在営んでいる事業又はこれに類似する事業を、その関与形態を問わず、直接又は間接に行ってはならない。 2. 売主は、その形態を問わず、直接又は間接、対象会社の従業員に対して、その他の従業員等となることを勧誘してはならない。 |
第18条 解説第18条は、競業避止義務に関する遵守条項である。 競業避止義務に関する遵守条項の必要性事業承継M&Aの対象会社は中小企業、零細企業であり、その事業運営に関する主たるノウハウやネットワークは、オーナー経営者である売主個人に帰属していることが多い。 また、買主は、事業承継M&Aに伴い、クロージングに際して、旧オーナー経営者から、事業運営に関するノウハウやネットワークの引き継ぎを受けるものであるものの、仮に、旧オーナー経営者が、事業承継M&Aのクロージング後、対象会社の事業と同じ事業を立ち上げた場合、対象会社の強力な競争相手となるのみならず、重要なノウハウやネットワークなどは旧オーナー経営者に帰属していることから、旧オーナー経営者のほうに行ってしまうことも多いであろう。 また、旧オーナー経営者が対象会社の事業と同じ事業を立ち上げた場合や、立ち上げることを考えていた場合、買主は、旧オーナー経営者から、対象会社の事業運営について、十分な引き継ぎを受けることは期待できず、対象会社の企業価値は大きく毀損し、買主の想定する株式譲渡価格の前提が崩れるのである。 そこで、事業承継M&Aにおける株式譲渡契約書においては、旧オーナー経営者の競業避止義務を規定することが一般的である。 競業行為の形態の多様性また、このような旧オーナー経営者の競業行為は、いろいろな形態で行われる可能性があるため、あらゆる場合を想定した記載をしておかなければならない。 典型的には、競業行為をする者が、自ら又は会社を設立して、対象会社の事業と同じ事業を行うが、そのような明らかな競業行為をする者は多くはない。 まず、競業行為をする者が、自ら前面に出て競業行為をするのではなく、他の者に競業行為をさせ、裏から操ったり、ライバル企業を支援したり、対象会社の事業と全く同じ事業は行わないものの、非常に類似した事業を行うなど、さまざまである。 やはり、旧オーナー経営者が競業行為を行う場合は、外部に協力者がいる場合が多く、それは、対象会社のライバル企業や、取引先や、下請け先などであることが多い、そのような会社が、対象会社の収益性の高さに嫉妬し、事業承継M&Aが行われた機会に、対象会社のノウハウやネットがワークを流用し、対象会社の損失を厭わず、対象会社の事業と同じ事業を開始するのである。 そのような場合、オーナー経営者としては、対象会社の事業の重要なノウハウや顧客情報などを持ち出し、また、対象会社における重要な技術情報などを抹消し、対象会社の企業価値を積極的に毀損するとともに、ライバル企業に利益を供与するのである。オーナー経営者が、対象会社を退職後、ライセンサーに転職し、ライセンス契約を解除して、対象会社の事業と同じ事業を開始することなどもある。 引き抜き禁止規定の必要性また、このような競業行為は、オーナー経営者が対象会社の従業員を引き抜いて行われることも多い。 すなわち、オーナー経営者は高齢でありかつ一人で事業を運営することもできない。また、ライバル企業に対する手土産として、対象会社の従業員を引き抜くのである。多くのケースでは、対象会社の従業員が、ライバル企業に採用され、競業行為の最前線に立つのである。 そこで、本条2項の従業員の勧誘禁止条項が必要になるのである。 なお、対象会社から引き抜かれた従業員が、ライバル企業に採用され、競業行為の最前線に立つことが多いものの、その背後で糸を引いているのは、オーナー経営者であり、そのオーナー経営者と友人関係にあるライバル企業などの関係先企業であることが多い。 競業避止義務の期間についてまた、これらの競業避止義務については、期間制限を入れることもあれば、入れないこともある。期間制限を入れるとしても、その期間は、そのオーナー経営者が、改めて対象会社の事業と同じ事業に参入したとしても、対象会社の企業価値が毀損しない程度に、長期間の競業避止義務を設定する必要がある。 また、オーナー経営者が、競業避止義務に期間制限を入れることを要望してきた場合は、注意が必要である。 確かに、オーナー経営者にも職業選択の自由はあるものの、職業選択の事由があるからといったような抽象的な理由で、競業避止義務に期間制限を設定することを希望することはない。競業避止義務に期間制限を設定することを希望する以上は、その事業に参入する具体的な可能性があるということである。買主としては、オーナー経営者が、対象会社の事業と同じ事業に参入することについて、事前に承諾することなどできない。 この競業避止義務には、買主の承諾がある場合を除外事由としているのであるから、オーナー経営者が、将来、対象会社の事業と同じ事業に参入するのであれば、それは、買主が、その都度、その競業行為について問題ないかを確認することができるよう、都度、買主に申請して頂いて、買主において承諾か否かを検討することができるようにしておくことが好ましい。 |
⇒M&Aトラブルでお困りの方はこちら! 秘密保持義務■■■第19条■■■■■■■■■■第19条 (秘密保持義務)1. 売主及び買主は、①本契約の交渉過程に関する情報、②買収監査の過程に関する情報、及び③本契約の当事者に関する情報、又は④対象会社に関する情報を、__氏が対象会社の代表取締役及び顧問を退任した後3年が経過するまでの間、自ら依頼した弁護士、司法書士、監査法人、公認会計士、税理士、フィナンシャルアドバイザー等の本条と同等の秘密保持義務を負担する外部専門家以外の第三者に開示してはならない。ただし、次の各号に定める情報については、この限りではない。 (1) 情報開示者から提供を受けた時点において既に保有していた情報 (2) 情報開示者から提供を受けた時点において既に公知となっていた情報 (3) 正当な権利を有する情報開示者以外の第三者から守秘義務を負うことなく合法的に取得した情報 (4) 法令により開示が義務付けられた情報 (5) 行政機関、司法機関又は証券取引所から開示を要請された情報 (6) 第三者に開示することについてその都度文書により情報開示者の承諾を得た情報 2. 前項の規定にかかわらず、クロージング日以降は、対象会社に関する情報は承継会社の保有する情報とみなされ、売主は、秘密保持義務を負担するとともに、買主は、秘密保持義務を解除される。 3. 本条における義務は、解除・失効等の原因の如何を問わず、本契約の効力が失われた後も有効に存続する。 |
第19条 解説第19条は、秘密保持義務に関する遵守条項である。 事業承継M&Aと秘密保持の重要性事業承継M&Aにおいては、M&Aが成立する前に、事業承継M&Aの情報が流出することで大きな問題が生ずることが多い。 すなわち、事業承継M&Aの情報が流出し、対象会社の従業員が知ることになった場合、対象会社の従業員は、買主が対象会社のオーナーになった後を恐れて、一致団結し、対象会社の経営陣と交渉し、事業承継M&Aを取り止めるよう働きかける可能性も高い。特に、医療法人や介護事業会社など、人手不足の業界で、かつ、健康保険の点数が在籍している看護師の人数により変動してくるような従業員の重要性が高い業種や、そうでなくても、建設事業会社やサロン事業会社においても、従業員が、事前に、事業承継M&Aの動きを察知し、事業承継M&Aの阻止に動くことはままあり、そのような場合、事業承継M&Aを否応なく中止せざるを得ないこともある。 また、従業員が、買主はハゲタカ企業だと考え、事業承継M&Aが実行された場合、従業員は大量に解雇されるらしいとの噂がまことしやかに流れ、今後の雇用の継続に不安を持ち、次々と退職することも生ずることがある。 特に、医療法人や介護施設など、従業員の資格により、許認可や保険の点数が変動するような事業を行っている場合、対象会社の従業員が退職してしまうことによる企業価値の毀損は著しく、そういう企業でなくても、今日の人手不足の時代において、建設業や運送業など労働集約的な事業を運営している会社においては、従業員が大量に退職してしまうことは企業価値を著しく毀損する。 また、従業員がライバル企業やユニオン(合同労組)などに相談する結果、ライバル企業やユニオン(合同労組)などに対象会社の秘密情報が漏れ、ライバル企業やユニオン(合同労組)などが従業員をけしかけ、事業承継M&Aを拒否したり、ユニオン(合同労組)の介入を招き、ユニオン(合同労組)が対象会社の経営陣と団体交渉を要求し、事業承継M&Aを断念させるのみならず、事実上、対象会社の経営陣を追放し、ユニオン(合同労組)が対象会社を事実上支配してしまった事例も存在する。 そのライバル企業としても、これを好機とし、対象会社の従業員を引き抜きにかかったり、取引先の不安をあおり、取引先を対象会社から剥がそうとすることも多い。 特に、従業員が、事業承継M&Aの動きを察知し、ユニオン(合同労組)などの企業に敵対する労働組合に駆け込み、ユニオン(合同労組)などを会社に導き入れ、事実上、これらに会社を支配させたり、ユニオン(合同労組)とともに従業員が会社を支配し、経営陣を追い出し、事業承継M&Aが頓挫することも、しばしば生じている。 そうでなくても、事業承継M&Aの情報が流出することにより、取引先や金融機関などとしては、対象会社の経営悪化による身売りかと勘繰ることもあり、対象会社は、取引先や金融機関などとの取引の継続に関連し、痛くもない腹を探られることとなる。その結果、取引先や下請先なども対象会社の経営に不安を持つなどして取引を停止したり、事業に協力しなくなるなど、対象会社の企業価値を毀損することとなる。 そうであるからこそ、事業承継M&Aにおいては、売主と買主は、事業承継M&Aの検討に入る時点で、秘密保持契約書を締結することが一般的である。 秘密保持契約書と株式譲渡契約書この点、事業承継M&Aにおいて、案件検討段階において、すでに秘密保持契約書を締結している場合、株式譲渡契約書において、改めて、秘密保持義務を規定する必要はないとも思われがちである。 実際に、株式譲渡契約書に規定される秘密保持義務よりも、秘密保持契約書に規定される秘密保持義務のほうが、一般的に、規定が充実しており、秘密情報の返還義務・廃棄義務や、再委託者に対する秘密保持義務賦課義務、秘密保持義務違反時の損害賠償条項など、秘密保持義務が網羅的に規定されていることが多い。 ただ、事業承継M&Aにおいては、必ずしも、売主と買主が、直接、秘密保持契約書を締結するのではなく、売主側M&A仲介業者と買主側M&A仲介業者が従前より秘密保持契約書を締結しているところに、売主と売主側M&A仲介業者及び買主と買主側M&A仲介業者が、それぞれ秘密保持契約書を締結することで、売主から買主まで秘密保持義務を連続させ、実質的に、売主と買主が秘密保持契約書を締結しているのと同様の状態にすることも多い。 また、株式譲渡契約書には、株式譲渡に関連する合意内容は株式譲渡契約書自体に規定されているものが全てであり、その他の合意は失効する旨を定めた完全合意条項が規定されていることが多く、当事者間において株式譲渡契約書以前に合意がされた秘密保持契約書については、完全合意条項により効力が失効させられることも多く存在する。 そのような場合、株式譲渡契約書においては、秘密保持義務が改めて規定することが必要である。 秘密保持義務の秘密情報の範囲及び秘密保持義務者の範囲また、秘密保持義務の対象である秘密情報の範囲については、売主と買主の株式譲渡の当事者に関する情報のみならず、株式譲渡に関する交渉過程全般に関する情報、及び、買収監査の過程全般に関する情報、さらには対象会社に関する情報も含み、すなわち、事業承継M&Aに関する過程において取り扱われた全ての情報が対象となるべきものである。 ただし、当事者といえども、事業承継M&Aについて、弁護士やフィナンシャルアドバイザーなどの専門家には情報を開示して相談する必要があることから、そのような専門家については秘密保持義務の対象外となっている。 この第19条においては、秘密保持義務の規定は簡潔なものとなっているが、フィナンシャルアドバイザーといっても、自称アドバイザーのような業者も非常に多く、弁護士、司法書士、監査法人、公認会計士、税理士とは異なり、法令上の秘密保持義務を負っていないフィナンシャルアドバイザーを、すべてこの第19条で秘密保持義務の対象から外すことは行きすぎかもしれない。したがって、秘密保持義務の対象から外すフィナンシャルアドバイザーなどに対しては、第19条と同等の秘密保持義務を賦課することを前提に開示可能とする規定も多い。 また、売主や買主の親会社やグループ会社などを、秘密保持義務の対象から外すことも多く行われる。親会社やグループ会社などを、秘密保持義務の対象から外さない場合、その都度、相手方の承諾を取得する必要が生じてしまうため、実務的ではない。 また、この第19条においては、当事者がすでに保有していた情報や公知であった情報、さらには当事者が第三者から適法に入手した情報などは、秘密保持義務の対象から外しているが、これも秘密保持義務としては一般的である。 事業承継M&Aのクロージング後の秘密保持義務また、秘密保持契約書は、主として、売主が買主に対して売主や対象会社の情報を開示する場合の秘密保持義務を規定するものであり、事業承継M&Aがクロージングした後のことまではあまり想定していないことが多い。 売主としては、対象会社を買主に売却した以上、対象会社とは特段の利害関係はなくなるものの、売主は対象会社の事業を運営してきたのであり、対象会社の情報を大量に保有している。売主が、対象会社の情報を秘密保持せずに、ライバル企業などに流出させたりするような場合、対象会社の企業価値は著しく毀損する。 すなわち、株式譲渡契約書における秘密保持義務としては、株式譲渡がクロージングする前、買主が対象会社の事業に関する情報を開示することを禁止することは当然のことであるが、株式譲渡がクロージングした後、売主が対象会社の事業に関する情報を開示することを禁止することまで含むように規定する必要がある。 その他、従業員であるならともかく、オーナー経営者や取締役は、対象会社との間で、特段、秘密保持義務を締結していないことが多く、株式譲渡契約書に対象会社の情報に関する秘密保持義務を規定しない限り、対象会社の情報の流出を防止することができない可能性も存在する。 秘密保持義務の期間また、秘密保持義務の期間も重要である。 秘密保持義務の始期であるが、通常は、特段記載しないため、株式譲渡契約書の締結と同時に効力を発生する。 問題は秘密保持義務の終期であるが、筆者らの経験則的には、2年や3年にすることが多いように思われるが、対象会社の事業においては、2年や3年では情報の重要性が消滅しない場合は、秘密保持義務の期間が2年や3年程度では短いものと思われる。また、特段、終期を定めないことも多い。 また、その秘密保持義務の期間であるが、どの時点を起算点として計算するべきかについても一考が必要である。すなわち、旧オーナー経営者が、事業の引き継ぎのため、当面、対象会社に役員として在任する場合や顧問として業務を受託するような場合、秘密保持義務の期間は、その任期が終了してから計算を起算すべきであるし、旧オーナー経営者本人でなくても、旧オーナー経営者の関係者である役員などが在任している場合は、その者が退任するなどしてから秘密保持義務の期間の計算を起算すべきであろう。 その者が対象会社に在任などしている限り、売主である旧オーナー経営者は、対象会社の情報をアップデートすることができるのであって、その情報のアップデートが終了した時点から情報の陳腐化が始まるのであるから、秘密保持義務の期間の計算の起算は、その時点からスタートすべきだからである。 秘密保持義務の存続条項また、本条第2項は、秘密保持義務の存続条項である。 すなわち、株式譲渡契約書が解除その他の理由により終了してしまった場合、株式譲渡契約書が失効するのであるから、この秘密保持条項も失効するとなると、解除などの時点で、直ちに、秘密保持条項が失効してしまうこととなる。本来であれば、株式譲渡のクロージングから2年か3年継続するべきであった秘密保持義務が直ちに失効してしまうことは明らかにおかしい。また、株式譲渡契約書の解除などは一方当事者の意思で行うことができるケースが存在するのであるから、一方当事者の意思で、株式譲渡のクロージングから2年か3年継続するべきであった秘密保持義務が直ちに失効してしまうことは明らかにおかしい。 したがって、株式譲渡契約書の秘密保持条項には、存続条項も併せて規定されるのである。 ■■■第20条■■■■■■■■■■第20条 (対外公表)売主及び買主は、公表の時期及び内容について事前に合意することにより、本契約の締結の事実及びその内容を公表することができる。ただし、金融商品取引法、証券取引所規則等により必要とされる場合において、あらかじめ相手方に時期・内容・方法を通知した上で、合理的な範囲内で公表を行う場合は、この限りではない。 |
第20条 解説第20条は、対外公表に関する規定である。 オーナー経営者と対外公表第19条に基づき、売主及び買主は、秘密保持義務を負うが、売主としても、買主としても、事業承継M&Aを公表する必要がある場合がある。 売主のオーナー経営者としては、必ずしも、事業承継M&Aを公表したいわけではないことが多い。オーナー経営者としては、事業承継M&Aは、自分の引退であり、積極的には公表したくないというのが一般的であろう。 オーナー経営者については、事業承継M&A完了後、それを聞きつけた、金融機関や証券会社、親族・友人など、さまざまな人物が近づいてくるのであり、金の無心に来る者も多いと聞く。また、オーナー経営者からは、事業承継M&A後、非常にリスクの高い金融商品に投資をしたとか、プライベートバンカーにほとんど資金を預けてしまったとか、長年話をしたことがなかった親族が急に親しそうにやってきたなどの話はよく聞くところである。 事業の引継ぎと対外公表の重要性半面、売主としては、事業承継M&Aに伴い、買主に対して、対象会社をスムーズに引き継ぐ必要があり、オーナー経営者が退職した後も、対象会社が取引先や金融機関などとスムーズに取引を継続することができるよう、取引先や金融機関などに対して、事業承継M&Aについて報告を行う必要はあろう。 また、特に、その取引先や金融機関などとの間の契約書に、いわゆるチェンジ・オブ・コントロール条項(COC条項)(M&Aについて、その取引先や金融機関などの事前承諾を必要とする義務や、その取引先や金融機関などに事前報告・届出又は事後報告・届出を行う義務を規定する条項)が存在していた場合は、対象会社としては、その取引先や金融機関などに対して、契約上の義務として、その事業承継M&Aについて、情報開示をすることが必要となる。 実務的には、そのような取引先や金融機関などに対しては、担当者と面談をして、事業承継M&Aの概要を報告したり、少なくとも事業承継M&Aの概要を説明した通知書を郵送することとなる。 さらに、買主としては、事業承継M&Aの後、対象会社と協働し、相乗効果(シナジー)を生んで、買主及び対象会社の競争力を向上させたいと考えているところであり、事業承継M&Aにより、対象会社が買主のグループ企業になったことや、対象会社の経営方針について、対外的に情報開示を行い、アピールをしたいところである。また、この事業承継M&Aの情報開示が契機になり、取引先や金融機関などとの取引に新しい展開が生ずる可能性もある。 これは、特に、買主が上場会社の場合、顕著である。上場会社の経営陣としては、継続的に自社の業績を向上させ、株主に対してアピールし、株価の維持向上に努めるプレッシャーを受けているところ、事業承継M&Aを行ったということは、自社の株価向上に大きく資する行為であり、株主に対して、大きくアピールしたいと事項であろう。 対外公表される情報の管理の重要性なお、この対外公表される情報(事業承継M&Aに関する情報)については、第19条に基づき、秘密保持義務が課されており、対外公表のためには、相手方当事者の承諾が必要なのである。 買主としては、その通知書の内容に、真実と相違する事実が記載されている場合、情報開示されたくないのは勿論のこと、開示されたくない事実が開示されてしまうことを避けたい。例えば、買主としては、事業承継M&Aの取引金額・取引条件や対象会社の今後の経営方針などは開示されたくない場合が多い。 すなわち、情報開示した内容によっては、取引先や金融機関などが、それを買主や対象会社の公約と捉え、それを前提とした取引を要求してくることもあり、また、情報開示した文言によっては、買主や対象会社が、それにより外部に対して、事実上の約束をして義務を負うものや、文言によっては、法律上の義務を負うこととなる可能性もある。 買主としては、売主が、事業承継M&Aについて、取引先や金融機関などに対して、情報開示する場合は、その内容について、事前に確認を行い、必要に応じてその内容について修正を求めることが必要である。 法令上の対外公表義務がある場合もあるなお、上場会社が買主となる事業承継M&Aでは、金融商品取引法や証券取引所規則によって、適時開示義務が規定されている。この適時開示義務は、法令上の義務であることから、第20条ただし書きにおいては、相手方に対して、事前通知を行った上で、合理的な範囲内で公表することができることが規定されている。 |
⇒M&A契約書の作成・チェックの弁護士費用はこちら! 補償条項■■■第21条■■■■■■■■■■第21条 (賠償・補償)1. 売主及び買主が本契約に定める義務に違反し、又は表明・保証に違反した場合、違反した当事者は、相手方がかかる違反から被った損害、損失、負担、支出(合理的な範囲の弁護士費用を含む)、不利益等(以下「損害等」という)について、クロージング日から__年以内に賠償又は補償を請求する旨の書面が相手方から送付された場合は、相手方に対して損害等を賠償又は補償するものとする。 2. 本条に基づき売主が負担する賠償額及び補償額については、売主が受領した本件株式譲渡代金の__%相当する額を超えないものとし、また、かかる賠償又は補償の請求は、単一の事実に基づく請求の額が金___万円を超えたものに限り、行うことができるものとする。 | 第21条の2(特別補償)1. 売主は、前条のほか、対象会社が、クロージング前の事情に基づき負担すべき対象会社従業員の未払賃金(割増賃金を含む)及び延滞金等を請求された場合、クロージング日から__年以内に補償を請求する旨の書面が買主から送付された場合は、買主(又は買主が指定する場合は対象会社)に対して、対象会社従業員の未払賃金(割増賃金を含む)及び延滞金等相当額を補償するものとする。 2. 本条に基づき売主が負担する補償額については、売主が受領した本件株式譲渡代金に相当する額の__%(ただし、前条の賠償・補償がある場合は、当該賠償・補償と併せて__%)を超えないものとする。 第21条 解説第21条は、「補償条項」である。 英語では、Indemnity(インデムニティ)といわれる。 |
補償条項とは補償条項とは、相手方が、表明保証や遵守条項に違反した結果、損害を被った場合、相手方に対して、損害賠償責任・補償責任ができるとする規定である。 通常、私法上、故意又は過失により、相手方に対して、損害を与えてしまった場合は、損害賠償義務が発生する。債務不履行責任(民法415条)や不法行為責任(民法709条)である。 なお、債務不履行責任であれ、不法行為であれ、私法上は、加害者に故意又は過失などの帰責事由がない場合、責任は問われない。そのような場合は、損害賠償義務を負わなくてよいのである。 第21条においては、もちろん、故意又は過失により、相手方に対して、損害を与えてしまった場合の損害の賠償・補償義務は含まれる。 それに加えて、第21条において特徴的なのは、加害者に故意又は過失のいずれもない無過失の場合であっても、遵守条項違反や表明保証違反などを行ってしまった場合、その損害について、損害賠償責任・補償責任が発生するのである。 不可抗力的な事由により、遵守条項違反や表明保証違反などを行ってしまった場合も、損害賠償責任・補償責任を負うのである。 すなわち、第21条では、表明保証違反などの損害賠償義務・補償義務が規定されている。そもそも表明保証というのは、特段、当事者が遵守を約束した事項ではなく、当事者に何らかの履行義務があるものではなく、当事者がその表明保証に違反しても債務不履行になるようなものではない。 実際、第6条及び第7条の表明保証条項においては、表明保証は、何らかの約束をするとか、履行を約束するものではなく、そのような文言になっていない。単に、当事者が、対象会社などの客観的事実関係につき事実の表明をするのみなのである。事実を表明した結果、それが真実と異なっていた場合、債務不履行ではないものの、表明保証違反などの損害賠償義務・補償義務の責任を負うのである。 このような表明保証について、日本の民商法には特段の規定は存在しない。かといって、そのように表明保証した内容が真実と異なっていた場合、表明保証をした者に特段の責任が発生しないのであれば、その虚偽の表明保証を信用した者(相手方当事者)が不慮の損害を被る可能性があり、その者(相手方当事者)をその損害から救済することは困難である。 また、むしろ、そもそも表明保証の役割としては、買主は外部者であり、内部者である売主であるオーナー経営者との間では、対象会社内の情報につき絶対的な格差が存在するため、売主であるオーナー経営者に対して、対象会社の客観的事実関係について表明保証をさせ、それが真実と異なっていた場合に損害賠償責任・補償責任を発生させることにより、事業承継M&Aのリスクを、売主であるオーナー経営者に一部負担させるための規定である。 実務上、買主としては、事業承継M&Aに際して、対象会社に対して、デューデリジェンス(DD)を実施するものの、対象会社の調査を十分行うことができなかった場合や、対象会社の重要な事実関係について明らかにならないような場合、その事業承継M&Aの成否に十分に自信を持てず、事業承継M&Aを取り止めてしまうこととなる。しかし、対象会社の客観的事実関係のごく一部について、明らかではないということで、事業承継M&Aが取り止めになるというのは非常に不経済である。したがって、売主であるオーナー経営者が、対象会社の客観的事実関係について表明保証をすることにより、もしそれが誤っていた場合、買主に対して損害賠償責任・補償責任を負うということとすることにより、買主としては、その点が調査によって明らかにならない場合であったとしても、売主であるオーナー経営者のその表明保証を信用して、事業承継M&Aを実行することができることとなり、事業承継M&Aが実施しやすくなるのである。 そういう意味では、表明保証違反などの損害賠償義務・補償義務が存在するからこそ、これらが存在しない場合には成立しないような事業承継M&Aも実施することができ、社会経済に資するのである。 補償期間についてこのような表明保証違反などの損害賠償義務・補償義務であるが、当事者としては、損害賠償義務・補償義務を負担する以上、永久に負担するということも一考であるが(その場合でも消滅時効により5年又は10年で消滅するものと思われるが)、それでは負担が重くなってしまうことから、多くの株式譲渡契約書においては、期間制限が設定される。また、表明保証違反などの損害賠償義務・補償義務に期間制限を設定しない場合は、事業承継M&Aの当事者は、その損害賠償義務・補償義務が発生することを恐れ、永久に損害賠償資金・補償資金を手元に準備しておく必要を感じることとなり、特に、事業承継M&Aの売主は、対象会社を売却し、その対象会社の売却資金を、自己の老後の生活資金や第二の人生を開始するための資金としたいと思っているにも拘らず、永久に、その対象会社の売却資金を使用することができなくなってしまう。 この表明保証違反などの損害賠償義務・補償義務の期間としては、多くの場合、1年から5年の間で設定されることが多いが、少なくとも1年以上にすることが一般的である。 すなわち、事業承継M&Aを行って1年以上経過することにより、対象会社は、少なくとも1回以上決算期を迎えることになるのだが、その決算期において、買主及びその税理士が決算を締める過程で、表明保証違反などが発覚することがあり、また、通常、買主及びその税理士は、その決算を締める過程で、表明保証違反などの事実がないかを全体的に検討することができ、表明保証違反などの損害賠償義務・補償義務の制限期間内に、表明保証違反などの損害賠償義務・補償義務の追及をすることができるからである。 この表明保証違反などの損害賠償義務・補償義務の期間制限について、買主としては、本来なら、1回の決算といわず、2回・3回の決算に際しても検証をしたいと思われ、また、1回だけの決算ではすべての表明保証違反などの事実を発見できるというようなものではないこともあり、2年や3年又はそれ以上の表明保証違反などの損害賠償義務・補償義務の期間を設定するものも多い。 また、個別の表明保証違反や遵守条項との関連では、対象会社の従業員の未払残業代の時効は2年であり、対象会社の法人税の時効は最大7年であることや、一般の商事時効が5年であることなどに鑑み、その期間の間は、対象会社にそのような表明保証違反や遵守条項違反の事実が存在し、従業員から未払残業代を請求されるかもしれない、税務署から未払法人税を請求されるかもしれない、取引先からも未払を請求されるかもしれない、ということになると、1年ではなく、2年や3年あるいはそれ以上の表明保証違反などの損害賠償義務・補償義務の期間を設定しないと、買主にとってリスクになってしまうケースも多く存在する。 また、土壌汚染のように、所有者である以上、時効の適用なく、永久に責任を負う可能性が生ずることもある。特に、事業承継M&Aにおいて、そのような事項が問題となった場合、表明保証違反などの損害賠償義務・補償義務の期間については、長期間設定されることも多くある。 また、これらの個別項目ごとに、表明保証違反などの損害賠償義務・補償義務の期間を設定することも多く存在する。 補償額の制限についてまだ、本条2項においては、損害賠償額・補償額の制限が規定されている。 すなわち、損害賠償額・補償額の制限が存在しない場合は、理論的には、売主としては、表明保証違反などの損害賠償義務・補償義務を最大限負った場合、株式譲渡価格以上の義務を負う可能性がある。 すなわち、理論的には、対象会社の行う事業の社会的影響に鑑み、対象会社は、対象会社の株式譲渡価格よりも大きな損害を、第三者に与える可能性はある。買主は、対象会社を買収後、対象会社が何らかの表明保証違反行為などを行っていた結果、株式譲渡価格以上の損害を第三者に与える結果、その損害賠償責任を負った場合、対象会社は相当額の損害を被ることから、売主はその損害賠償責任・補填責任を負担してしまう。 ただ、売主としては、この事業承継M&Aの結果、株式譲渡代金の額しか受領していないのに、それ以上の損害について損害賠償責任・補償責任される可能性があるということであれば、それ自体、大きなリスクであり、それであれば事業承継M&A自体行わないという判断になりかねない。事業承継M&Aにより、対象会社を売却することで、株式譲渡代金以上の損害を被るのであれば、トータルでマイナスであるから、そもそも、事業承継M&Aを実施しなければよかったということになり、社会経済に大きなマイナスとなるのである。 したがって、株式譲渡契約書の補償責任としては、最低でも、株式譲渡代金の額を超えないとされることが一般的である。この点、対象会社の株式価値が、実質的に、株式譲渡代金と役員退職慰労金その他の2つ以上に分けて支払われる場合は、株式譲渡契約書の表明保証違反などの損害賠償責任・補償責任の額の範囲としては、株式譲渡代金の額ではなく、株式譲渡代金と役員退職慰労金その他の合計額が基準となることが一般的である。 また、さらに進んで、表明保証違反などの損害賠償額・補償額の範囲について、株式譲渡代金の額から公租公課を考慮した手取り額の範囲とすることも多く、その場合、株式譲渡代金の額の80%とすることや、50%とすることもある。 また、そもそも、表明保証違反などの損害賠償額・補償額の範囲について、株式譲渡代金の額の30%や20%とすることもある。これは、ひとえに、買主としては、表明保証違反などによる損害賠償責任・補償責任が発生する可能性をどの程度だと考えるか、あまり発生しないだろうと考えるか、この程度は発生するであろうと考えるかに依ってくる。 また、売主としても、株式譲渡代金を受領した後、直ちに資金使途がある場合などもあり、株式譲渡代金の手残りが減ってしまう場合、そのようなタイミングで表明保証違反などの損害賠償責任・補償責任が行われたとしたら、自己資金からの持ち出しになるような場合や、ひいては資金不足で破産しなければならないような事態にならないかなどを考慮して決定されることが多い。 実務上は、中間をとってということではないと思われるが、50%とすることが最も多いように思われるが、こちらは売主と買主の力関係で決定してくるものであり、景気循環局面局面で大きく変わることとなる。 補償請求の最低金額についてまた、第2条の後半においては、表明保証違反などの損害賠償責任・補償責任を負う場合として、単一の事情に基づく損害賠償責任・補償責任の最低金額が規定されている。すなわち、例えば、対象会社の什器備品が壊れていたとか、対象会社のオフィスの壁にキズがあり賃貸物件の明け渡しの際に敷金・保証金から控除されるとか、少額の表明保証違反などが存在することはままあり、そのように、例えば、数万円程度の表明保証違反違反などによる損害が発生する都度、損害賠償請求権・補償請求権を行使されるようでは、事務が煩雑すぎて対応できないし、対象会社の事業を運営する過程において、それくらいの損害であれば数多く存在する可能性もある、他方、買主としても、まとまった金額の株式譲渡価格を支払う以上、その程度の金額であれば表明保証違反などによる損害も想定内であるという場合も多い。売主であるオーナー経営者としても、対象会社において、少額の表明保証違反などはあるかもしれないと考えつつも、重要な表明保証違反などは存在しないと考えていることが多いであろう。また、そもそも、軽微な表明保証違反などによる損害であれば、事業承継M&Aのクロージング後、買主による対象会社の事業の運営上、重大な問題にならないはずである。したがって、株式譲渡契約書において、単一の事情に基づく損害賠償責任・補償責任の最低金額を設定し、軽微な表明保証違反などによる損害については、損害賠償義務・補償義務が発生しないとすることが多い。 なお、単一の事情に基づく損害賠償責任・補償責任の最低金額を設定する場合、表明保証違反などが数多く存在し、その結果、すべての表明保証違反などによる損害の合計額が、この最低金額を超過したとしても、単一の事情に基づく損害賠償責任・補償責任の額が最低金額を超過していなければ、損害賠償請求権・補償請求権は行使できないこととされることが一般的である。 また、この単一の事情に基づく損害賠償責任・補償責任の最低金額を超過した場合に、売主から、買主に対して、その損害額の超過額のみを損害賠償責任・補償責任可能とする場合もあれば、その損害額の全額について損害賠償責任・補償責任可能とする場合も存在する。前述の、数万円程度の表明保証違反違反などによる損害が発生する都度、損害賠償請求権・補償請求権を行使されるようでは、事務が煩雑過ぎるとの趣旨に鑑みると、単一の事情に基づく損害賠償責任・補償責任の最低金額を超過した場合に、売主から、買主に対して、その損害額の全額について損害賠償責任・補償責任可能とすることが経済合理的である者と思われる。 特別補償条項について前述のとおり、買主において、表明保証違反に関する認識があった場合には、表明保証違反の損害賠償責任・補償責任が認められないというのが、近時の裁判の傾向であり、また、株式譲渡契約書にいわゆるサンドバッキング条項を盛り込む場合においても、このいわゆるサンドバッキング条項が裁判所で有効と判断されるか否か分からない。 したがって、近時においては、買主が、デューデリジェンス(DD)において、表明保証違反の状態を発見した場合には、表明保証条項のみならず(表明保証条項ではなく)、特別補償条項を別途規定することが多い。 特別補償条項は、表明保証違反とは関係なく、一定の事由が発生した場合に、売主に対して補償義務を負担させる規定であることから、表明保証違反の認識の有無によっては、その効果は変動しないはずだからである。 補償責任の履行の現実性について事業承継M&Aの対象会社は中小企業、零細企業であり、そのオーナー経営者は、事業承継M&Aにより譲渡代金が入ってくるものの、もともと小規模事業者であり、その資力に鑑みると、買主が、売主であるその旧オーナー経営者に対して、この損害賠償責任・補償責任を行ったとしても、必ずしも、履行されるとは限らない。 そこで、この損害賠償責任・補償責任を担保するための手法の検討が必要であり、株式譲渡代金の分割払いや損害賠償請求権・補償請求権に対して担保提供をして頂くとか、株式譲渡代金を一定期間エスクロー口座に預かってもらうなどの対応が検討されることもある。 しかし、そのような旧オーナー経営者としては、老後資金などの資金ニーズがあったり、分割払いについては、2回目以降の支払いが実際に行われるかどうか不安だとか、担保提供に関しても、そのような担保がないとか、そのような提案は、売主である旧オーナー経営者が拒否することが多い。 そもそも、筆者らが相談を受けるケースにおいても、買主は、しばしば、クロージング後、事業承継M&Aに失敗したと認識した時、売主である旧オーナー経営者に補償させようとして、表明保証違反や遵守条項違反など、とにかく、何らかの理由をつけ、2回目以降の支払いを拒絶したり、担保権を実行しようとしたり、エスクロー口座からの出金を認めなかったりし、株式譲渡代金が宙に浮いたり、売主が、株式譲渡代金の一部返還を強いられていることが多い。 したがって、売主としては、株式譲渡代金の分割払いや損害賠償請求権・補償請求権に対して担保提供をして頂くとか、株式譲渡代金を一定期間エスクロー口座預かってもらうなどの対応は、受け入れないことが一般的である。 そう考えると、買主としては、最悪、売主であるその旧オーナー経営者に対して、この損害賠償責任・補償責任を行ったとしても、履行されないことを前提に、事業承継M&Aを検討しなければならない。すなわち、事業承継M&Aの買主としては、十分に対象会社に対して、デューデリジェンス(DD)を実施したり、株式譲渡代金の価格についてよく検討を行ったり、事業承継M&Aのスキームについてもよく検討し、株式譲渡契約書などを良く作り込み、予めリスクヘッジをしておくことが好ましい。 |
⇒M&A契約書の作成・チェックの弁護士費用はこちら! 解除条項■■■第22条■■■■■■■■■■第22条 (解除)売主及び買主は、相手方に重大な表明保証違反があることが判明し、その結果本契約を維持することが困難になった場合、相手方に本契約上の重大な義務の違反があり、当該当事者に対する書面による催告後その違反が是正される見込みがない場合、又は相手方について、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始その他これらに類する法的倒産手続きの申し立てがなされた場合には、クロージング日前に限り、相手方に対して書面で通知して本契約を解除することができる。 |
第22条 解説第22条は、株式譲渡契約書の解除規定である。 株式譲渡契約の解除について株式譲渡契約も、契約である以上、契約の解除条項は存在する。 株式譲渡契約にも、一般的な契約と同様、契約の相手方に遵守条項違反を含む債務不履行がある場合は、契約は解除されてしかるべきである。また、契約の相手方に債務不履行が生ずることが確実である場合、例えば、契約の相手方が倒産状態に陥ったような場合、契約は解除されてしかるべきである。 また、買主が、株式譲渡代金を支払えないことが確実になった場合のように、債務不履行が確実になった場合も解除されてしかるべきかもしれない。売主であるオーナー経営者としては、そのような買主との契約は早々に解除して、新しい信用力のある買主を探したいと考えてしかるべきである。 表明保証違反などによる株式譲渡契約の解除と損害賠償責任・補償責任についてその他、株式譲渡契約書に特有の解除事由は、表明保証違反があった場合である。表明保証違反があるということは、株式譲渡の前提条件が満たされないということであり、そもそも買主の株式譲渡の実行義務が発生しないことが多く、また、買主としてもそのような株式譲渡を実行して対象会社を買収しても、想定通りにはならず、買主の想定する株式譲渡価格の前提を欠くため、不利益を被る可能性が高いため実行したくないのである。 他方、売主と買主は株式譲渡の実行のために、それまでの間、時間と労力と資金を投入して交渉し、多大なるエネルギーを費消して株式譲渡契約書の締結にも至っているのであるから、売主から見ると、表明保証違反があっても、それが重大なものでない限り、株式譲渡契約書は解除まではせずに、クロージングは行った上で、買主が被るであろう表明保証違反などによる損害は、表明保証違反などによる損害賠償責任・補償責任により事後的に調整することも可能であり、この方が経済的である。 また、契約の解除という、影響の大きい方法を採用するのではなく、表明保証違反などに基づく損害賠償責任・補償責任により、当事者の利害関係を適切に調整できる可能性も高い。表明保証違反などが存在し、株式譲渡を実行することで、当事者に取り返しのつかない損害が発生しない限り、株式譲渡を実行しつつ、表明保証違反に基づく損害賠償責任・補償責任により利害関係を調整したほうが良い場合は多いであろう。 表明保証違反などによる株式譲渡契約の解除と前提条件に基づく株式譲渡の実行の延期についてまた、表明保証違反の場合には、株式譲渡の前提条件が充足されないわけであるから、買主としては、株式譲渡の実行を延期しつつ、売主に表明保証違反への対処を求め、それが解消した場合に(あるいはそれが一定程度解消した場合に)、株式譲渡を実行し、それでも発生した表明保証違反に基づく損害については、損害賠償責任・補償責任により調整するというように、株式譲渡契約書においては、前提条件条項・補償条項・解除条項により、売主と買主の利害を調整しつつ、株式譲渡が実行することが好ましい場合が多い。 とはいえ、事業承継M&A実務上、株式譲渡の前提条件を充足されていないことを理由に一度延期された株式譲渡を、再度軌道に乗せて、株式譲渡の実行を行うことは、その間において、売主と買主との間の信頼関係が毀損されてしまっていることが多く、それほど容易なことではない。 また、特に、買主が中堅企業・大企業である場合など、社内手続きや各部署に対する説明などの関係で、一旦、事業承継M&Aを中断することも困難であり、また、いったん中断した事業承継M&Aを再開することはさらに困難を伴う。 このように考えると、事業承継M&Aにおいては、表明保証違反などが存在したとしても、ひとまず株式譲渡の実行は完了させることとし、売主と買主は引き続き協議し、クロージング後も引き続き、表明保証違反などの解消に努めて頂くことについて合意し、売主が、最大限、買主の想定する対象会社の企業価値が毀損されないようにすることに合意することが、最も実務的であるものと思われる。 そのうえで、どうしても表明保証違反などが解消されず、それが重大な損害をもたらしている場合は、やむを得ないのであるから、売主は、買主に対して、表明保証違反に基づく損害賠償責任・補償責任により利害関係を調整したほうが好ましい場合も多いものと思われる。 クロージング後の解除の制限について事業承継M&Aにおいて、事業承継M&Aを実行し、買主が対象会社の事業の運営を開始してしまった後に、その取引を解除するとなると、その後、売主が対象会社の事業の運営を継続することとなるが、そのようなことが生ずると、対象会社の事業の運営に大変な混乱をもたらすこととなる。 すなわち、事業承継M&Aにおいて、株式譲渡のクロージングが行われるまで、売主であるオーナー経営者が対象会社を経営し、クロージング直後から、買主が対象会社を経営することが一般的である。クロージングにより、対象会社の所有権が、売主から買主に移動するのだから、これは当然のことである。 そうであるからこそ、対象会社においては、株式譲渡契約書締結後、対象会社のオーナーが変更になることについて、取引先や金融機関、役員・従業員その他のステークホルダー(関係者)に周知し、売主であるオーナー経営者としては、クロージング以降、買主に対して、対象会社の事業の運営の引継ぎを開始し、又は、すでにクロージング前から買主に対する引継ぎを開始しているケースも多い。 また、株式譲渡のクロージング以降は、買主は、買主の独自の経営戦略をもって対象会社の事業の運営を開始している場合も多く、取引先や金融機関などに対する独自の対応や、役員・従業員などに対しても独自の対応を開始している可能性があり、かつそのようなことを行うことが可能な状態になっている。 売主であるオーナー経営者としては、株式譲渡のクロージング以降、株式譲渡契約を解除して、原状回復を行った場合(株式を売主に返還し、株式譲渡代金を買主に返還した場合)、売主に返還されるのは、買主がそのような独自の対応に基づく事業の運営を行った対象会社であるのであって、クロージング前の対象会社と同じ会社ではない。 すなわち、売主に返還される対象会社は、すでに株式譲渡のクロージング前の対象会社とは異なっているのである。具体的に考えても、買主が取引先や金融機関などを変更してしまっている場合や、買主の対応やフォロー又は引き継ぎが悪く、取引先や金融機関などとの関係が悪化していたり、取引継続が困難になっていたり、取引が中断されてしまっていたりすることもある。 また、買主としては、役員・従業員などを入れ替えたり、買主の対応やフォロー又は引き継ぎが悪く、役員・従業員などが退職してしまったり、特に重要な従業員(キーマン)が退職してしまったり、組織体系を変更してしまっていたり、さらには、従業員から未払残業代を請求されてしまったりすることもある。 売主としては、株式譲渡契約の解除に伴い、原状回復として、そのような対象会社を返還してもらったとしても、原状回復することができないのである。すなわち、株式譲渡のクロージング以降は、対象会社という意味では同じではあるが、クロージング前のそれとは異なった会社になってしまっているのであり、対象会社の企業価値が変動してしまっているのである。 そうであるからこそ、株式譲渡契約書を含むM&A契約書においては、通常、クロージング後は、契約の解除を行うことはできないものとされている。 |
⇒M&Aトラブルでお困りの方はこちら! 一般条項■■■第23条■■■■■■■■■■第23条 (費用)本契約に係る諸費用(弁護士、公認会計士その他のアドバイザーに係る費用を含む)は、本契約に別途規定した場合及び別途合意した場合を除き、売主及び買主の各々が支出した金額を各自で負担するものとする。 |
第23条 解説第23条は、費用の負担に関する規定である。 費用の負担に関する規定について本条は、各自の費用は各自の負担とだけ規定する。 ただし、事業承継M&Aに関する費用には様々なものがあり、各自の負担とすれば、すべて公平性が担保されるほど単純ではない。 遵守条項の履行費用について株式譲渡契約書には、すでに述べた通り、多数の遵守条項が存在し、売主も買主もそれを履行するにはそれなりのコストが発生することがある。 例えば、売主に対して、遵守条項として、クロージングまでに、対象会社の就業規則を作成するという規定があった場合、対象会社において、就業規則を作成するために、弁護士又は社会保険労務士を指名し、報酬を支払うこととなる。その報酬は、だれが負担するのかと考えると、対象会社が負担することが一般的である。 しかし、対象会社において、就業規則が作成されていなかったというのは、売主である旧オーナー経営者の怠慢なのではないかとも考えられる。 対象会社が就業規則の作成の費用を負担するとなると、その対象会社を買収するのは買主なのだから、総合的にみると、買主が対象会社を通じてその費用を負担したということになるのではないかとも思われる。そうであるならば、買主としては、株式譲渡価格をその分減額する必要があるだろう。もし、株式譲渡価格をその分減額しないのであれば。対象会社が就業規則の作成の費用を負担してしまうと、対象会社の企業価値がその分減少してしまう。そう考えると、対象会社の就業規則の作成の費用は、売主である旧オーナー経営者が負担するべきではないかとも思えるが、売主である旧オーナー経営者が対象会社の就業規則の作成の費用を負担するための遵守条項は規定されていないことが多い。 就業規則の作成の費用であればそれほどの金額にはならないが、事業承継M&Aに伴い、対象事業を会社分割する会社分割方式の場合は、その会社分割手続きの費用や会社分割の登記費用は、誰が負担するかも大きな問題となる。 各自の費用は各自の負担とだけ規定する場合は、特段の規定がなければ、対象会社がその費用を負担し、事業承継M&Aのクロージングに伴い、実質的に買主の負担ということとなってしまうが、その個別の遵守条項において、費用負担を明記することにより、売主に費用負担をさせるべき場合が多く存在するのである。 変更登記費用などについてまた、クロージング前後における臨時株主総会の開催の費用や、クロージングに伴い、売主側の役員が辞任し、買主側の役員が就任する場合の登記費用なども、売主又は買主のどちらが負担するべきか問題になることが多い。 この点、事業承継M&Aのクロージングに伴い、臨時株主総会が開催されるのは、一般的にクロージングの直後であり、したがって、役員変更登記を行うのもクロージングの後であることから、その費用は対象会社が負担し、実質的に買主の負担となることが多いかと思われるが、買主としては、それを嫌って、クロージング前に臨時株主総会を開催し、役員を変更し、役員変更登記も済ましておくことを求めることも多い。その場合も、対象会社自身の費用であることから対象会社負担となり、結局、実質的に買主の費用負担となるものと思われるが、実務上は、売主の費用負担である旨明記することも多く、また、売主側役員の辞任に関する費用は売主負担、買主側役員の就任に関する費用は買主側負担とすることも多い。 また、対象会社が、取締役会非設置会社・監査役非設置会社となり一人代表取締役となっている場合も多く、買主としては、特に、中堅企業・大企業の場合、一般的な組織形態である取締役会設置会社・監査役設置会社に戻したい場合も多い。そのような場合、一般的ではない組織形態を採用していた売主である旧オーナー経営者が費用負担するべきではないかとも思われる。また、買主が、クロージングを契機に、対象会社を、管理が容易な取締役会非設置会社・監査役非設置会社の一人代表取締役にしたいと考えることもあり、そのような場合、その部分は、売主ではなく、買主が費用負担するべきとも思われる。すなわち、特殊な組織形態を採用した場合、それを採用した者が、費用負担をすることとされる場合が多い。 金融機関から融資(LBOローン)や法律意見書に関連する費用についてまた、買主が事業承継M&Aを行うに伴い金融機関から融資(LBOローン)を借りる場合には、金融機関に法律意見書の提出などが必要となり、その法律意見を形成する前提として、対象会社が数多くのクロージング書類を作成することとなるが(事業承継M&Aの対象会社は中小企業、零細企業のためそのような業務能力に欠けることもあり売主が対応することが多くなるが)、その作業には多大な費用が発生するところ、また、法律意見書作成の弁護士費用はとかく高額であるところ、その費用の全てを売主が負担するのか、買主が金融機関から融資(LBOローン)を借りるために必要な資料を、売主が労力と費用をかけて作成するのか、売主としても、買主や対象会社に費用負担して頂くのが自然なのではないかなどの問題が生ずる。 ■■■第24条■■■■■■■■■■第24条 (不可抗力)1. 地震、台風、津波その他の天変地災、戦争、暴動、内乱、テロ行為、政府、重大な疾病、省令・規則の制定・改廃、地方公共団体等公権力の命令規制・処分その他政府による行為、争議行為、輸送機関・通信回線等の事故、その他当事者の責に帰すことのできない事情により本契約の全部又は一部(金銭債務を除く)の履行遅滞又は履行不能については、いずれの当事者もその責任を負わない。 2. 前項に定める事由が生じ、本契約の目的を達成することが困難であると認めるに足りる合理的な理由が有る場合には、売主及び買主協議の上、本契約の全部又は一部を解除できる。 |
第24条 解説第24条は、不可抗力条項である。 事業承継M&Aにおいて、多くはないものの、予定していたM&Aを否応なく取り止める必要性に迫られることが存在する。 東日本大震災と不可抗力条項について特にこれが問題となったのは、まずは、東日本大震災の際である。東日本大震災の被害は甚大であり、その後、当面の間、対象会社が通常の事業運営の状態に戻ることができないことは明らかであった。対象会社が被災していなくとも、対象会社の取引先が被災したり、インフラが毀損したりして、対象会社はそれまで通りの事業運営や業績を上げることは著しく困難になったのである。すなわち、対象会社の企業価値は著しく毀損したのである。このような場合、買主は、対象会社の株式譲渡の実行を強行しなければならないとしたら、事業承継M&A直後から、直ちに大きな損害が発生することとなる。特に、東日本大震災は3月11日に発生したこともあり、非常に多くのM&A案件が、3月末のクロージングを目指して、株式譲渡締結を完了し、クロージングに向けて準備をしていた。 東日本大震災が発生した際、多くのM&A案件は、この不可抗力条項が入っていることを理由に、又は不可抗力条項が入っていない場合であっても当事者の合意により事実上、クロージングを停止し、ひとまずクロージングを延期し、最終的に、事業承継M&A自体が取り止めになったものが多く存在した。 他方、株式譲渡契約書にこの不可抗力条項が入っていなかったため、買主として、売主からクロージングの実行を迫られ、ここで買収したら直後から多額の損害が発生することを予測しつつも、紛争化することや損害賠償責任・補償責任を避けるため、泣く泣く、事業承継M&Aのクロージングを実行した事例も存在すると聞いている。 リーマンショックと不可抗力条項についてまた、特にこれが問題となったのは、リーマンショックの際である。 リーマンショックの前数年間は、未曾有のM&Aバブルであり、リーマンショックの際もM&Aバブルのピークは過ぎていたものの、余韻の冷めやらぬ中、多数のM&A案件が存在しており、クロージングを迎えていた。その際に、リーマンショックが発生した。買主としては、リーマンショックの後の、経済情勢の不透明感の強い中、M&Aを実行し、対象会社を買収したとしても、対象会社においてそれまでと同様の業績を上げることは著しく困難な状態である。すなわち、これも、対象会社の企業価値が著しく毀損してしまったのである。しかも、その帰責性は、売主にあるものでもなく、買主にあるものでもない。売主にも買主にも帰責性があるわけではなく、株式譲渡契約の解除事由も適用されない。株式譲渡契約書に不可抗力条項が規定されていなかった場合、買主は、泣く泣く、株式譲渡のクロージングを強行し、対象会社を買収しなければいけないこととなってしまう。 実際にこのような場合も想定されることから、事業承継M&Aの買主においては、対象会社の買収という小さからぬ買い物をするわけであることから、不可抗力状況を規定しつつ、やむを得ない場合には、不可抗力条項により、事業承継M&Aを取り止めることができるようにしておく必要があるものと思われる。 ■■■第25条■■■■■■■■■■第25条 (譲渡禁止)本契約において別段の定めがある場合を除き、売主及び買主は、本契約上の権利又は本契約上の地位の全部若しくは一部を、相手方当事者の書面による事前の同意なしに、第三者に譲渡、移転、担保権の設定その他の方法により処分してはならない。 |
第25条 解説第25条は、譲渡禁止の規定である。 譲渡禁止の規定についてすなわち、この株式譲渡契約の当事者を、第三者に譲渡することを禁止する規定である。これは英米法上、契約書の一般条項として、一般的に規定されるものである。 これはいわば当然の規定である。売主としても、買主を信頼して対象会社を売却するのであり、買主としても、売主を信頼して対象会社を買収するのであるから、もし、株式譲渡契約の当事者を第三者に譲渡することができ、株式譲渡契約の当事者が他の第三者となるのであれば、事業承継M&Aは成立しないであろう。 英米法上、このような譲渡禁止規定が存在していないことを良いことに、契約当事者の地位を譲渡してしまう事例が生じたため、敢えて契約書にこの譲渡禁止を入れることとなった歴史がある。 株式譲渡契約書を譲渡すべき場合について日本においても、確かに、有望な会社を買収する株式譲渡契約を予め締結しておいて、クロージングまでに多めに日数を確保し、その間にマーケティングを行い、新しい買収希望会社を探し出し、より高い価格でその買収希望会社に売却するか、あるいは、この株式譲渡契約の買主の地位をその買収希望会社に譲渡してしまうことで利益を得る業者は存在してもおかしくはない。 実際、ファンドなどは、ファンド運営会社などがひとまず株式譲渡契約の当事者となり、クロージングまでに、ペーパー・カンパニー(SPC)を設立し、このペーパー・カンパニー(SPC)に対して、株式譲渡契約を譲渡することはまま行われる。また、ファンド運営会社がひとまず株式譲渡契約の当事者となり、クロージングまでに投資家の了解を得てその出資を確保し、買収主体となるファンドを設立し、そのファンドに対して、株式譲渡契約を譲渡し、そのファンドが対象会社を買収することもある。 このような場合には、株式譲渡契約の譲渡は許されることとなり、本条に基づき、売主の承諾を得て、株式譲渡契約の譲渡が行われるのである。 ■■■第26条■■■■■■■■■■第26条 (通知)本契約に基づく通知は、以下の住所(又は本条の方式に従い通知された住所)宛てに書面又はファクシミリにより通知された場合に限り有効な通知とする。 (1) 売主に対する通知 住 所 東京都______________ 氏 名 _________________ FAX _________________ (2) 買主に対する通知 所在地 東京都______________ 会社名 株式会社_____________ 担当者 _________________ FAX _________________ |
第26条 解説第26条は、通知に関する規定である。 事業承継M&Aのクロージング前はともかく、クロージング後において、売主と買主の間では何かとコミュニケーションが発生する。 クロージング前であれば、クロージングの準備などの実務的なコミュニケーションはもとより、第8条第2項に基づき、対象会社に、対象会社に重大な悪影響を及ぼすおそれのある事由が発生した場合において、売主は買主に対する通知義務が課されているが、このような通知は、本条に基づき行う必要がある。また、第22条に基づき、株式譲渡契約を解除する場合の通知も、本条に基づき行うこととなる。 また、株式譲渡契約書に明記されていない通知についても、株式譲渡に関する通知は、本条に基づき行う必要がある。すなわち、実務上発生するものは、買主から売主に対する表明保証違反や遵守条項違反行為に関する要請や警告の通知や、売主が株式譲渡契約の解消を求めている場合や、売主が他の買主候補者と交渉している場合に送付する警告書などは、本条に基づき送付することとなる。 また、株式譲渡のクロージング後についても、買主から売主に対する表明保証違反や遵守条項違反行為に関する要請や警告の通知や、損害賠償請求権・補償請求権の行使の通知などは、本条に基づき行うこととなる。 第26条では明確に記載していないが、日本の民法はいわゆる到達時説を採用し、通知は到達したときに有効になるのが原則であるものの、必ずしも到達しなくても発信しさえすれば通知が有効であると規定されることもあり(発信時説)、注意が必要である。また、当事者が、自らの故意又は過失によって、例えば、通知が届かないようなところに引っ越したり、FAX番号を変更したりして通知が届かなかった場合や、引っ越しをしたことによって通知が届かなくなった場合も、受信者の過失として、実際には通知が到達していなくても通知は有効であるとする規定がなされることもある。 そのような意味で、株式譲渡契約書には、当事者とも、明確に住所・氏名・FAX番号を記載し、株式譲渡のクロージング以降も当面はそれを維持すること、及び、通知先が変更になる場合は遅滞なく通知することを前提に、相手方当事者からの通知が相違なく届く状況にしておくことが必要となろう。 ■■■第27条■■■■■■■■■■第27条 (完全合意)本契約は、本契約の対象事項に関する当事者間の完全な合意及び了解を構成するものであり、書面によるか口頭によるかを問わず、かかる対象事項に関する当事者間の本契約締結前の全ての合意及び了解に取って代わる。 |
第27条 解説第27条は、完全合意条項である。 完全合意条項とは、当事者間の合意は、この株式譲渡契約書に記載されたもののみであり、それ以前になされた文章又は口頭の合意は全て無効とするものである。 たしかに、事業承継M&Aの手続の過程は長く、通常は、事業承継M&Aに本格的に取り組み始めてから半年程度、長いものでは2-3年越しの案件も多く、さらに事業承継M&Aの話になる前に、かなりの長期間にわたって、M&A専門家やM&A税理士が売主との間で相談に応じていることもあり、その過程で、売主と買主のみならず双方のアドバイザーや専門家も含めて、さまざまな口頭の合意をすることも多く、事業承継M&Aの後には、往々にして、「あのとき・・・という約束をしたはずだ」「・・・にするという話だった」という問題が生ずることが多い。 たしかに、日本法上、口頭での合意も有効であり、かつ書面がなくても、メールや録音、その他の周辺事情から、そのような口頭の合意があったことが証明できることも多い。 しかし、そのような合意が、株式譲渡契約書の内容と異なっていたり、矛盾していたりすると、後日混乱をきたすし、当事者の一方はそのような合意はすでに失効したと考えているのに対し、もう一方の当事者は有効と考えているなど、合意の状態が不明確な状態になっていたり、それが原因で後日トラブルになりそうな場合も多い。 したがって、そのような株式譲渡契約書外の合意を排除して無効化し、株式譲渡契約の内容を一元化するために、株式譲渡契約書においては、この完全合意条項が重要となるのである。 他方、事業承継M&Aの際には、株式譲渡契約書以外の契約書も締結されることも多い。 法的拘束力を有する可能性のある書類としては、秘密保持契約書、意向表明書、基本合意書があるし、事業承継M&Aのストラクチャーによっては、会社分割計画書・会社分割契約書、合弁契約書、商標譲渡契約書その他の知的財産権譲渡契約書、ライセンス契約書、業務委託契約書、顧問契約書などが締結される。株式譲渡契約書に完全合意条項を規定することで、そのような契約書の効力が失効させられてしまうことは避ける必要があり、契約書を特定したうえで、本条において除外文言を入れることもある。 なお、契約書の特定は、契約当事者名・契約締結日付・契約書名をもって行い、例えば、「売主及び買主の間の平成30年7月10日付け秘密保持契約書」などというように記載する。 その他、第27条は、売主と買主との間のその他の契約をすべて失効させるものではない。売主と買主との間には事業承継M&Aのみならず、通常の取引も存在する可能性があり(全く無い場合も多くあると思われるが)、そのような契約の効力を失効させるべきではない。そこで、第27条においては、「本契約の対象事項に関する」との文言が入っており、事業承継M&Aに関する事項についてのみの完全合意条項となっており、事業承継M&A以外の合意については失効させないような配慮がなされている。 ■■■第28条■■■■■■■■■■第28条 (準拠法)本契約は、日本法に準拠し、これに従って解釈されるものとする。 |
第28条 解説第28条は、準拠法に関する規定である。 売主と買主の双方が日本人又は日本企業であれば、通常、準拠法は、日本法が選択される。このような準拠法の合意がなされれば、法の適用に関する通則法第7条に基づき、この株式譲渡契約書の準拠法は日本法になり、またこのような規定が存在していなくても、法の適用に関する通則法第8条に基づき、密接関連地法として、日本法が準拠法として選択されるものと思われるため、いずれにしろ事業承継M&Aの株式譲渡契約書の準拠法は日本法となるものと思われる。 第28条は、今日の、日本人・日本企業同士の一般的な事業承継M&Aにおいてはあまり問題になることはないものの、今後、外国人や外国法人の事業承継M&Aへの参入又は、多国籍企業の事業承継M&Aが生ずる場合などは、重要な論点として浮上してくる可能性は存在する。 この点、株式譲渡契約の準拠法を外国法としたとしても、いずれにしろ対象会社に適用されるのは日本法であり、業法も日本法が適用されるのであり、対象会社の所在や事業承継M&Aの取引は日本で行うのであるから、日本法を準拠法とすべきである。また、外国人に対して、事業承継M&Aを実行する場合も、米国などの自由主義国家の法律であれば、日本法同様、取引について特殊な制限は多く存在しないこともあり、また、国によっては、M&Aの準拠法は自国の法律が適用されるとする国もあることもあり、日本法を準拠法とすることに了解を頂く必要があるものと思われる。 ■■■第29条■■■■■■■■■■第29条 (専属的合意管轄)売主及び買主は、本契約に関する争いについて、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることにあらかじめ合意する。 |
第29条 解説第29条は 専属的合意管轄の規定である。 この規定がない場合は、民事訴訟法4条が適用になり、被告の所在地の裁判所が管轄になるため、売主又は買主のいずれが訴訟提起するかにより、管轄裁判所が異なってくる。 しかし、専属的合意管轄の規定を入れることにより、株式譲渡契約について紛争になった場合の管轄裁判所が一義的に明確になるのである。 この管轄裁判所をどこにするかは、多分に、交渉力によって決定することが多い。 また、専属的合意管轄は、売主の管轄裁判所又は買主の管轄裁判所になることが多いが、売主が原告になる場合は買主の管轄裁判所、買主が原告になる場合は売主の管轄裁判所と相互主義的に規定することもあるし、売主の管轄裁判所とも買主の管轄裁判所とも異なった第三の裁判所を指定することもある。 また、紛争解決は裁判所ではなく、仲裁機関で行うこととし、仲裁機関を指定することもある。特に、国際的な取引の場合、他の国の裁判所の判決については、他の国で承認・執行することができない可能性がある。例えば、日本の裁判所では、米国や韓国などの判決は承認・執行されることが可能であるものの、相互主義の観点から、中国の判決は承認・執行されないため、中国人又は中国法人が当事者になる場合、中国の裁判所を管轄指定することは意味をなさない。 他方、ニューヨーク条約に基づいて、中国の裁判所においても、日本の裁判所においても、仲裁機関の決定は承認・執行されるため、中国人又は中国法人が当事者になる場合、管轄裁判所の合意をするのではなく、仲裁合意をすることも多い。 なお、第28条とも関連するが、準拠法の合意をしたとしても、管轄裁判所が、準拠法の合意をした国と異なる場合、管轄裁判所において、その準拠法に基づいて審査することは、事実上困難である。そのような場合、管轄裁判所は、事実上、自国の法律に基づいて事案を検討し、審理を進めることとなる。したがって、外国人に対して、事業承継M&Aを実行するような場合は、準拠法もしかりではある者の、特に、管轄裁判所を日本の裁判所とする必要があるものと思われる。 ■■■第30条■■■■■■■■■■第30条 (誠実協議)本契約に定めのない事項及び本契約の各条項の解釈に疑義が生じたときは、法令・慣習に従い、誠意をもって、売主及び買主が協議の上、解決を図るものとする。 |
第30条 解説第30条は、誠実協議義務の規定である。 日本人であれば、紛争について訴訟提起する前に誠実協議をすることは当然の前提のように思われるが、世界的にも必ずしもそうではない。また、日本における大企業においても、誠実協議の規定が存在することを根拠に、いきなり訴訟提起や交渉謝絶をするのではなく、社内検討の結果、まずは協議することとしようかと意思決定されることもある。また、誠実協議の規定が存在しない場合、同規定が存在しないことに不安を覚える当事者は存在するようであり、株式譲渡契約書においても、誠実協議義務の規定を入れることが一般的である。 署名欄■■■署名欄■■■■■■■■■■| 【署名欄】 本契約締結の証として、本書を2通作成し、甲及び乙それぞれ記名・捺印の上、各自1通を保有する。 平成 年 月 日 売主:住 所 名 前 買主:所 在 地 会 社 名 代表取締役 |
署名欄 解説署名欄である。 なお、株式譲渡契約書を何通作成するかは、当事者の数により、各当事者が1通ずつ保管することが通常であるものの、売主が複数の場合、少数株主については、写しを作成して保管することもある。 代表者が署名押印しない場合についてまた、事業承継M&Aの買主が大企業の場合、代表取締役ではなく事業部長などが署名押印することもある。しかし、事業部長などは、必ずしも、会社の代表権は有しておらず、代表権がある者から代理権を与えられているかどうかは明らかではない。そこで、本来的には、売主としては、買主に対して、代表権のある者の署名押印を求めることが原則である。 この点、株式譲渡契約書に代理権を有しない事業部長などが署名押印し、後日、クロージング前に、対象会社の業績が悪化したような場合、買主の代表権を有していないものが署名押印していることをもって、買主が対象会社の買収を拒否することも十分考えられる。筆者らに実際に相談のあったケースでは、株式譲渡契約書ではないものの、通常の取引契約書の基本合意書などで、代表権がある者が署名押印していないことをもって、無責任な態度を取られたことも存在する。判例としても、代表権がある者が署名押印していない場合は、契約責任は発生しないとするものは多く存在するとの理解である。 ただ、買主がどうしても代表権を有する者の署名押印が困難だということであれば、その理由をしっかり確認し、その事業部長などの代理権の存在を委任状などで確認し、表明保証にその事業部長などが代理権を有する旨規定しつつ、その事業部長などの署名押印により株式譲渡契約書を締結することもある。 |
⇒M&Aの条件を改善する方法を見る! |