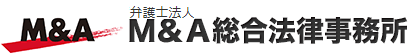株式交付制度は、新たなM&A(Mergers「合併」and Acquisitions「買収」の略で、企業の合併買収を意味する言葉)の手法として、2019(令和元)年の会社法改正によって導入され、2021(令和3)年3月1日に施行されました。
2019年の会社法の改正では、会社をめぐる社会経済情勢の変化に鑑み、株主総会の運営および取締役の職務執行の一層の適正化を図ることを主な目的として改正がおこなわれました。その中で株式交付制度は、M&Aにおける買い手が売り手から株式を譲受し、その対価として買い手の自社株を交付できる制度として導入されています。
この記事では、株式交付制度という言葉の意味や、株式交付制度を利用するメリットおよびデメリット、株式交換との違いなどをわかりやすく解説します。
株式交付とは
株式交付制度とは、例えば、A株式会社がB株式会社を子会社化するために、B株式会社の株式を譲り受け、その対価としてA株式会社の株式を交付する制度です。
2021年3月、2019年に公布された「会社法の一部を改正する法律案(会社法の一部を改正する法律案)」が施行されました。この改正法において株式交付制度が創設され、これに対応する税法上の改正が令和3年度税制改正に盛り込まれました。
株式交付制度の仕組み
株式交付制度の用語を確認しましょう。
A株式会社がB株式会社を子会社化するケースでは、A株式会社を「株式交付親会社」、B株式会社を「株式交付子会社」と言います。
株式交付で当事者となるのは、株式交付親会社と株式交付子会社の「株主」です。
株式交付親会社は、株式交付子会社の株主から株式を個別に譲り受けて、その対価として自社の株式を交付する形になります。
株式交付子会社の株主は、株式交付に応じるかどうかは、それぞれが任意に決めることができます。
株式交付に応じない株主は、株式交付子会社の株主のまま留まることが可能です。
そのため、株式交付後は、株式交付親会社が株式交付子会社を完全に子会社化できるとは限らない仕組みになっています。
株式交付制度が作られた背景
株式交付制度が作られた背景としては次の4つを挙げることができます。
- 株式を対価とするM&Aニーズ
- 株式交換および現物出資に見られる課題
- 組織再編税制の課題
- 産業競争力強化法の問題点
M&Aでは、親会社側は対価を支払う必要がありますが、買収資金を調達するには大きな負担が掛かります。
その点、株式を対価とすることができれば、負担を軽減することができます。
M&Aにおいて、株式を対価とする手法としては株式交換がありました。
しかし、株式交換は、子会社の発行済株式をすべて取得しなければならず、完全子会社化することまでを企図していないケースでは利用できません。
また、子会社の株式を現物出資財産として、これに対して親会社が株式を発行する方法もありますが、現物出資は検査役の調査に時間やコストが掛かったり、引受人等が財産価額塡補の責任リスクを負わされたり、有利発行規制の適用を受ける可能性があります。そのため、実務上はほとんど利用されていません。
さらに、組織再編税制の面でも、自社株式以外の対価が含まれる場合は、売り手側企業の株主には譲渡益課税の繰延べが認められず、売り手側企業自体にも時価評価課税がなされるなど、不利な面がありました。
なお、これらの点は産業競争力強化法の特例を受けることにより回避することも可能でしたが、そのためには、事業再編計画・特別事業再編計画に係る主務大臣の認定を受ける必要があるなど手続きが複雑だったために利用が進みませんでした。
そこで、株式を対価として容易に親子会社関係を創設できる制度として株式交付制度が創設されました。
株式交付が用いられるシチュエーション
株式交付が用いられやすい代表的なシチュエーションは次の7つです。
- M&Aの資金調達が困難である
- 買収対象企業の経営株主に経営のインセンティブを付与したい
- 完全子会社化までは考えていないが過半数の株式を取得したい
- 対象企業にコンタクトできない株主がいる
- 自社株式の株価が割高である
- 自己株式・金庫株を活用したい
- 資産管理会社に株式を移したい
株式交付は、株式を対価とすることができ、買収資金を調達しなくてよいため、M&Aの資金調達が困難な場合でも利用できます。
また、親会社の株式は子会社の株主に対して交付するため、完全子会社化まで想定していないケースでも利用可能です。コンタクトできない株主がいる場合でも問題ありません。
なお、株式交付により自社株式が希薄化する懸念もありますが、親会社の株価が割高なら交付する株式を抑えられるので利用しやすいでしょう。
自己株式(金庫株)を多数保有している場合は、株式交付で活用することができます。
さらに、株式対価が対価総額の80%以上となる株式交付なら譲渡所得税が掛からないため、子会社の株主にとっても有利な制度と言えます。
このように株式交付は、様々なシチュエーションにおいて使い勝手が良い制度になると考えられます。
株式交付と他制度の違いを比較
本章では、株式交付と類似する他の制度(スキーム)との間に見られる違いについて取り上げます。
株式交換との違い
株式交換とは、完全子会社となる会社(対象会社)の発行済株式のすべてを完全親会社となる会社(株式会社または合同会社)に取得させる手法のことです。株式交換の実施を通じて株式を取得した会社では、対象会社に対して100%の完全支配関係が生じます。
株式交換では、その実施によって完全子会社化する予定の株主の株式をすべて交換しなければならないのに対して、株式交付制度ではすべての株式を対象とすることだけでなく、一部の株式を対象とすることも認められています。
そのため、株式交付制度は、株式交換と比較して選択肢が多いため、比較的活用しやすい制度だと考えられています。
現物出資との違い
現物出資とは、会社設立にあたって、金銭以外の財産(例:不動産や設備など)で出資をおこなうことです。
現物出資は会社設立にあたり出資金に回せる手元資金が少ない起業家には心強い制度ですが、出資財産の過大評価により、出資者が実際の価値より多く株式を取得するなどの不正が起こりかねないことから、制度を利用するうえでさまざまな規制があります。
例えば、現物出資では、裁判所選任の検査役と呼ばれる専門家によって、出資された財産の価値が適切であることの証明を受ける必要があります。また、会社法第五十二条において、会社設立にあたって現物出資財産等の価額が定款に記載された価額より著しく不足するときは、発起人及び設立時取締役は不足額を支払う義務を負うと定められているなど、現物出資の活用にはさまざまな課題があります。
他方、株式交付制度では、基本的に上記のような問題点が活用の妨げになることはありません。そのため、現物出資と比較して、株式交付制度は活用しやすい制度だと考えられています。
株式交付のメリット
ここまでの解説で株式交付制度の概要を把握したところで、本章ではM&Aの実施にあたって株式交付のスキームを用いることで期待されるメリットとして代表的な5つをピックアップし、順番に解説します。
完全子会社化が不要となる
前述のとおり、株式交換の手法を通じた組織再編行為をおこなう場合、対象となる子会社を完全子会社化する必要性があります。
また、株式交換をおこなう場合、親会社の株式が子会社の株主に交付されることから旧子会社の株主は親会社の株主に新たに加わりますが、このことが原因となり株主同士の意見が対立すると社内で混乱が発生し最悪のケースでは経営が悪化する可能性があります。
他方、株式交付であれば対象企業を完全子会社化しなくてよいことから、経営上必要な持分までの株式の取得にとどめることができ、株式交換をおこなう場合のようなトラブルが生じる可能性を抑えられます。
資金調達の負担を減らせる
株式交付の手法を通じて対象企業を子会社化する場合、対価として対象企業の株主に自社株を交付するため、現金を対価として子会社化する場合と比較すると資金調達の負担を減らせます。なお、この「資金調達の負担を減らせる」というメリットは株式交換でも同様に得られるものですが、その負担の軽減度合いが両者の手法では大きく異なります。
株式交換によって完全子会社化するためには、対象企業の株主に交付する内容が自社株と現金を問わず、費用として相応の金額が求められます。
とはいえ、そもそも子会社の支配権のみを必要とする場合には、子会社の株式を100%取得し完全子会社化する必要はありません。なぜなら、対象企業について、半数超の株式を取得していれば子会社化自体は可能であるうえに、3分の2超の株式を取得していれば株主総会における特別決議で承認を得ることが可能となるためです。
したがって、対象企業を完全子会社化することを元来希望していないケースでは、株式交付の手法を用いることで、資金調達の負担をさらに軽減することが可能です。
以上の点を踏まえて、株式交付制度を利用すると、少ない資金で大規模な買収をおこなうことが可能です。具体的には、上場会社の買収など大規模な買収でも少額の資金で実施することが可能で、今後、株式交付制度の活用が拡大することが見込まれています。また、スタートアップやベンチャーが上場企業と資本提携をおこなうケースなどにも活用されることが想定されています。
非上場企業の場合、正確な市場価値の測定が難しく、現金化することが困難であるため活用が難しいものの、上場企業であれば市場価格がついていることから、現金化が容易であり株式交付の対価として適していると考えられています。そのため、株式交付制度の活用の方法として、買い手側が上場企業となるケースが想定されています。
税制上のハードルを下げられる
株式交換により組織再編を進める場合、税制上の優遇を受けるためには適格株式交換として認められるための適格要件を満たしていることが必要不可欠です。
適格要件を満たすための要件は、その形態によって3種類に分かれていますが、最も要件が少ない「完全支配関係」のケースであっても、以下の2つを満たすことが求められます。
- 完全支配関係の継続、もしくは支配関係の継続
- 株式以外の不交付
他方、株式交付の手法を通じた組織再編で適格要件を満たすためには、以下の要件を満たすのみで足ります。
- 株式交付を通じて交付された株式交付親会社の株式の価額が当該株式交付を通じて交付された金銭の額および金銭以外の資産の価額の合計額のうちに占める割合が100分の80に満たないケースを除く(租税特別措置法第六十六条の2の2第1項)
上記をいいかえると、株式交付で税制上の優遇を受けるためには、対価として支払う自社株の比率が全体の8割以上であることが唯一の条件として設定され、税制上の優遇を受けるにあたって適格要件を満たすためのハードルが低下しています。
税制上の優遇措置を利用できる
従来、株式交換を通じて交付された親会社の株式の時価が子会社の株式の取得価額と比べて高額であるケースでは、その利益に対して税金が課される決まりでした。
しかし、2019年の会社法改正によって、一定条件を満たした場合、この納税が繰り延べされて株式交付の実施タイミングでは税金が課されないことになりました(租税特別措置法第三十七条の13の3、租税特別措置法第二十五条の12の3)。
株式交付子会社の新株予約権を取得できる
2019年の会社法改正によって、子会社が新株予約権を発行している場合、株式交付の手法を通じて新株予約権を譲り受けることも認められるようになりました(会社法第七百七十四条の3第1項第7号)。
仮に新株予約権を譲り受けられないとすると、子会社化の実施後に予約権を行使されてしまい、親会社・子会社の関係が維持できないおそれがあります。ところが、新株予約権も譲り受けられることで、このリスクが解消されています。
株式交付のデメリット
M&Aの実施にあたって株式交付のスキームを用いることでさまざまなメリットが期待されますが、その一方で株式交付の活用には少なからずデメリットも存在します。
本章では、株式交付の実施にあたって、とりわけ発生すると問題となりやすいデメリットを4つピックアップし、順番に解説します。
株式会社のみしか子会社化できない
株式交付は、株式会社がその会社以外の株式会社を子会社化する目的のもと、対価として自社の株式を交付する行為であると定義されていることから、合同会社など株式会社以外の組織を子会社化することは認められません。
また、株式交付の実施対象は、日本で設立された株式会社に限定されており、外国法人を親会社や子会社にすることは不可能です。そのため、クロスボーダーM&A(国際間での取引のことで、M&Aの当事者のうち譲渡企業もしくは譲受企業のいずれか一方が外国企業であるM&A取引のこと)において株式交付を活用することは、現行の制度では不可能だといえます。
対象はすでに議決権の過半数を取得している会社のみ
株式交付は、自社以外の株式会社を子会社化するために実施される行為であり、すでに任意の企業の子会社となっている企業を対象にすることは不可能です。
対価の8割以上を株式としなければならない
株式交付の手法を通じた組織再編で適格要件を満たすためには、子会社に支払う対価の合計金額のうち8割以上を親会社の株式とする必要があります。したがって、株式に加えて現金なども交付するケースでは、株式以外の対価を全体の2割未満に抑えなければなりません。
新制度であり活用に関する情報が乏しい
株式交付は一見するとメリットが多く、株式交換と比べて魅力度が高いように感じられる経営者の方も多いですが、まだまだ情報量も少ないです。今後も、株式交付に関する新たな論点が登場し、これと同時に新たな課題も生じることが想定されます。
現段階では株式交付に関する情報が乏しいことから、常日頃から国税庁がリリースする株式交付に関するQ&Aなどを注意深く観察することも求められます。
特に国税に関して不明点があれば、国税局電話相談センター等で相談対応がおこなわれているため、相談窓口を確認したうえで電話相談を利用すると良いでしょう。
株式交付の手続き・流れ
株式交付の手法を用いたM&Aにおける買い手側(株式交付親会社)から見ると、株式交付は「部分的な株式交換」とも考えられる行為であり、実施にあたって株式交換に準ずる手続きが求められます。
本章では、M&Aにおける買い手側(株式交付親会社)をA社、売り手側(株式交付子会社)をB社と仮定し、A社に求められる株式交付の大まかな手続き内容と流れを解説します。
株式交付計画の作成
A社では、株式交付計画を作成し、これに以下の事項を盛り込みます(会社法第七百七十四条の2後段)。
- B社(株式交付子会社)の商号および住所
- A社が譲り受ける売り手側の株式の数の下限(議決権が50%超となるように定める必要)
- 対価として交付するA社の株式の数またはその算定方法
- A社の資本金および準備金の額に関する事項
- B社の譲渡人に対して交付する金銭等に関する事項(該当ある場合)
- B社の株式の譲り渡しの申込みの期日
- 株式交付の効力発生日
株式交付計画の承認
A社では、株式交付の効力発生日の前日までに、株主総会の特別決議によって株式交付計画を承認しなければならないのが原則です(会社法第八百十六条の3第1項)。
ただし、A社が交付する親会社株式を含む財産合計額が純資産額の5分の1を超えない場合、上記の手続きは求められません(簡易株式交付。同法第八百十六条の4第1項本文)。ちなみに、株式交付差損が計上されるケースや、買い手側が公開会社でないケースなどでは、簡易株式交付には該当しません(同法第八百十六条の3第2項、第八百十六条の4第1項但書)。
加えて、A社の株主に対する通知の日から2週間以内に、一定数以上の株主が株式交付に反対する旨を買い手側に対して通知した場合も、株式交付計画について株主総会特別決議を経なければならなくなります(同法第八百十六条の4第2項)。
株式交付計画書等の通知・株式譲渡の申込
A社は、B社における株式の譲り渡しの申込みをしようとする者に対し、株式交付計画の内容等を通知することが義務付けられています(会社法第七百七十四条の4第1項)。
そして、申込みをしようとする者は、申込みの期日までに、譲り渡そうとする株式の数等を記載した書面を買い手側に交付することが義務付けられています(同法第七百七十四条の4第2項)。
割当ての決定および通知
A社は、申込者の中からB社の株式を譲り受ける者を定めたうえで、その者に対して割り当てをおこなう譲受株式数を定める必要があります(会社法第七百七十四条の5第1項)。そして、A社は、効力発生日の前日までに申込者に対して通知することが義務付けられています(同法第七百七十四条の5第2項)。
ただし、B社の株式を譲り渡そうとする者が、A社が株式交付に際して譲り受けるB社の株式の総数の譲り渡しを行う契約(これを総数譲渡契約という)を締結する場合、申込みと割当てが総数譲渡契約の締結で完結するため、B社の株式の譲り渡しの申込みおよびA社が譲り受けるB社の株式の割当ての手続きに関する規定は適用されません(同法第七百七十四条の6)。
株式交付の効力発生
④の通知を受けた申込者は、B社の株式の譲渡人(会社法第七百七十四条の7第1項第1号)となり、効力発生日に通知を受けた数の株式をA社に給付し(同法第七百七十四条の7第2項)、A社の株主となります(同法第七百七十四条の11第2項)。
その他に求められる手続
株式交付では、その他の組織再編行為と同様に、事前開示書面および事後開示書面の備置き(会社法第八百十六条の2、第八百十六条の10)、差止請求(同法第八百十六条の5)、反対株主の株式買取請求(同法第八百十六条の6)、債権者異議手続(同法第八百十六条の8)をおこなう決まりです。
なお、上記の規定はA社の株主および債権者に対して定められているものです。
株式交付の税制・会計処理
続いて、株式交付の実施にあたって把握しておくべき税制と会計処理について、それぞれの概要を取り上げます。
株式交付の税制
株式会社の株主が自身の保有している株式を他者に譲渡するケースでは、有価証券の譲渡として課税を受けるのが通常です。そのため、従来は株式交付制度が導入されたとしても有価証券の譲渡に該当して課税される限り実務上用いられることは少なく、株式交付制度が広く活用されるためには課税の繰延措置などが必要と考えられていました。
そこで、2021年度の税制改正にて、株式交付に関する税制措置として「株式譲渡損益の繰り延べ」が盛り込まれました。もともと株式交付はM&Aの活用を促進する目的で創設された制度であるため、税務上でM&Aの実施ハードルが高まらないよう配慮されました。
上記の措置を具体的に説明すると、株式交付制度を通じて売り手側の株主が売り手側の株式を譲渡し、買い手側の株式等の交付を受けた場合に生じた譲渡損益に対する課税を繰り延べるものです。
株式交付の手法を用いたM&Aの対価は一部を金銭とすることも認められていますが、対価として譲り受けた資産の価額のうち株式の価額が80%以上であることが「株式譲渡損益の繰り延べ」を利用するための条件です。ちなみに、譲渡損益の金額は、株式交付の日にもとづいて算定されます。
他方で、上記で述べた株式交付に関する税制措置が、上場企業オーナーの私的な節税手法として使用されているとの指摘もなされており、専門家を中心に合理性や税制改正の必要有無などについて議論がなされています。
株式交付の会計処理
会社法上、2021年に株式交付制度が新たに施行されましたが、これに伴った会計基準の改正等は現在のところなされていません(2023年1月時点)。そのため、株式交付制度では、「企業結合に関する会計基準」を中心とする現行の会計基準をベースに処理します。
株式交付は、これと同じ組織再編行為として位置づけられている株式交換に準じて処理される仕組みです。
株式交付の注意点
本章では、株式交付を用いたM&Aの買い手側における実務上の注意点を解説します。
買い手側における売り手側株式の取得価額
買い手側における売り手側株式の取得価額は、売り手側株式の取得元の株主数によって、以下のようになります。
| 売り手側株主が50人未満の場合 | 当該株主における売り手側株式の帳簿価額に相当する金額 |
| 売り手側株主が50人以上の場合 | 売り手側の前期末時の資産の帳簿価額から負債の帳簿価額を減算した金額(当該前期末から当該取得日までの間の資本金等の額又は利益積立金額の一定の増減金額を加減算)に、発効済株式総数のうちに当該取得をした売り手側株式数の占める割合を乗ずる方法等により計算した金額 |
買い手側が上場企業の場合の注意点
株式交付における買い手側は、一般的には上場企業が担うと想定されます。このケースにおいて、買い手側は株式交付の対価として自社の株式を発行しますが、その発行が金融商品取引法上の募集(金融商品取引法第二条3項)にあたれば、買い手側は有価証券届出書の届出をおこなわなければならず(同法第四条1項)、その他の開示規制が適用されます。
加えて、改正会社法の施行により、株式交付の決定が適時開示事由と定められたことから、買い手側の取締役会が株式交付を決めたケースでは、その旨の適時開示が求められます(東京証券取引所有価証券上場規程第四百二条1項jの2)。
そして、買い手側で振替株式の交付をおこなう場合の手続きに関しては、社債および株式等の振替に関する法律で特則が設けられている点に留意が必要です(同法第百五十五条、第百六十条の2、第百六十一条など)。
売り手側が上場企業の場合の注意点
上場企業が売り手側を担うケースでは、株式交付による売り手側の株式取得に関して公開買付規制が適用されることから、会社法および金融商品取引法その他の諸規制を踏まえて、さまざまな問題が生じ得ます。ここからは、特に主要と考えられる内容に絞って注意点を解説します。
スケジュール調整
株式交付の売り手側を上場企業が担うケースにおいて、買い手側では会社法および公開買付規制その他の諸規制を満たすためのスケジュール調整が求められます。現金を対価とする公開買付けをおこなうケースでは、買付者が公開買付けを開始する時点で機関決定が下され、公開買付けの公表がおこなわれます。
株式交付の場合、株式交付計画について取締役会による決定だけでなく、株主総会特別決議による承認も義務付けられています(会社法第八百十六条の3第1項)。
買い手側の取締役会が株式交付計画の作成を決定した場合は適時開示をおこないますが、他方で公開買付けをいったん開始した場合、厳格な要件を満たさない限り、公開買付けを撤回できません(金融商品取引法第二十七条の11第1項)。
買い手側による公開買付け開始後、株主総会で株式交付計画の承認が得られなかったケースでは、株式交付を進められなくなるにもかかわらず、公開買付けを撤回できないという大きな矛盾に陥ります。したがって、株式交付による公開買付けを開始する前に、株主総会による株式交付計画の承認を得ておきましょう。
対抗買付けへの対応
株式交付で公開買付けの開始後に対抗買付者が登場した場合、買い手側としてはこれに対応するためにスピーディーに買付条件を変更する必要性が生じることが想定されます。
公開買付期間の延長については、買い手側では当初の効力発生日から3か月以内であれば、株主総会の再承認なくして効力発生日を延長できます(会社法第八百十六条の9)。
他方で、対価等の条件変更に関しては、再度の株主総会承認が必要とされるのが原則と解されています。株式交付における買い手側としては上場企業が想定されるところ、買い手側が臨時株主総会を開催するためには相応の時間と手間が発生することから、対抗買付者の動向を踏まえて迅速に対応することは困難なのが実情です。
株式交付の買い手側としては、公開買付けの開始前に株主総会で株式交付計画を承認する際、取締役会の裁量によって事後的な条件変更が認められるような決議を取っておくことができるかどうかが問題となります。
上記の点に関して否定的な見解も少なからず存在しますが、会社法が上記のような効力発生日の延長制度を設けた趣旨を踏まえれば、柔軟な解釈論もあり得ると考えられています。
例えば、株式交付計画で事後的な条件変更後の対価の数がある程度事前に判明するような対価の算定方法(同法第七百七十四条の3第1項3号)が策定されており、株主総会の特別決議で承認されていれば、希薄化防止など買い手側の既存株主の利益保護の要請を踏まえても、取締役会の裁量による事後的な条件変更も許容される余地があると考えられます(この点については、今後の解釈論と実務運用の集積が期待されています)。
株式交付の事例
最後に、過去に株式交付の手法を実際に用いた企業の事例として3件をピックアップし、順番に解説します。
テクマトリックス株式会社とPSP株式会社の株式交付事例
2022年1月、テクマトリックス株式会社はPSP株式会社を株式交付子会社とする株式交付をおこなうことを決議しました。また、テクマトリックスの連結子会社である株式会社NOBORIは、本件株式交付の効力が生じることを条件に、自社と本株式交付の効力発生後にテクマトリックス株式会社の子会社となったPSP株式会社との間で、PSP株式会社を吸収合併存続会社、株式会社NOBORIを吸収合併消滅会社とする合併をおこなうことを決議しました。
本件統合を通じて当事会社では、顧客基盤の拡大による医療関連ネットワークシステムサービスのシェアの増加、新規事業のサービス展開の加速及び製品やサービス面における機能強化や研究開発強化といったシナジーが見込まれることによって事業領域の拡大と企業価値の向上につながると見込んでいます。
トレンダーズ株式会社と株式会社クレマンスラボラトリーの株式交付事例
2021年12月、トレンダーズ株式会社は、株式会社クレマンスラボラトリーを株式交付子会社とする株式交付をおこなうことを決議しました。
本件事例では、トレンダーズ株式会社は株式交付制度を用いて、株式会社クレマンスラボラトリーが発行する株式20株をすべて取得しています。
なお、本件事例において、トレンダーズ株式会社は買収対価30,000千円のうち21,650千円を現金対価とし、残り8,350千円を株式対価としたため、株式譲渡損益の繰り延べの要件が満たされなかったものと推察されます。
本件株式交付を通じて、トレンダーズ株式会社では、自社が強みとするマーケティングノウハウを活用し、美容医療・再生医療領域におけるDX支援やマーケティング支援、医療施術・製剤および専売品の開発などに取り組むことによる業界課題の解決および自社グループのさらなる価値向上を図っています。
株式会社ソフトフロントホールディングスと株式会社サイト・パブリスの株式交付事例
2021年11月、株式会社ソフトフロントホールディングスは、株式会社サイト・パブリスを株式交付子会社とする株式交付をおこなうことを決議しました。なお、株式会社ソフトフロントホールディングスは、簡易株式交付の手続によって株主総会の決議による承認を受けずに本件株式交付をおこなっています。
本件株式交付を通じて、株式会社ソフトフロントホールディングスでは、ボイスコンピューティングを中心としたコミュニケーション基盤事業に加えて、コミュニケーション基盤の領域で近接し、事業内容を十分把握したうえで経営できる第二の事業の柱を獲得でき、安定した経営基盤を確保することを見込んでいます。
そのほか、 株式会社ソフトフロントホールディングスでは、株式会社サイト・パブリスの子会社化を通じて、隣接分野(音声・動画・ Web)における顧客基盤の確保および 、自社顧客への提供価値の拡大なども図っています。
まとめ
株式交付制度とは、2021年に会社法上に新たに創設された組織再編のスキームのことです。株式交付のスキームを用いる場合、買い手側では、M&Aなどにおいて他社を子会社化するために支払う対価として、自社の株式の交付が認められています。
実際のM&A案件において株式交付制度を活用するためには、案件の相手方との折衝だけでなく、思わぬ課税関係を回避するため税務面の詳細な検討・確認も必要とされるため、M&Aを実施する前に自らをサポートしてくれる弁護士に相談・依頼することを検討しましょう。