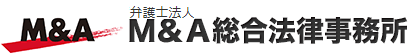M&A最終契約書 補償条項(インデムニティ)とは?
M&Aの契約書(最終契約書)において、補償条項は、表明保証や遵守事項に違反した場合など相手方に対して損害賠償請求ができるとする規定です。
M&Aの契約書(最終契約書)において、①の表明保証や②の遵守事項に違反した場合は、契約違反を行ったのですから、損害賠償を行うことは当然でもあります。
ただ、M&Aにおいては、①の表明保証や②の遵守事項に違反した場合、買主にいくらの金額の損害が発生したのかが明らかでない場合も多い反面、買主にいくらの金額の損害が発生したのかを証明するのは買主の立証責任です。この立証責任を果たすことが難しい場合がありますので、M&Aの契約書(最終契約書)においては、そのような場合などいろいろなケースを想定し、買主の損害を推定する規定を入れることもあります。
また、M&Aにおいて、損害賠償については、売主の立場から見ると、せっかく会社を売却したのに、M&A代金を返金させられる可能性があるわけですので、その地位は不安定となるのであり、例えば、資金需要があって会社を売却した売主などにとっては、切実な問題ともなりかねませんので、損害賠償請求の可能性を限定したいというのが本音のところかと思います。すなわち、売主からすると、M&A代金よりも多額の損害賠償を行った場合、会社を売却したのに、1銭も入ってこない状態と言え、経済的に不合理な結果になります。
そこで、M&Aの契約書(最終契約書)においては、損害賠償金額については、売主が受領した本件株式譲渡代金の○%相当する額を超えないものとするとか、また、損害賠償の請求は、○年内に損害賠償を請求する旨の書面が相手方から送付された場合に限るとか、または、単一の事実に基づく請求の額が金○万円を超えたものに限り行うことができるとする場合など、合理的な範囲に限定されることとなります。
他方、買主としても、決算を行う際に、対象会社の問題点がいろいろ発見されることがありますので、1回は決算期を跨ぎたい、すなわち、決算を行った際に発見された問題点を損害賠償請求したいという意向もありますので、M&Aの契約書(最終契約書)における損害賠償請求権の条件としては、最低でも1年ということとなろうかと思います。
M&A最終契約書の補償条項(インデムニティ)の解説
弁護士法人M&A総合法律事務所では、M&Aにおいて取り扱う主な契約書である秘密保持の契約書・基本合意書・最終契約書・附随契約書などのM&Aの契約書について、10年来、300件以上の豊富な経験を有していますので、契約書の契約者様の権利を守り、リスクを排除するため、適切なM&Aの契約書の作成及びアドバイスを提供させて頂いております。
その中でも、このページでは、M&Aの契約書のうち最も重要な契約書である最終契約書(株式譲渡契約書・事業譲渡契約書等)の「表明保証条項」について説明いたします。
M&A最終契約書の補償条項の法的性質
通常、私法上、故意又は過失により、相手方に対して、損害を与えてしまった場合は、損害賠償義務が発生する。債務不履行責任(民法415条)や不法行為責任(民法709条)である。
なお、債務不履行責任であれ、不法行為であれ、私法上は、加害者に故意又は過失などの帰責事由がない場合、責任は問われない。そのような場合は、損害賠償義務を負わなくてよいのである。
補償条項においては、もちろん、故意又は過失により、相手方に対して、損害を与えてしまった場合の損害の賠償・補償義務は含まれる。
それに加えて、補償条項において特徴的なのは、加害者に故意又は過失のいずれもない無過失の場合であっても、遵守条項違反や表明保証違反などを行ってしまった場合、その損害について、補償責任・損害賠償責任が発生する。
不可抗力的な事由により、遵守条項違反や表明保証違反などを行ってしまった場合も、補償責任・損害賠償責任を負うのである。
すなわち、補償条項では、表明保証違反などの補償義務・損害賠償義務が規定されている。そもそも表明保証というのは、特段、当事者が遵守を約束した事項ではなく、当事者に何らかの履行義務があるものではなく、当事者がその表明保証に違反しても債務不履行になるようなものではない。
実際、表明保証条項においては、表明保証は、何らかの約束をするとか、履行を約束するものではなく、そのような文言になっていない。単に、当事者が、対象会社などの客観的事実関係につき事実の表明をするのみなのである。事実を表明した結果、それが真実と異なっていた場合、債務不履行ではないものの、補償条項に基づき、表明保証違反などの補償義務・損害賠償義務の責任を負うのである。
M&A最終契約書の補償条項の重要性について
日本の民商法上、表明保証条項について、特段の規定は存在しない。かといって、そのように当事者が表明保証した内容が真実と異なっていた場合、表明保証をした者に特段の責任が発生しないのであれば、その虚偽の表明保証を信用した者(相手方当事者)が不慮の損害を被る可能性があり、その者(相手方当事者)をその損害から救済することは困難である。
また、むしろ、そもそも表明保証の役割としては、買主は外部者であり、内部者である売主であるオーナー経営者との間では、対象会社の情報につき絶対的な情報格差が存在するため、売主であるオーナー経営者に対して、対象会社の客観的事実関係について表明保証をさせ、それが真実と異なっていた場合に補償責任・損害賠償責任を発生させることにより、事業承継M&Aのリスクを、売主であるオーナー経営者に一部負担させるための規定である。
実務上、買主としては、事業承継M&Aに際して、対象会社に対して、デューデリジェンス(DD)を実施するものの、対象会社の調査を十分行うことができなかった場合や、対象会社の重要な事実関係について明らかにならないような場合、その事業承継M&Aの成否に十分に自信を持てず、事業承継M&Aを取り止めてしまうこととなる。しかし、対象会社の客観的事実関係のごく一部について、明らかではないということで、事業承継M&Aが取り止めになるというのは非常に不経済である。したがって、売主であるオーナー経営者が、対象会社の客観的事実関係について表明保証をすることにより、もしそれが誤っていた場合、買主に対して補償責任・損害賠償責任を負うこととすることにより、買主としては、その点が調査によって明らかにならない場合であったとしても、売主であるオーナー経営者のその表明保証を信用して、事業承継M&Aを実行することができることとなり、事業承継M&Aが実施し易くなるのである。
そういう意味では、表明保証違反などの補償義務・損害賠償義務が存在するからこそ、これらが存在しない場合には成立しないような事業承継M&Aも実施することができるようになり、社会経済に資するのである。
M&A最終契約書の補償期間について
このような表明保証違反などの補償義務・損害賠償義務であるが、当事者としては、補償義務・損害賠償義務を負担する以上、永久に負担するということも一考であるが(その場合でも消滅時効により5年又は10年で消滅するものと思われるが)、それでは負担が重くなってしまうことから、多くの株式譲渡契約書においては、期間制限が設定される。
また、表明保証違反などの補償義務・損害賠償義務に期間制限を設定しない場合は、事業承継M&Aの当事者は、その補償義務・損害賠償義務が発生することを恐れ、永久に損害賠償資金・補償資金を手元に準備しておく必要を感じることとなり、特に、事業承継M&Aの売主は、対象会社を売却し、その対象会社の売却資金を、自己の老後の生活資金や第二の人生を開始するための資金としたいと思っているにも拘らず、永久に、その対象会社の売却資金を使用することができなくなってしまう。
この表明保証違反などの補償義務・損害賠償義務の期間としては、多くの場合、1年から5年の間で設定されることが多いが、少なくとも1年以上にすることが一般的である。
すなわち、事業承継M&Aを行って1年以上経過することにより、対象会社は、少なくとも1回以上決算期を迎えることになるのだが、その決算期において、買主及びその税理士が決算を締める過程で、表明保証違反などが発覚することがあり、また、通常、買主及びその税理士は、その決算を締める過程で、表明保証違反などの事実がないかを全体的に検討することができ、表明保証違反などの補償義務・損害賠償義務の制限期間内に、表明保証違反などの補償義務・損害賠償義務の追及をすることができるからである。
この表明保証違反などの補償義務・損害賠償義務の期間制限について、買主としては、本来なら、1回の決算といわず、2回・3回の決算に際しても検証をしたいと思われ、また、1回だけの決算ではすべての表明保証違反などの事実を発見できるというようなものではないこともあり、2年や3年又はそれ以上の表明保証違反などの補償義務・損害賠償義務の期間を設定するものも多い。
また、個別の表明保証違反や遵守条項との関連では、対象会社の従業員の未払残業代の時効は2年であり、法人税の時効は最大7年であることや、一般の商事時効が5年であることなどに鑑み、その期間の間は、対象会社にそのような表明保証違反や遵守条項違反の事実が存在し、例えば、従業員から未払残業代を請求されるかもしれない、税務署から未払法人税を請求されるかもしれない、取引先からも未払を請求されるかもしれない、ということになると、表明保証違反などの補償義務・損害賠償義務の期間制限は、1年ではなく、2年や3年あるいはそれ以上の表明保証違反などの補償義務・損害賠償義務の期間を設定しないと、買主にとってリスクになってしまうケースも多く存在する。
また、土壌汚染のように、所有者である以上、時効の適用なく、永久に責任を負う可能性が生ずることもある。特に、事業承継M&Aにおいて、そのような事項が問題となった場合、表明保証違反などの補償義務・損害賠償義務の期間については、長期間設定されることも多い。
また、これらの個別項目ごとに、異なった表明保証違反などの補償義務・損害賠償義務の期間を設定することも多い。
M&A最終契約書の補償額の制限について
また、補償条項においては、しばしば、補償額・損害賠償額の制限が規定されている。
すなわち、補償額・損害賠償額の制限が存在しない場合は、理論的には、売主としては、表明保証違反などの補償義務・損害賠償義務を最大限負った場合、株式譲渡価格以上の義務を負う可能性がある。
すなわち、理論的には、対象会社の行う事業の社会的影響に鑑み、対象会社は、対象会社の株式譲渡価格よりも大きな損害を、第三者に与える可能性はある。買主は、対象会社を買収後、対象会社が何らかの表明保証違反行為などを行っていた結果、株式譲渡価格以上の損害を第三者に与える場合は、対象会社が株式譲渡価格以上の補償責任・損害賠償責任を負う結果、売主に対して、株式譲渡価格以上の補償請求・損害賠償請求を行うこととなる。
ただ、売主としては、この事業承継M&Aの結果、株式譲渡代金の額しか受領していないのに、それ以上の損害について補償請求・損害賠償請求される可能性があるということであれば、それ自体、大きなリスクであり、それであれば事業承継M&A自体行わないという判断になりかねない。事業承継M&Aにより、対象会社を売却することで、株式譲渡代金以上の損害を被るのであれば、対象会社は失うわ、トータルでマイナスであるから、そもそも、事業承継M&Aを実施しなければよかったということになる。
したがって、株式譲渡契約書の補償責任としては、最低でも、株式譲渡代金の額を超えないとされることが一般的である。
なお、事業承継M&Aにおいて、対象会社の株式価値を、実質的に、株式譲渡代金と役員退職慰労金その他の2つ以上に分けて、買主から売主に対して支払う場合は、株式譲渡契約書の表明保証違反などの補償責任・損害賠償責任の額の範囲としては、株式譲渡代金のみの額ではなく、株式譲渡代金と役員退職慰労金その他の合計額が基準となることが一般的である。
さらに、表明保証違反などの補償額・損害賠償額の制限について、株式譲渡代金の額から公租公課を考慮した手取り額の範囲とすることも多く、その場合、株式譲渡代金の額の80%とすることや、50%とすることもある。
また、そもそも、表明保証違反などの補償額・損害賠償額の制限について、株式譲渡代金の額の30%や20%とすることもある。これは、ひとえに、買主としては、表明保証違反などによる補償責任・損害賠償責任が発生する可能性をどの程度だと考えるか、あまり発生しないだろうと考えるか、この程度は発生するであろうと考えるかに依ってくる。
また、売主としても、株式譲渡代金を受領した後、直ちに資金使途がある場合などもあり、その資金使途に株式譲渡代金を費消した結果、株式譲渡代金の手残りが減ってしまう場合、そのようなタイミングで、買主から、表明保証違反などの補償請求・損害賠償請求が行われたとしたら、自己資金からの持ち出しになるような場合や、ひいては資金不足で破産しなければならないような事態になる場合もあり、補償額・損害賠償額の制限の額は、これらの事情などを考慮して決定されることが多い。
補償額・損害賠償額の制限について、実務上は、中間をとってということではないと思われるが、株式譲渡代金の50%とすることが最も多いように思われる。
しかし、補償額・損害賠償額の制限は、売主と買主の交渉力の関係で決定してくるものであり、景気循環の局面局面で大きく変わるように思われる。
M&A最終契約書の補償請求の最低金額について
また、補償条項においては、表明保証違反などの補償責任・損害賠償責任を負う場合として、単一の事情に基づく補償請求・損害賠償請求の最低金額が規定されている。
すなわち、例えば、対象会社の什器備品が壊れていたとか、対象会社のオフィスの壁にキズがあり賃貸物件の明け渡しの際に敷金・保証金から控除されるとか、少額の表明保証違反などが存在することはままあり、そのように、例えば、数万円程度の表明保証違反などによる損害が発生する都度、補償請求権・損害賠償請求権を行使されるようでは、事務が煩雑すぎて対応できないし、対象会社の事業を運営する過程において、それくらいの損害であれば数多く存在する可能性もある。他方、買主としても、まとまった金額の株式譲渡価格を支払う以上、その程度の金額であれば表明保証違反などによる損害も想定内であるという場合も多い。売主であるオーナー経営者としても、対象会社において、少額の表明保証違反などはあるかもしれないと考えつつも、重要な表明保証違反などは存在しないと考えていることが多いであろう。また、そもそも、軽微な表明保証違反などによる損害であれば、事業承継M&Aのクロージング後、買主による対象会社の事業の運営上、重大な問題にならないはずである。
したがって、最終契約書において、単一の事情に基づく補償請求・損害賠償請求の最低金額を設定し、軽微な表明保証違反などによる損害については、補償義務・損害賠償義務が発生しないこととすることが多い。
なお、単一の事情に基づく補償請求・損害賠償請求の最低金額を設定する場合、表明保証違反などが数多く存在し、その結果、すべての表明保証違反などによる損害の合計額が、この最低金額を超過したとしても、単一の事情に基づく補償請求・損害賠償請求の額が最低金額を超過していなければ、補償請求権・損害賠償請求権は行使できないこととされることが一般的である。
また、この単一の事情に基づく補償請求・損害賠償請求の最低金額を超過した場合に、売主から、買主に対して、その損害額の超過額のみを補償請求・損害賠償請求可能とする場合もあれば、その損害額の全額について補償請求・損害賠償請求可能とする場合も存在する。単一の事情に基づく補償請求・損害賠償請求の最低金額を設定する趣旨が、前述のとおり、数万円程度の軽微な表明保証違反などによる損害が発生する都度、補償請求権・損害賠償請求権を行使されるようでは、事務が煩雑過ぎることとなるのでこれを防止するとの趣旨に鑑みると、単一の事情に基づく補償請求・損害賠償請求の最低金額を超過した場合に、売主から、買主に対して、その損害額の全額について補償請求・損害賠償請求可能とすることが経済合理的であるものと思われる。
M&A最終契約書の特別補償条項について
前述のとおり、買主において、表明保証違反に関する認識があった場合には、表明保証違反の補償責任・損害賠償責任が認められないというのが、近時の裁判の傾向であり、また、株式譲渡契約書にいわゆるサンドバッキング条項を盛り込む場合においても、このいわゆるサンドバッキング条項が、裁判所で有効と判断されるか否か現状明らかではない。
したがって、近時においては、買主が、デューデリジェンス(DD)において、表明保証違反の状態を発見した場合には、表明保証条項のみならず(表明保証条項ではなく)、特別補償条項を別途規定することが多い。
特別補償条項は、表明保証違反とは関係なく、一定の事由が発生した場合に、売主に対して補償義務を負担させる規定であることから、表明保証違反の認識の有無によっては、その効果は変動しないはずであり、買主が、デューデリジェンス(DD)において、表明保証違反の状態を発見した場合であっても、補償請求権を行使することが可能と思われるからである。
M&A最終契約書の補償責任の履行の現実性について
事業承継M&Aの対象会社は中小企業・零細企業であり、そのオーナー経営者は、事業承継M&Aにより譲渡代金が入ってくるものの、もともと小規模事業者であり、その資力に鑑みると、買主が、売主であるその旧オーナー経営者に対して、この補償請求・損害賠償請求を行ったとしても、必ずしも、履行されるとは限らない。
そこで、この補償請求・損害賠償請求を担保するための手法の検討が必要であり、株式譲渡代金の分割払いや補償請求権・損害賠償請求権に対して担保提供をして頂くとか、株式譲渡代金を一定期間エスクロー口座に預かってもらうなどの対応が検討されることもある。
しかし、そのような旧オーナー経営者としては、老後資金などの資金ニーズがあったり、分割払いについては、2回目以降の支払いが実際に行われるかどうか不安だとか、担保提供に関しても、そのような担保がないとか、そのような提案は、売主である旧オーナー経営者が拒否することが多い。
そもそも、筆者らが相談を受けるケースにおいても、買主は、しばしば、クロージング後、事業承継M&Aに失敗したと認識した時、売主である旧オーナー経営者に補償させようとして、表明保証違反や遵守条項違反など、とにかく、何らかの理由をつけ、2回目以降の支払いを拒絶したり、担保権を実行しようとしたり、エスクロー口座からの出金を認めなかったりし、株式譲渡代金が宙に浮いたり、売主が、株式譲渡代金の一部返還を強いられていることが多い。
したがって、売主としては、株式譲渡代金の分割払いや補償請求権・損害賠償請求権に対して担保提供をして頂くとか、株式譲渡代金を一定期間エスクロー口座で預かってもらうなどの対応は、受け入れないことが一般的である。
そう考えると、買主としては、最悪、売主であるその旧オーナー経営者に対して、この補償請求・損害賠償請求を行ったとしても、履行されないことを前提に、事業承継M&Aを検討しなければならない。すなわち、事業承継M&Aの買主としては、十分に対象会社に対して、デューデリジェンス(DD)を実施したり、株式譲渡代金の価格についてよく検討を行ったり、事業承継M&Aのスキームについてもよく検討し、株式譲渡契約書などを良く作り込み、予めリスクヘッジをしておくことが好ましい。